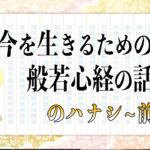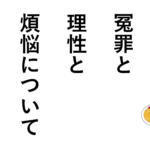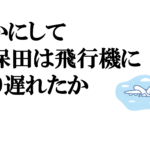スポンサードリンク
今回の記事も、以前にYouTubeで配信した「永平寺の配役、寮舎について」お送りします!
毎回お伝えしてますが、今からお話する永平寺内の配役、部署についてはあくまでも私が修行していた当時の配役となり、今は変わっているかもしれないので、その点ご注意ください。
だんだんマニアックな内容になって来ましたが、よろしくお願いします!
Contents
いくつの配役があるの?
永平寺内に様々ある部署のことを寮舎というふうに呼びます。
私が永平寺で修行していた時には、24の寮舎がありました。
ざっと紹介しますと
不老閣、監院寮、知庫寮、直歳寮、典座寮(大庫院)、侍真寮(真行)、知殿寮(殿行)、後単行寮、堂行寮、維行寮、講送寮、衆寮、祠堂殿、伝道部、受処、接茶寮、小庫院、参禅系、傘松会、人権室、国際部、吉峰寺、名古屋別院、紹隆寺
の24の寮舎です。
また、季節や行持によって臨時で設立される寮舎などもありますが、基本的には24の寮舎がありました。
これらの寮舎は、多いところで10名ほど、少ないところで3名ずつ配属され、期間は3ヶ月から半年ほどで、ローテーション(人事異動)していくことになります。
漢字の読み方について
監院寮、知庫寮、直歳寮、典座寮など、漢字と読み方が違うと思った方もいらっしゃるかもしれません。
曹洞宗や臨済宗などの、禅宗は中国の唐と宋の時代に使われていた唐音という漢字の読み方をするので、独特の読み方なります。
唐、宋は、日本では鎌倉時代に当たりますが、この時代に日本に入ってきた物や文化はそのまま唐音で使われています。
例えば、和尚、椅子や提灯、箪笥や西瓜などは、普段漢字ではそう発音しないですが、これらは唐音になります。
1年目で配属される寮舎
しかし、これらの寮舎は、1年目で配属される寮舎、2年目で配属される寮舎など、修行年数や条件によっていけるところいけないところが分かれています。
1年目、配属される寮舎は、衆寮、直歳寮、典座寮(大庫院and小庫院)、祠堂殿、伝道部、接茶寮、吉峰寺、名古屋別院 、紹隆寺の11の寮舎になります。
衆寮
永平寺の中では、時間によって太鼓や梵鐘などの鐘を鳴らすのですが、その鳴らしものや坐禅堂の管理をするところが衆寮になります。
この衆寮は1年目の1番最初に配属される寮舎になり、修行生活においての基本的な流れや生活を学ぶところになります。
また、1度きりの配属ではなく、2回3回と経験することになります。
直歳寮
永平寺の建物の管理や、修理修繕、整備を行う寮舎。
ですが、内容はもっぱらお風呂や永平寺内外の掃除になります。
私が永平寺修行中で、1番長くお世話になった寮舎です。
典座寮(大庫院and小庫院)
料理を作る寮舎。
永平寺内において典座寮は2つあり、1つは修行僧のみに食事を作る大庫院と、参拝者、参拝客に出す食事を作る小庫院があります。
祠堂殿
一般の人から依頼された供養、法要を行っている寮舎。
伝道部
参拝者に対して、参拝時の注意事項の説明や、永平寺内の案内を行う寮舎。
接茶寮
永平寺に泊まりにこられた方(参籠者)のお世話、案内をする寮舎。
秋の観光シーズンには多くの参籠者がいるため、季節によって激務となります。
吉峰寺、名古屋別院 、紹隆寺
永平寺以外にも、外寮舎と呼ばれる別のお寺に配属されることがあります。
吉峰寺は、永平寺から車で20分ほどのところにあるお寺。
道元禅師が、福井県に来た時に初めて身を寄せたお寺になります。
また、名古屋にある永平寺名古屋別院、鹿児島にある紹隆寺もありますが、外寮舎に配属される理由は様々あります。
心身ともに問題ない場合もありますが、中には怪我をしたり、永平寺の修行についていくことが難しいと判断された人が配属されたりもします。
2年目で配属される寮舎
2年目で配属される寮舎は、不老閣、監院寮、知庫寮、後単行寮、維行寮、講送寮、受処、参禅系、傘松会、人権室、国際部の11の寮舎になります。
これらは主に、行者寮と言う永平寺の重役の付き人をする寮舎と、少し専門的なことを行う寮舎などが2年目で配属されます。
不老閣
永平寺の住職、禅師様の付き人をする寮舎。
監院寮
監院と呼ばれるお寺の管理・監督を行う方の付き人をする寮舎。
禅師様を会社の会長とするならば、監院という役は社長のイメージといえばわかりやすいかと思います。
またその他にも、永平寺山内全般の事務や、対外的なことも行うので、会社で言うところの総務部と言えるでしょう。
後単行寮
後堂、単頭と呼ばれる、修行僧の指導をする方の付き人をする寮舎。
後堂、単頭は、会社でいうところの、専務、常務のイメージです。
維行寮
維那と呼ばれる、修行僧の指導をする方の付き人をする寮舎。
維那は、修行僧の配役を決める人でもあるので、会社でいうところの、人事部長のイメージです。
講送寮
衆寮の1年目修行僧を指導する寮舎。
知庫寮
永平寺山内の、物品やお金の管理をする寮舎。
受処
参拝者、参籠者の受付や、外部からの電話対応を行う寮舎。
参禅系
永平寺に坐禅体験にこられた方に坐禅指導をしたり、3泊4日の参禅研修のお世話、案内をする寮舎。
傘松会
永平寺から毎月発行される「傘松」と呼ばれる機関紙、広報誌の作成、発行をする寮舎。
人権室
毎月行われる人権学習の準備、運営をする寮舎。
国際部
海外の方の参拝者や参籠者がいた時にお世話、案内をする寮舎。
ただ、これらの寮舎は必ずしも2年目になってから配属されるというわけではなく、1年目の終わり頃から配属されることもあります。
また、1つの寮舎だけではなく、2つ3つ兼任するということもあります。
以上が、2年目までに配属される寮舎になります。
永平寺の中でもトップクラスにきつい寮舎
永平寺の修行において、関門とも呼べる場所が、侍真寮(真行)と知殿寮(殿行)と呼ばれるところになります。
侍真寮(真行)
永平寺の中でも特に聖域とされるのが、道元禅師や歴代の住職を祀る承陽殿と呼ばれる場所になります。
侍真寮は、この承陽殿を管理し、お護りする寮舎になります。
承陽殿をお護りする老師(責任者)のことを御真廟の侍者という意味で、侍真というのですが、侍真老師の行者(付き人)だから別名:真行と呼ばれます。

承陽殿
知殿寮(殿行)
永平寺内で行われる法要の準備や裏方を行う寮舎。
お釈迦様をお祀りしているところを仏殿というのですが、この仏殿を知っている、つまり仏殿をお護りする人のことを知殿と言います。
この知殿の行者(付き人)だから別名:殿行と言います。
法要の裏方で、基本黒子ではありますが、法要中に唯一動き回っているので「華の殿行」と言ったりもします。

仏殿
侍真寮、知殿寮は2年目以降、順次配属されていくことになります。
※侍真寮に行くには、嗣法をしていなければならないといった条件がありましたが、私が修行していた時にその制度は無くなりました。(平成25年頃)
どちらも行かなければならないというわけではなく、どちらかに配属されます。
この2つの寮舎はなんと言っても厳しい!
それまでの修行が生ぬるく感じてしまうほど、きついです!
言うなれば、自衛隊でいうところのレンジャー部隊です。笑
私は、2年目の10月に知殿寮に配属されましたが、配属をされた最初の頃は、毎朝1時半(朝と言えるのだろうか?)に起きて、掃除をしたり法要の準備をしたりして、休む暇がないくらい1日中動き続けているので、気を緩めたら簡単に意識を失えます。
立ったまま寝てしまう、止まった瞬間寝てしまうというのはザラにありましたが、とにかく体育会系の部署で、1ヶ月経つ頃には知らぬ間にムキムキになっていました。
私の人生の中では、1番苦しい経験をしたのは恐らく知殿寮だと思います。
しかし、知殿寮よりさらに厳しいのが侍真寮という・・・
恐ろしや。笑
この侍真寮もしくは、知殿寮を終える頃には3年目になっているので、それまで経験してきた寮舎の寮長になることができます。
ちょっと整理しますと、
・1年目、2年目で配属される寮舎が決まっており、人事によって異動していく。
・2年目以降からに侍真寮もしくは、知殿寮に順次配属されていく。
・真行や殿行を終えた人から、それぞれの寮長になっていく。
なので各寮舎には、1年目2年目の人と、3年目以降の寮長さんが1人もしくは2人いると言った様子です。
永平寺警察?
そして、最後にご紹介するのは堂行寮です。
堂行寮
法要において鐘を鳴らしたり、木魚を鳴らしたり、お経の題名を唱えたりする寮舎。
つまり、法要において最も重要とされる鳴らしものを担当する部署になります。
ここは、基本的には3年目以上の人が配属されます。
そしてこの寮舎の最も重要な役割が、1年目や2年目修行僧に対しての監視・指導役を担っています。
永平寺警察の異名を誇るほど、常に修行僧を見張っています。
例えば、法要に必要な持ち物を忘れたとか、荷物が散らかっていたとか、お勤め中に目をつぶっていた、などなど・・・
理由をあげたらキリがないです。
そして、捕まったら私たちの時は何かしらの罰がありましたが、どんな罰かはご想像にお任せします。
堂行寮=怖い!と言ったイメージです。
ただ私も堂行寮に配属されましたが、私はとても優しい方だったと思います。
禅活のしんこうさんが永平寺に入ってきたとき、私は堂行寮に配属されていました。
普通なら、1年目の時の堂行寮の人は絶対に会いたくない人ランキング上位に来るほど、怖い印象を持っています。
しかし、こうして禅活のメンバーとして一緒に活動しているということは、私が優しい先輩だったという証拠に他ならないのです!
堂行寮を終えた、4年目以降はどこかの寮舎の寮長をやっていると言う形になります。
永平寺の配役とは?
このように、一言で永平寺の修行僧といっても、それぞれの寮舎でそれぞれの動きがあるので、みんな同じ流れで動いているわけではありません。
前回、1日の流れをお話しましたが、朝4時の起床が決まっていたとしても、1時間前、2時間前に起きて掃除をしたり、ご飯を作ったりしている人もいますし、夜の坐禅の時に泊まりにきている人の布団を敷いている場合もあります。
なので、寮舎や配役によっては永平寺の行持に全く出れないところもあります。
そうするとやっぱり永平寺に修行に来たのに、布団ばっかり敷いてる、受付にいて字ばっかり書いてると思う人も出てきます。
ただ、修行というのは坐禅や掃除はもちろんですが、こうした配役1つ1つが全てが修行といえます。
永平寺に行くと感じるのですが、本当に一人一人が繊細に噛み合い、綿密な秩序の中で永平寺という修行道場が成り立っているのがわかります。
もちろん永平寺は建物自体も歴史があり美しい場所ではありますが、本当の意味での永平寺とは建物を指すのではなく、修行僧全体を通して修行僧一人一人が、永平寺という修行道場をつくりあげているのだと思います。
ということで、今回は「永平寺内の配役・寮舎について」説明させていただきました。
お読みいただきありがとうございました!