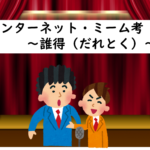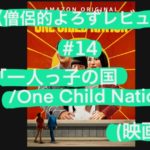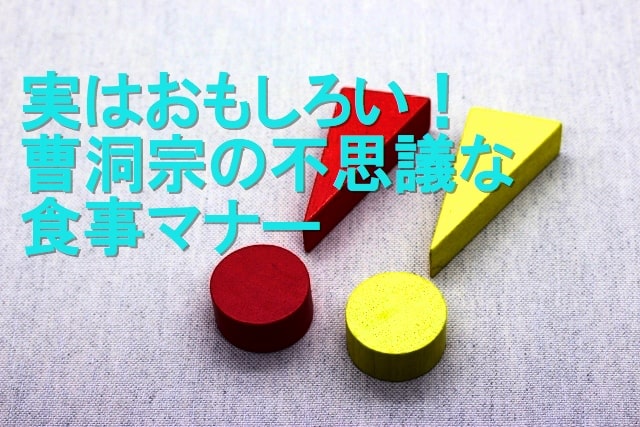
禅活-zenkatsu-は毎月精進料理のワークショップを開催しています。
そのワークショップでは一般的な精進料理教室よりも食べる作法に重点をおいています。
禅宗の食事作法というと、厳しくて、難しくて、敷居が高いというイメージがお有りの方も多いはず。
曹洞宗には『赴粥飯法』という食事作法について書かれた書物があり、ここには様々な食事のマナーも登場します。
私たちが今もこうして作法やマナーの実践ができているのは、ここで事細かに作法が記されているおかげです。
そしてこの『赴粥飯法』に登場する食事マナーのいいところは、当時の修行僧の様子が想像できるところです。
お釈迦様の頃から、修行生活で守らなくてはいけないルール、「律」は実際の事例に応じて定められてきました。
つまり、「律」があるということは実際間違いを犯した修行僧がいたということです。
今回ご紹介する食事のマナーはこの「律」に当たる部分。
これを踏まえて『赴粥飯法』を読んでみると、一見古文で書かれた厳かな文章見えますが、思わずクスッと笑ってしまうトリッキーな作法があるんです。
今回はそんな人いる!?と言いたくなってしまうトリッキーな食事作法をご紹介します。
動画版はこちら
Contents
マナー1:食べ物で遊んじゃいけません!
まずご紹介するのはこちらのマナー。
仏の言わく、「窣都婆の形を作りて食することを得ず」と。
「仏の言わく、」とあるようにこれはお釈迦様が仰った律をまとめた『四分律』というインドの律からの引用です。
お釈迦様は一体どんなことを戒められたのでしょうか?
窣都婆というのは
その原型となったインドの言葉に直すとストゥーパ、仏塔のことです。
窣都婆とは仏塔のことなんですね。

そこでこの一文を訳してみましょう。
仏様が仰るには、「仏塔の形を作って食べてはいけない」と。
…。
…本当に失礼を承知の上でですね、
誰がやるかい!
と思わず言いたくなってしまいます。
どれだけマナーがなってなくても仏塔の形にして食べたりしません。
ただ、思い出してみましょう。
このマナーがあるということは…そう、やった人がいたんですね(泣)
こんなことやる人いないとは思いますが、ここで説かれている意図を考えてみましょう。
解説
ここで説かれているのは、「仏塔の形」を作ることがダメなのではなく、簡単に言えば食べ物で遊ばないということ。
今更言うようなことではないのかもしれませんが、食べ物で遊ぶというのは、広く言えば命と向き合わないことです。
坐禅なら坐禅、食事なら食事、とただ一心に物事と向き合うのが、曹洞宗の修行であり生き方です。
そして食べ物というの、その命を活かしていきますという思いでいただくもの。
器に盛られた食べ物をコネたりいじったりせずに、ちゃんと正面から向き合いなさいということでもあるのです。

マナー2:となりの人のを羨ましがらないの!
続いてご紹介するのはこちら。
比坐の盋盂の中を視て嫌心を起こすことを得ず。
ちょっと難しい言葉がでてきましたが、比坐というのは隣に坐る人のこと、盋盂というのは修行僧が使う食器である「応量器」のことです。

そして嫌心というのは、くそーとかずるいとか、羨ましいというような心です。
つまり
隣の人の器の中身を見て羨ましがっちゃいけません!
ということ。
これすごくリアルなんですよ!
修行中は、隣の人のお粥に大きなお餅が入っているのを見ると、すっごく羨ましくて、悔しくて、ずるい!、よこせ!と思うんです。
昔からそうだったんですね(笑)
どうやら今も昔も修行僧は食欲に苦しめられていたようです。
解説
今言ったようにこれは修行生活としては超あるあるなんですが、外食した時に、自分のものより友達が頼んだ料理の方が美味しそう、なんてことは誰にでもあるはず。
ちなみに禅活メンバーで言えば本田さんは隣のテーブルまでしっかりチェックします(笑)
人が頼んだやつにすればよかったな〜と思いながらだと、当然その料理のありがたみは下がりますし、先ほどの向き合うということもできていません。
実は私たちの生活は、この比べっこする心に苦しめられていることがとても多いのです。
年収、学歴、成績、記録、色んな物を人と比べっこして、羨ましがっているうち、手元にあるものの価値を見失ってしまうのです。
一事が万事、まずは食事から、比べっこを離れよう、そんな意味があるのかもしれませんね。

マナー3:ご飯でおかずを隠しちゃだめ!
これはかなりトリッキーなものになります。
まずは原文
飯を以て羹を覆い、更に得んと望むことを得ず。
飯は炊いたご飯、羹というのは煮物などのおかずのこと。
つまり
ご飯でおかずを覆って隠して、もっともらおうとしちゃダメ。
そもそも私たちが思いつきもしないレベルのトリッキーなマナーです。
ただここに書かれているということは…いたんですねえ。やった人。

解説
ご飯でおかずを隠して更におかずをもらおうとするこの離れ業、思わず笑ってしまいますが、実は極悪な行いなんです。
そもそも、修行道場では食糧を確保・管理するということが大変で、修行僧全体に平等に食事が行き渡るよう、なんとか切り盛りしながら作られています。
それを自分が食べたいからといってご飯で隠してもらってないフリなんてしたら、絶対誰かの分が少なくなってしまうわけです。
自分の欲を満たすために嘘をつき、さらに得ようとする。
社会でやったら完全に犯罪ですよね。
「自分さえよければ」で行動して他人のことは考えない、これは仏教とはもっともかけ離れた行動です。
そう考えてみると、このマナーの中で言われているのは「欲をかいて行動を誤ってはいけません」という、とても重要なことなのではないでしょうか。

まとめ
いかがでしたか?
禅宗の食作法というと厳しさが強調されがちで、「たくあんの音をさせないように食べた」という経験をされたことのある方もいらっしゃるかと思います。
しかし、今回ご紹介した『赴粥飯法』で言えば、ご飯を音を立てて食べてはいけないという言い方だけされています。
曹洞宗の食作法やマナーは、例に挙げた3つのように、修行僧の気持ちをリアルに反映させ、なおかつ仏教の生き方が含まれた非常に実用的なものです。
一度先入観を忘れて、騙されたつもりで経験してみると意外な発見があるかもしれませんね!
(商品ページに飛びます)