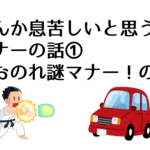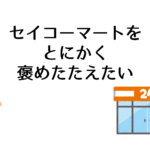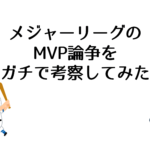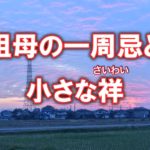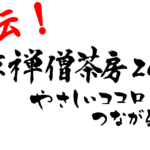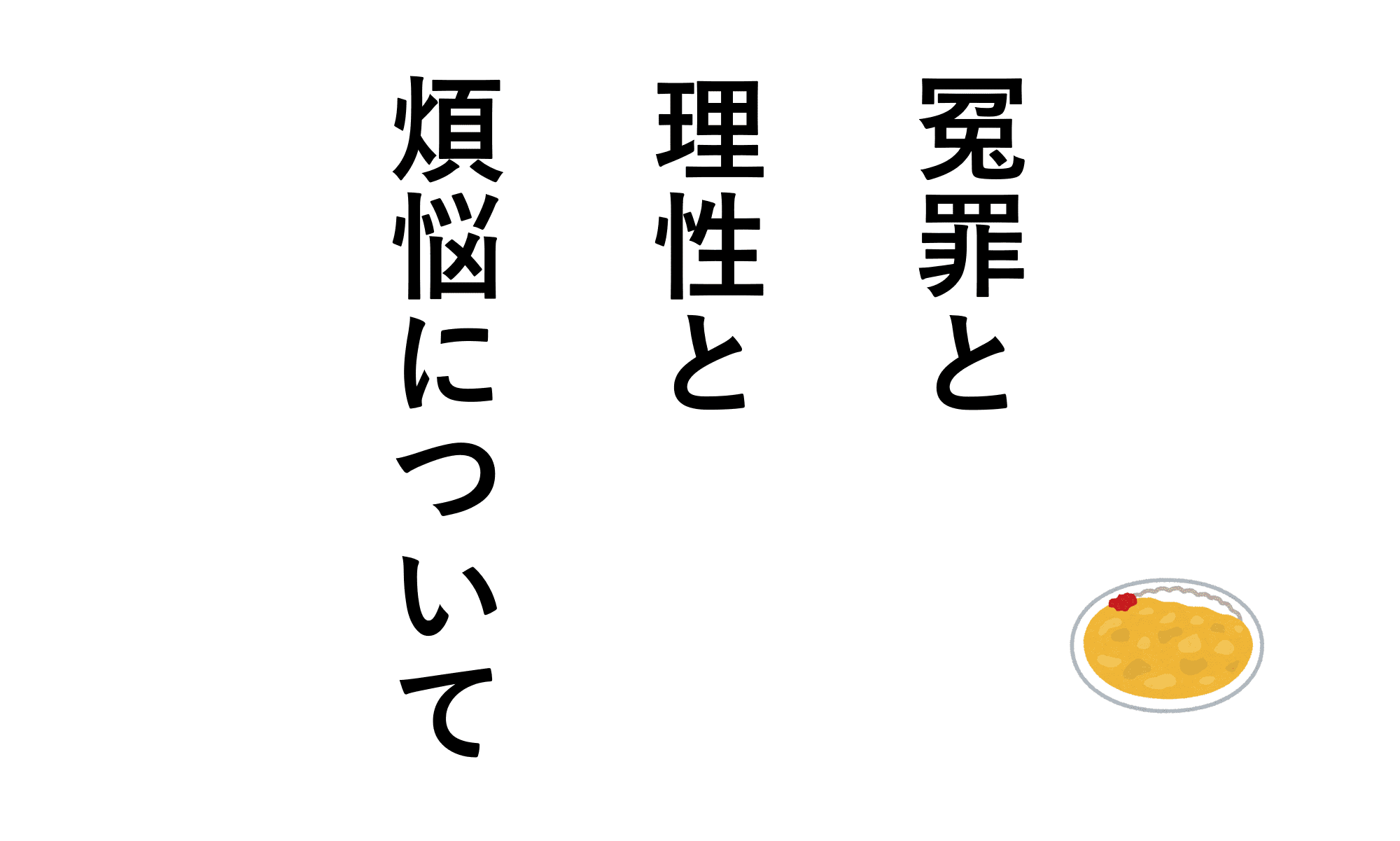
スポンサードリンク
去る6月11日、和歌山カレー事件の犯人とされ、裁判で死刑が確定している林眞須美さんの再審請求を地裁が受理したというニュースが流れました。
私自身、この事件については疑わしい点が多く、検察の立証が十分であるか疑問に思っていました。
報道によれば再審請求「受理」とのことですので、この請求によって再審が開始されるかはまだわからないという段階だとは思いますが、
多くの方が犠牲となり、さらには死刑という取り返しのつかない判決が出ている事件です。
少しでも疑わしい部分があるのであれば、審理を尽くす必要があると私は考えます。
今回の記事は、このニュースを足掛かりに、冤罪が生まれてしまう原因から人間の理性と煩悩について考えてみます。
Contents
冤罪を生み出す様々な問題
日本をはじめ、世界には数々の冤罪事件があります。
なぜ冤罪が生まれてしまうのか。
言わずもがな、この問題については様々な角度からの議論が必要です。
死刑制度の是非を含め、あらゆる観点からの問題提起が必要なテーマだとは思いますが、
今回の記事では特に、捜査、証言、再審制度について考えます。
門外漢ゆえ、認識不足も多々あるかと思いますが、素人の一意見としてご覧いただければ幸いです。
捜査の問題
昨年、取り調べの可視化(録音・録画)が法律で義務付けられましたが、
これまでの冤罪事件では強引な取り調べや拷問による自白の強要や、証拠の捏造が存在していました。
また、捜査のプロセスも問題視されることがあります。
実刑判決を受けた経験を持つとある政治家が、演説でこのようなことを言っていました。
「検察はまず最初に事件のストーリーを描きます。そしてそれにあった証拠を集めようとします。それで冤罪が作られていくんです。」
これが100%事実だとは思いませんが、先入観は人の判断を狂わせます。
「ストーリー」にそぐわない証拠の見落としや、あるいは黙殺が起きる可能性も否定できません。
……
それから、蛇足かもしれませんが、私の実体験を付け加えておきます。
経緯は割愛しますが、私はかつて一人の刑事の前で、自分の意に全くそぐわない反省文を書いたことがあります。
その方法は、
「刑事が口頭で述べた言葉通りに、やってもいない罪を認めて事実とは異なる文面を書き出す」
というものでした。
あまりの屈辱と情けなさに、目がくらみ、呼吸もままならなくなるほどの経験でした。
私自身、警察を信頼してはいるし、感謝もしている。必要な組織です。
しかし、こうした経験もあって、こと捜査や取り調べという点においては、疑問を呈さざるを得ないと私は考えています。
証言の問題
90年代になり、検察の科学捜査にはそれまでにはできなかった新たな検証方法が加わりました。
DNA鑑定です。
今では当たり前ですが、犯行現場に残された体液や体毛によって、容疑者の同定が高い精度で可能になりました。
このDNA鑑定の精度向上によって判明したことがあります。
それは、多くの冤罪事件に不確かな証言が関与しているということです。
ある論文によれば、アメリカでDNA鑑定によって冤罪であると判明した事件のうち、実に75%が不確かな証言が関与する冤罪であったそうです。
不確かな証言が何によってもたらされるか。
その要因は状況によって様々でしょうが、そもそも人間の記憶や判断がどれほど確かなものでしょうか。
たとえば、とある航空機事故では、存在しないはずのミサイルが航空機に向かっていくのを見たという複数の証言が寄せられたという事例もあります。
「あの時、あやしい人影を見たような気がする」が、気づけば「あやしい人物がいた」にすり替わっても何ら不思議はないのです。
人は偏見や先入観、限られた情報、想像力の働きによって、いとも簡単に判断を誤り、事実を都合の良いものに作り変えてしまうことがあるのです。
再審制度の問題
最後に、司法制度、とくに日本における再審制度の問題です。
日本では判決が確定した刑事事件について、年間およそ200件ほどの再審請求があるそうです。
それに対し、再審が認められるのは、年間数件程度。
200件に対し、数件しかないのです。
3審制度によってすでに十分な議論が尽くされているとする意見もありますが、数々の冤罪事件が示す通り、犯罪者になるということの重みと現行の裁判制度が釣り合っているとは私には思えません。
とくに日本において最も重い刑罰である死刑については、身の潔白を証明すべく再審請求を行っている最中に、刑が執行されてしまった事件もいくつかあります。
ここで死刑制度について詳しく語ることは避けますが、当事者にとって取り返しのつかない問題であるのに対し、再審がほとんど棄却されてしまう現状はおかしいのではないか、私はこのように思います。
以上、愚考ではありますが、冤罪を生み出す原因についてざっとまとめてみました。
法の原則として「疑わしきは罰せず」という言葉を聞きますが、果たしてそれは適正に機能しているでしょうか。
むしろ「疑わしき」で「罰せられている」からこそ、数々の冤罪事件が起こってしまっているように思います。
おそろしい「思い込み」の力
人間、一旦「こうだ」と考えたことはなかなか覆せないものです。
もう一つ私自身の実体験をお話ししましょう。
小学生の頃です、
「○○君の家が留守の間に、ちしょー君が上がり込んで勝手にお菓子を食べて、勝手にゲームをしていた」
といううわさが流れたことがありました。
もちろん身に覚えは一切ありません。
当然、
「そんなことはしていない」
と、主張しました。
しかし一切取り合ってもらえず、クラスメートとの付き合いがしばらくうまくいかなかった記憶があります。
結局、うわさの出どころもわからないまま、何となくなかったことになりましたが、
誰にも信じてもらえないという絶望感は今でも強烈に印象に残っています。

お互いがお互いの間違った「思い込み」を支持した結果、間違った「思い込み」が正当性を持ってしまう。
こうしたことは人類の歴史の中で数限りなく起こっています。
そこでは正常な判断はむしろ異端と見なされてしまうことでしょう。
あやしいという前提のもと、みんなであやしい証拠を探そうとすれば、誰しもあやしい人物となってしまうような気がします。
真実から目を背け、自分こそ正しいと思い込み、それに執着すること。
これが人間を苦しめる、根源的な煩悩です。
理性への妄信が生む煩悩
私たちが生きる現代社会は、人間の理性によって構築されました。
科学技術の進歩をはじめ、医療や建築など様々な学術的分野の発達。
過去の蓄積や、社会を生きるための経験知、世間知。
現代人がこれら理性がもたらした様々な恩恵の中に生きているのは疑いようのない事実です。
それだけに、その理性という働きを絶対的なもの、常に正しいものと思い込んでしまうのは、ある意味仕方のないことであるのかもしれません。
しかし人間の理性には限界があります。
すべての事象を読み解き、未来に起きることを完璧に予測することはできません。
古い理論が新しい理論に取って代わられたり、かつての常識が通用しなくなるように、完全でなく、どこかにほころびがあって当然です。
不完全なものを、完全だ、絶対だと信じ込んでしまえばその先には大きな過ちが生まれてしまうのではないでしょうか。
こうした不完全な理性が生み出す煩悩から逃れるにはどうすべきでしょう。
それには様々な変化を受け入れ、自分の判断や常識すらも疑い、時に手放すことが必要となります。
しかし、言うは易し、行うは難し。
すべての変化を受け入れていては身の置き所すらわからなくなるでしょうし、
常に自分を疑っていては社会生活なんて送れません。
まして、一度「こうだ」と信じたもの、苦労の末に手に入れたものを手放すことをできないのが人情というもの。
「明日から努力して理想の自分になるぞ!」なんて計画は超高確率で頓挫するものです。
では、どうすればよいでしょうか。
「絶対化しない」「考え直す」
正直なところ、私も煩悩に翻弄されている真っ最中ですから、「これが正解!」というものを安易に示すことはできません。
その上で伝えたいのは、
特定の人物・事物・思想・信条・知識などを「絶対化しない」ということ。
そして時に立ち止まり「考え直す」ということです。可能ならば、自分だけで考えずに他人の意見や書物を参考にするべきでしょう。
はじめの結論に固執せず、
過ちがある可能性に目を背けず、
議論を重ねることをいとわない。
この記事の出発点は冤罪事件でしたが、何事にも共通して必要な姿勢ではないでしょうか。
おわりに
長々と書いてしまいました。
ちなみに和歌山カレー事件について私は、
「マスメディアの報道によって、被告に不利な証言が生まれやすい状況が作られたのではないか」
「立証は十分ではないのではないか」
「林眞須美さんが事件の犯人かどうかは疑わしい」
と考えています。
最後にこの事件やその影響を受けて亡くなられた方々のご冥福を願いつつ記事を終えさせていただきます。
合掌。