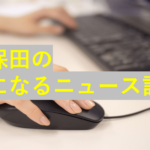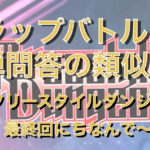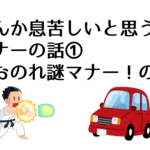スポンサードリンク
いつの間にやらもう12月。
「僧侶が駆け回るほど忙しい」という意味で12月のことを師走というのは有名なお話ですが、禅活メンバーは11月が忙しかったのでようやく一息、といった感じです。
ただし、12月に僧侶が避けて通れないイベントが「大掃除」です。
特に私の実家のお寺は大掃除ガチ勢なので、一週間くらいかけて本堂からリビングまでを掃除します。
永平寺でも大掃除はしますが、修行中に「うちの大掃除の方が大変だなあ」と思った記憶すらあります。
まあ、永平寺は建物が大きすぎたり、掃除にかけられる時間も限られているのに比べ、うちは小さくて、その気になれば全部掃除ができてしまう、ということではあるのですが…。
さて、そんな大掃除のシーズンになると「断捨離」というワードもよく目にするようになります。
いらないものを手放す断捨離は年末に気分転換ができて気持ちがいいですよね。
ただ、断捨離を仏教的に考えると、少し危ない面も持っているように私は感じます。
そこで今回は、断捨離が煩悩になってしまう可能性と仏教的な断捨離の心構えについてのお話です。
Contents
そもそも断捨離って何?
さて、話を進める前に、私自身が断捨離についてよく知らなかったので、その出どころについて少し調べてみました。
すると、元はヨーガの行法である断行・捨行・離行にルーツがあるのだとか。
それぞれの内容は
・断行:入ってくるいらないものを断つ
・捨行:持っているいらないものを捨てる
・離行:物への執着から離れる
といったものである様子。(wiki調べ)
なるほど、確かにこれは執着を離れるという意味では仏教とも近いところがあって、なおかつわかりやすいので流行語になるのもわかります。
ただし、実はここには一つ気をつけなければならない大きな落とし穴があるのです。

「無くしたい」という煩悩
断捨離のキーワードとなるのは「いらない」という、自分に不必要であるという判断です。
たしか、断捨離をする時のチェック項目などもあったと思いますが、断捨離をする人全員がそれを使っているわけではないはず。
物を手放して空っぽになった感覚、整頓された感覚というのは確かに気持ちがいいでしょう。
しかし、断捨離がブームになった時、家族の物を勝手に捨ててしまう人が現れて問題になったりしました。
これについては断捨離ブームの火付け役である作家のやましたひでこさんも「人の所有物を捨てるのは断捨離ではない」と断言しているそうです。
こうした例を見ると、断捨離に含まれる危ない面が見えてきます。
二種類のベクトル
実は人間の煩悩には二種類のベクトルがあります。
一つは煩悩としてイメージされやすい、求める欲望「有愛」です。
これは物や人といった目に見えるものから、愛情や名誉といった目に見えないものまで、自分の方に求める煩悩のことです。
喉が渇いた人が水を求めるような様子になぞらえて「渇愛」とも言います。
そしてもう一つは、反対方向の遠ざける欲望「無有愛」です。
自分の嫌いな物や人、立場や感情を遠ざけたい、無くしたいという煩悩のことです。
お釈迦様は王族の出身でしたが、王宮での贅沢三昧の暮らしをしていた頃と、出家をしてあらゆる欲を断った苦行生活をしていた頃を引き合いに出して、この両極端に近づいてはいけないとおっしゃっています。
理由は、帰ってこれなくなるから。
物欲のままに物をため込むのも、なんでもかんでも物を無くそうとすることも、やりすぎてしまえばその両極端となり、なかなか元には戻せなくなってしまうのです。
煩悩についてはこちらの記事で詳しく触れています。

無有愛の怖さ
そして、この断捨離における無有愛の怖さはどこにあるかというと、自分も他人も気づきにくいという点です。
欲張りで物を増やすのと違って、物を減らしている分には、自分も他人も良いことをしているように感じてしまいます。
しかし、物を捨てることで得た爽快感や満足感から、「物を無くす」ということに執着して行う断捨離は限りを知らず、いつしか他人の物にまで及び、トラブルとなってしまいます。
そしてトラブルになって周りが異変に気づいた頃には、本人はもう見境がつかなくなっているのです。
無有愛の煩悩としての性質はここにあります。
煩悩とは、一つ叶えば次の煩悩が生まれるというところに、その恐ろしさがあります。
自分の物を減らす、無くすということが達成されて満足すると、次は家族の物や他人にまで及んでしまう…まさに煩悩のはたらきといえるでしょう。

仏教的断捨離のポイント
しかし、このままでは「そんなこと言ってたら物を捨てられないじゃないか!」ということになってしまいますので、ここからは仏教的な断捨離の心構えをご提案いたします。
①「生かし道を考えること」を最優先
まず、最も大切にしたいのはこの精神です。
断捨離が目指していたのは、物に対する執着を離れるということだったはずです。
執着というものは、とりあえずゴミ袋に詰め込んでハイ離れた!といって離れられるものではありません。
なんとなく後ろ髪を引かれるようだけど、自分は生かし切れていないなあ、という時、その物がどうすればもっとも生きるのかを考えましょう。
ここで重要なのは、優先すべきは自分ではなく物です。
自己満足の為ではなく、物を生かすということを最優先にしてこそ、我を離れることができます。
その物の生かし道、生かせる在り方を考えることは、不殺生の教えに通じる非常に重要なことなのです。
②手間を惜しまない
不要なものには、
・自分には不要だけど人によっては必要なもの
・壊れたりしていて他人にとっても不要なもの
という二つのパターンがあると思います。
まだ使えるけど不要になったものの場合は、SNSや最近数多く出ているフリマアプリなどで、使ってくれる・役立ててくれる人を直接探すのがオススメです。
さらに発展途上国などでは、日本では古いとされる家電などが大活躍する場合もあるので、寄付という方法も考えてみると良いかもしれません。
発足に曹洞宗が関わっているシャンティ国際ボランティア会さんなどでも、そうした活動が行われています。
→シャンティ国際ボランティア会「もので寄付するプロジェクト」
そして、壊れてしまっている物、使えなくなった物の場合は捨てるしかなくなるわけですが、そういった物も手放し方次第では再利用やリメイクされ、形を変えて生かされる場合があります。
少なくとも自治体の決まりを守って、捨てるべき日に捨てましょう。
こうした生かし道を考えるのは手間がかかりますが、この手間を惜しまないことこそ、執着を離れる一番重要なことです。
人間の心は行動についてくるものです。
段階を踏んで手放すという過程によってこそ、心も徐々にその物から離れていくことができるのです。
もちろん不法投棄なんて言語道断ですが、大変でも手間を惜しまないこと、これが重要なんです。

まとめ
生かし道を考えることを第一として、その手間を惜しまない、これが私の考える仏教的断捨離です。
断捨離は仕事や人間関係にも応用されることがあるようですが、そこでも同じことが言えるはずです。
恋愛で言えば、相手の幸せを願うなら、別れることが最善であるということもあるでしょう。
仕事で言えば、その仕事がうまくいく為に他人に任せるべき時もあるでしょう。
しかし、それがわかっていながらなかなか納得できないのが、人間の心情というものです。
だからといって、自分の気持ちばかりを優先し、とりあえず捨てて、切り離して、遠ざけてあぁスッキリ!という断捨離は、繰り返すうちに視界を狭めていく可能性があります。
手放すことが辛いものも、むしろ近くにあることが辛いものもあるかもしれません。
しかし、手放すものの生かし道、言ってしまえば幸せを祈り、そのためには手間を惜しまないという在り方をすれば、断捨離は非常に仏教的な行いとなります。
物を捨てるのではなく、生かしていく。
せっかくなら、嫌いだから・いらないから捨てるのではなく、生かし方を考えるための断捨離が広まっていくといいなあと、私は思います。