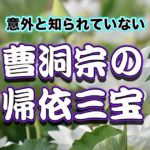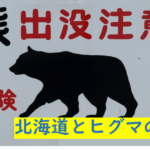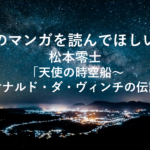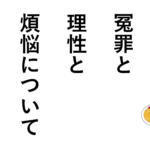毎月開催している精進料理&食作法体験ワークショップ「禅活しょくどう」では、
現在月替わりでメンバーの一人が法話を担当しています。
今回は私西田が『典座教訓』の「喜心」についてお話しした内容を掲載いたします。
本編
さて、ここまでいす坐禅と食事作法を通して、カジュアルな環境ながら曹洞宗の食の教えを実践していただきました。
度々お話ししている通り、曹洞宗には食事をする時の心構えを説いた『赴粥飯法』という書物があり、
今実践していただいた作法はその内容をご家庭でも実践できる形にアレンジしたものです。
一方で、食事を作る、調理に関する教えが説かれたものが『典座教訓』です。
『典座教訓』は、永平寺を開かれた道元禅師が、中国に渡ってご修行された際の経験をもとに、修行道場の食を司る「典座」という役職について著された書物です。
道元禅師が出家をされた鎌倉時代、日本では僧侶が自分で身の回りのことをする習慣がなく、食事の用意や洗濯などはお寺に仕える人の仕事であったようです。
道元禅師もそのような環境で僧侶として修行をされたわけですが、中国に渡ってみると大きく環境が異なりました。
食事や掃除、畑仕事や大工仕事のようなことまで、お寺に関する労働を僧侶自ら行なっていたのです。
これには仏教が伝わった過程と社会背景が関係しています。
お釈迦様がいらした頃のインドでは、出家者に衣食住を供養する習慣が社会的に根づいており、僧侶は労働や生産活動をせず、社会から離れて修行生活を送ることができました。
しかし仏教が伝わった中国には、そういった風習がありません。
また、時の権力者や社会状況によっても修行生活が左右されてしまうため、インドのように旅をするのではなく、寺院を建てて定住し、僧侶たちは生活環境を自ら整えていく形での修行生活を送るようになります。
この、修行生活に必要な労働のことを「作務」といいます。
一般的には庭掃除や草とりを想像されるかもしれませんが、修行の場である寺院の運営に必要なことは、調理も洗濯も、現代で言えば事務仕事もSNSの更新も、場合によっては作務なのです。
そのような経緯があって、道元禅師が修行した中国のお寺では、ご老僧が腰を折って海藻の天日干しをしたりしていて、その様子に大変な衝撃を受けられました。
この、作務が重要な修行となっていることへの感動が、『典座教訓」の根底にはあります。
実は『典座教訓』とは、典座という役職を強調しつつも、修行道場の維持や作務にあたる心構えを説いたものなのです。
そんな『典座教訓』の中で特に有名な教えが「三心」です。
道元禅師は、作務にあたる時に持つべき心を「喜心」「老心」「大心」の三心として説かれました。
よく、典座の心得として知られる三心ですが、『典座教訓』には
およそ諸々の知事・頭首の、職に当たるに及びて、
事を作し務を作すの時節は、喜心・老心・大心を保持すべき者なり
とあるように、作務の役職に当たった人が忘れてはならない心として説かれています。
そこで、今回から三回にわけて、私と原山さんと渡辺さんが、それぞれに一つずつ三心についてのお話をさせていただきます。
本日私がお話しするのは「喜心」です。
喜心とは喜悦の心、簡単に申し上げると「喜んで取り組む心」のことです。
『典座教訓』には、
今吾れ、幸いに人間に生まれ、而も此の三宝受用の食を作る、豈に大因縁に非ざらんや。
尤も悦喜すべきものなり。
とあるように、人間に生まれ、三宝に食事を供養できるということが、最上の喜びであると説かれます。
三宝というのは仏教信仰の要である、仏・法・僧、お釈迦様のお覚りと、そこに至る教え、そしてそれを実践する人々のことです。
修行道場では、修行生活を送る修行僧に、この禅活しょくどうでは参加費こそ頂戴してはいますが、作法を実践する私たちに食事が供養されています。
それならば実践する人、僧宝への供養ではないか、と思われるかもしれません。
しかし実は、修行僧もここにいる私たちも、お釈迦様の教えを実践し、実践によってその心を宿した存在であるため、仏・法・僧の三宝が一つになった存在としてここにいます。
この時間、実は皆様は三宝になっているんです。そんな三宝に他ならない実践者に対して食事を供養できることを喜ぶのが、典座にとっての喜心ということです。
私も永平寺では、修行僧や指導役の和尚様方の食事を作る役をいただいていたことがありました。
永平寺の食事は、必要以上に精がついてしまうという栄養面や、素人が食事を作るという衛生面も含めて、動物性食品を使わない、いわゆる精進料理です。
ただし、ここにいらっしゃる皆様との大きな違いは、その多くが進んで精進料理を食べているわけではない、ということ。
つまりお肉が食べたいんです。
私も学生の頃に食べていたファミリーマートのスパイシーチキンが恋しくて仕方ありませんでした。
そんな中で、初めて食べた車麩の唐揚げはセブンイレブンの唐揚げ棒の味がして、思わず坐禅堂の天井を仰いでしまいました。
そして、食事を作る役にあたった時、私はあの感動をみんなに届けたいと思いました。
いかに外の世界の味に近づけるか、という工夫に一番力を入れたのです。
醤油とみりんの味付けになりやすい厚揚げをトマト味で煮たり、こんにゃくを凍らせてお肉の食感に近づけるなど、色んな手を尽くしました。
そして、頑張った分だけ、食べた人から反響もあり、これが喜んで取り組む喜悦の心、喜心か!と思っていました。
これは調理に関しての経験ですが、先ほどお話ししたように三心は典座だけの心得ではありません。
法事やお葬式、このワークショップでも、お勤めしたことを感謝されたり喜んでもらえるたびに、私は喜心を感じているつもりでした。
しかし、これはいわば「やりがい」の一言で済んでしまうような、非常に一般論的といいますか、わざわざ道元禅師が書かれるようなことだろうか?と思ってしまうような内容に感じられないでしょうか。
そこで重要になるのが、「なぜ三宝へ供養できることが喜びなのか」ということです。
これを考えるきっかけになった出来事が、この一年のお寺でのお勤めでした。
私は現在、栃木県足利市の明林寺というお寺で、永平寺で役に就いている住職の留守を預かる形で、法事やお葬式などの、いわゆる檀務をお勤めしています。
以前から手伝いはしていましたが、一人でお勤めするようになったことと、何より、一人の方のお葬式から四十九日、一周忌と、時間の経過と共に一連の御供養を全てお勤めするようになったのはとても大きな変化でした。
人の死と一口に言ってもその様子というのは実に様々で、見送るご遺族の反応や対応も全く異なります。
そんな中でも特に印象に残っているお勤めがあります。
ある日、お寺の電話が鳴り、受話器を取ると、「もしもし、西田くんですか?」と聞かれました。声の主は、小学生の友人のお母さんでした。
とても明るくフレンドリーなお母さんで、大変お世話になった方です。
その電話の内容は、お母さんのお父上、友人にとってはお祖父様が亡くなり、まだお墓が決まっていないのでぜひ西田くんのお寺でお願いしたい、というものでした。
すぐに枕経に伺い、お勤めをしてからお父上の生前のご様子や今後のことを含めて色々とお話ししました。
お母さんは昔とお変わりない様子でしたが、明るく振る舞っている中に焦りや悲しみが見え隠れして、少し心配になったのを覚えています。
それから数日後にお通夜に伺うと、その場の誰よりも悲しみの色が濃く、枕経の時とは打って変わって憔悴しきった様子で棺のそばに立つお母さんがいました。
明るいイメージのお母さんが式中も声をあげて泣いていることに私は動揺しました。
それほどにお父上の存在は大きく、気丈に振る舞っていた分、溢れた感情も並々ならぬものがあったに違いありません。
そんなご様子を見て、私は自分では力不足だったのではないか、住職が勤めるべきだったのではないかと、申し訳ない思いを抱いていました。
葬儀からしばらくして、お仏壇の開眼、いわゆる魂入れに伺った際、お母さんは
「お葬式の時はごめんね。昔から知っている西田くんに頼めて本当によかった。今後の法事やお盆もお願いね。」
と穏やかな笑顔で仰ってくれたのです。
ご自身も様々な経験をされる中で、いつも支えてくれていたお父上を亡くし、悲しみに沈んでいたところから、また前に一歩を踏み出す。
悲しくても辛くても続く人生の一歩に、私のお勤めが必要だと仰ってくれたのです。
この経験から、私は「三宝に供養できる喜び」をこんな風に捉えることができるのではないか、と考えます。
三宝は、お釈迦様のお覚りとそこにいたる道、そしてそれを実践する人であるということは先ほどお話した通りです。
永平寺の修行僧は、みんなそれぞれに置いてきた人や物や、我慢している事、耐えていることがあって、それでも僧侶として生きていくために道を歩んでいます。
この禅活しょくどうに来られたみなさんも、ご自身のお仕事やお家のことや人間関係や悩み事、立場や責任を抱えながら、この場に足を運ばれ、食を通してご自身の人生と向き合い、道を歩まれています。
そう考えると、三宝とは「志をもって道を歩む人」のことでもあり、そこに供養するというのは「その歩みの一歩に関わること」という見方ができるのではないでしょうか。
『典座教訓』には、喜心についての説示の最後に、
能く千万生の身をして、良縁に結ばしめんが為なり。此の如く観達するの心、乃ち喜心なり。
という一節があります。
これは、
自分一人のものではなく縁によって循環していくこの身を良縁と結ぶために、私はこの作務を全うするのだ。と、このように道理を見抜いて事にあたることが喜心である
というものです。
志をもって道を歩む人は、その道中で様々な人や場所や物と出会い、そこに縁を紡いでいきます。
供養をお勤めしたお檀家さんが家族や親戚を幸せにするかもしれないし、食事を供養した人が誰かの人生を救うかもしれません。
その人の踏み出す一歩との縁が、自分一人では到底届かなかったようなところまで、私たちの行いを、人生を運んでくれるのです。
そして、自分の行いが思い掛けぬところまで縁を結んでいくと思って事にあたることが、喜心の本質なのです。
それは単に自分が嬉しいかどうかという世界ではありません。
自分の行動が果てしなく影響を及ぼすものであるということへの責任感と言ってもいいでしょう。
はじめにお話しした通り、喜心を含む三心とは調理をする時だけ、食事を供養する時だけのものではありません。
修行に必要な作務にあたる時の心構えです。
作務とは「作すべき務め」とも読むことができます。
人生という修行の中で作すべき務めがあったのなら、それは作務となり得ます。
私なら葬儀や法事もそうですし、皆さんならお仕事や家事一つとってもそうです。
相手が人であろうとものであろうと場所であろうと、目の前にした務めは、そこから良縁が紡がれていくことを願って全うする。
喜心、喜悦の心とは生き方そのものにも関わってくる心のことをいうのではないかと、私は考えています。
関連記事