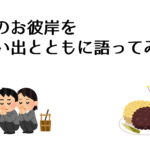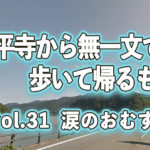毎月開催している精進料理&食作法体験ワークショップ「禅活しょくどう」では、
現在月替わりでメンバーの一人が法話を担当しています。
今回は原山佑成さんがお話しした法話です。
法話「精進する料理」
みなさん初めまして。
西田さん、渡辺さんと共に禅活しょくどうのスタッフとして関わらせいただいております、原山佑成です。
本日は私が修行時代に「食」と向き合うことの大切さに気付かされたお話をいたします。
私は今から6年前の2017年に、福井県にある大本山永平寺に上山しました。
永平寺の修行では修行僧それぞれに辛く感じることがあり、
その内容は千差万別なのですが、私の場合は特に悩まされたのが食事でした。
朝食はお粥とごま塩、梅干しと漬物。
昼食はご飯とお味噌汁とおかずが一品、そこに漬物、夜はおかずが二品に増えます。
品数を聞けばそこまで少ない印象は受けないかもしれませんが、
永平寺で出される食事には肉や魚などの動物性の食材を使われていません。
そのためか、大学を卒業したての私の舌は、
とても味気ない食事に感じられました。
また、食べる量も自分の好きなだけ食べられるわけではありません。
ご飯とお味噌汁は一度だけおかわりが出来るのですが、皆に行き渡るようにし、
なおかつ周りと食べる速さを合わせなくてはならないため、
好きなだけというわけにはいきません。
そのため、私はいつも「もっと食べたい」という気持ちと戦い、物足りなさを感じていました。
そして上山から少し経った頃、私に与えられたのは、
ご宿泊の方々の食事を作る「小庫院」という部署での、調理の役でした。
ここで重要なのは、小庫院にはたくさんの食材があり、さらには作って余った分を食べられる、ということです。
仮に、もし仮に、十人分の食事を作るときにうっかり十二人分作ってしまった場合、
余った二人分の食事を粗末にすることはできないので、ありがたくいただきます。
時には余ったご飯を無駄にしないように、とおにぎりにしたものが作務衣のポケットに入ったままになっていて、
ありがたく寝る前に食べていたことや、味見という形で料理を研究していたこともありました。
また、永平寺にいてお肉と同じくらい欲しくなるのが、甘い物でした。
そんな中で、食料庫を点検すると、調味料として氷砂糖が常備されているではありませんか。
万が一品質が落ちていたらご宿泊の方に申し訳がないので、私は毎日味の確認をしていました。
砂糖のはっきりとした甘さは、薄味なことが多い精進料理とは違った、強烈な刺激でした。
そして私はいつの間にか、暇さえあればその氷砂糖を口に入れるようになったのです。
そんな毎日を過ごしていたため、私の体重は大学生の頃よりも重くなっていました。
ここまで冗談交じりにお話ししましたが、
実際は「貪る」という言葉がふさわしいような食べ物を「食い漁る」生活でした。
やがて感覚が麻痺してしまったのか、いくら食べても「もっと食べたい、もっと食べたい」
と欲が止めどなく溢れてくるようになりました。
当然そのような食べ方に食作法も何もありません。
食べ物に感謝をすることもなく、欲に任せて食い漁る、
皆様が想像される修行とはほど遠い生活を送っていたのです。
そんなある日、小庫院の責任者であり、私たちの指導してくださる副典座にあたる
〝副典〟という役職の和尚さんから私はこんなことを問いかけられました。
「精進料理とはなんでしょうかね?」
私は咄嗟に、「肉や魚を使わない質素な料理のことです」と答えました。
すると副典さんは「もう少しよく考えてみなさい」とおっしゃいます。
次に私が、「一生懸命に頑張って作った料理が精進料理です」と絞り出すと、副典さんは次のようにおっしゃいました。
「精進して作り、そして精進して食べることによって、その料理は精進料理になるのです」
私はハッとさせられました。
当時の私は、役を与えられて食事を作ることは考えていても、
食べることに関しては全く考えていなかったからです。
精進というのは一心に仏道修行に励むことです。
そのため、仏道修行として一生懸命に作った料理は精進料理になると頭では理解はしていました。
しかし、精進して作るだけでなく、精進して食べる人がいることの重要さに、その時気付かされたのです。
次の日の朝、私は僧堂という建物でみんなと一緒に坐禅をしながら、応量器で朝のお粥を食べました。
それまでは量も作法も早さも自由にできない、苦痛な食事でした。
しかし、前日に副典さんから言われた言葉を思い出しながら、
作法に集中してみようと思い、お唱えごとをして、ゆっくりとお粥を味わって食べました。
すると今までに感じたことのない美味しさを感じたのです。
今までは、とにかく急いで、いかにたくさん食べるかしか考えていなかったからなのか、
味などはほとんど意識したことはありませんでした。
しかしその日のお粥はとても温かく、口に入れるとお米の甘みが優しく広がりました。
ゆっくり味わった後に飲み込むと、自分の喉を通り胃に入っていくのがわかります。
そのように一口一口をゆっくり食べていると、
この食事に生かされている自分自身に気づくとともに、お粥をありがたいと思えてきたのです。
道元禅師が食事をする際の心構えについて示された『赴粥飯法』に、このような一節があります。
是を以て法は是れ食、食は是れ法なり。
是の法は、前仏後仏の受用したもう所と為すなり。
此の食は、法喜禅悦の充足する所なり。
この意味は、
食事が修行として正しく実践された時、お釈迦様の教えは食に現れ、食もまた教えとしてそこにある。
この食と一体となったお釈迦様のみ教えは歴代の仏さまやお祖師さま方が実践し、
受け継いでこられたものである。
そうして目の前にした食事は、仏の教えに触れる喜びや心の安らかさを得る悦びに溢れるものである、というものです。
欲にまかせ、欲を満たすように食べ物を口に運ぶのではなく、
お釈迦様の教えに則って食事をする時、それはただの栄養摂取ではなく、
修行として、覚りとしての食がそこに現れるというのです。
そんなことを知らないかつての私は、ただ自分の食欲を満たすためだけに貪っていました。
しかし、改めて作法に目を向け、ゆっくりとお粥をいただいた時に、
食事によって生かされている自分に気づかされました。
そしてその一口一口が当たり前ではないこと、そのありがたみを感じながら、
ゆっくりと食事をすると、不思議と満たされるものがあったのです。
あの時私は「どのように食べるか」がいかに重要かということに気づかされました。
恥ずかしながら今でも慌ただしく動く東京にいて、せわしない食事をすると、
つい食べ方への意識が薄れてしまうこともあります。
食べたいものを食べたい時に、食べたい分だけ食べることができてしまう今こそ、
あの日の一杯のお粥が気づかせてくれたことを大切にしようと思います。
教えの実践として、精進としての食事にできるか、自分の食欲を満たすためだけのものにしてしまうのか。
その一食を「精進する食事」としての精進料理にできるかどうかは、毎食の自分にかかっているのです。

原山佑成