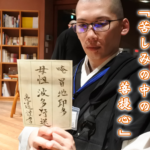スポンサードリンク
法は良薬なるがゆえに帰依す
曹洞宗のお経「修証義」では、仏教徒が法(教え)を心の拠り所とするのは、それが薬であるからだと、説かれます。
「修証義」に限らず、インドや中国の経典の中でも、こうしたお釈迦様の教えを薬に例えた表現は登場します。
これがどんな薬かというと、四苦八苦と言われる八つの「苦」を癒す為の薬です。
なるほど、心に抱えた苦しみや悩みとの向き合い方を示していく教えが、その薬であるというのは納得がいきます。
ただ、薬という例えにはもう一つの側面があります。
今回は私の修行時代を振り返りながら、仏教が薬と言われる理由について考えてみましょう。
Contents
修行中の出来事
ある朝
これは私が永平寺での修行中のお話です。
2年目を迎え、先輩僧侶の厳しい目は1年目の後輩達に向けられるようになったある日のこと。
私は当時、永平寺の広報誌「傘松」の編集室での役割が当てられ、お経を読んだり坐禅をする以外に、一眼レフで山内の行事や風景の写真を撮ったり、文章の校正などを担当していました。
そこでの朝の仕事の一つに、参拝に来られた方が「傘松」を受付カウンターに並べるというものがありました。
その日もいつも通りに、「傘松」を持って行きいい具合にレイアウトして、準備完了。
そこでふと、トイレの場所を示す立て看板の位置と違うことに気づきました。
永平寺では、こうした物を置く位置や向きまで細かく決めることで、整然とした山内を維持しています。
修行も2年目になると自然とそうした所に気づくようになるものです。
「昨日掃除をした人が動かして戻さなかったんだな。まったくしょうがないなあ。」
と立て看板を本来の位置まで動かし、手を離したその時。
バターーーーーン!
なんと看板の脚が根元から折れて倒れてしまったのです。
一辺が4~5cmはある、そこそこ太い角材がそんな簡単に折れるはずはなく、おそらく既に折れていたものを誰かが絶妙なバランスで立てていたのでしょう。
その場ではどうすることもできず、朝の仕事はまだ他にも残っています。
私は脚の折れた看板を一旦、あくまでも一旦カウンターに置いて、残りの仕事を終わらせる為にその場を後にしたのです。

ちょうどこんな感じの看板
案の定
嫌な予感がした皆様、その予感の通りです。
私はそのことをすっかり忘れ、誰かに報告をすることもなく日常の生活に戻ってしまったのです。
そして、文章を校正している時に一本の内線電話が。
同期の修行僧がなにやら焦った様子で対応していることから、先輩からの電話だとわかります。
おいおい、何をやらかしてしまったんだいと他人事と思っている私をよそに、彼は「はい、はい、ここにおります」と。
ん?誰かに代わるのかな?
「法雲さん(修行中の私の名前)、○○さん(先輩)から電話。。。」
え…、ぼく?汗
私は何かミスをしただろうかと、頭をフル回転させながら電話に出ます。
相手は5年目の大先輩。
永平寺を高校に例えるなら、5年目の先輩はもはや体育教師くらいの立ち位置。
先輩というにはあまりにも経験値が違いすぎてもはや先生の領域になる存在です。
一体何だろう…。
心あたりはないものの、心臓の鼓動が早くなるのを感じながら先輩の言葉を聞きます。
「法雲、看板壊した?」
心あたりあったーーーーーーーーー!!!!
忘れてたーーーーーーーーーー!!!!!
仕事が残っていたのが半分、そして自分のせいじゃないという思いが半分で、完全にそのことを忘れていました。
結果的に修行僧を指導する和尚さんが気づき、その方が建物や設備の管理を担当する5年目の先輩に連絡して、あの時受付カウンターにいた人に聞いて私が捜査線上に挙がったのです。
こうなっては事情もなにもありません。
私は自分が壊れた看板を放置したことを認めると、すぐカウンターに来るように言われ、電話が切れました。

鬼の待つカウンターへ
本当は一歩も行きたくない受付カウンターの方に、急いで向かう私。
たどり着くと、腕を組んで座る先輩。
もう全てを諦めその先輩の前に参じます。
怒られる…。
そう思っていると、先輩は「ついてきて」と一言。
あれ?怒られない?
あらゆる叱責・罵声を覚悟していた私は無言で先を歩く先輩についていきます。
着いたのはそうした備品の修理をしてくれる大工さんがいる山内の作業場でした。
そこで、壊れた看板を修理してもらうための申請をして、大工さんはあっさり承諾してくれました。
あまりにもあっさりとしていて呆気に取られている私に先輩は一言。
「大人なんだから、ちゃんと責任は果たして。」
そう言い残して去っていきました。
ようやく心にしみる言葉
私は幼い頃から両親に注意されてきたことがありました。
それは、何かをしたらしっぱなしだったり、面倒なことを後回しにする癖です。
ドアを開けっぱなし、椅子を出しっぱなし、料理をしたらしっぱなしという「ぱなし癖」や「後回し癖」を、特に父からはずっと注意されてきました。
しかし、それまでの私は父が細かすぎるんだとしか思っておらず、自分の非をちゃんと認めていませんでした。
そしてこの看板の出来事はまさにその自分の悪い癖から起こった出来事です。
私は自分がそれまでと全く同じことを繰り返していることに気づいたのです。
そして先輩の冷静な一言は、そんな自分深く突き刺さりました。
その時行うべきことを一心に行うのが修行生活であるはずなのに、自分は一体なにをやっているのだろうと、自分の短所である癖を深く反省し、それまで両親からされてきた注意をようやく飲み込むことができたのです。

仏教が薬と言われる理由
「良薬口に苦し」ということわざがあるように、本当に自分に必要な言葉や教えというものは、時にはなかなかに飲み込むことができないものです。
恐らくあの時、先輩が怒鳴ったり厳しく叱責をしていれば、私は「ツイてなかった」で終わっていたはずです。
なんなら、最初に壊した人を恨んでいたでしょう。
しかし「大人なんだから、ちゃんと責任は果たして。」という冷静な一言が、私を心から反省させてくれたのです。
実は、仏教の経典でその教えが薬と例えられる時は、その効能より薬を飲むということに焦点が当てられます。
どんなに素晴らしい薬があったとしても、患者がそれを飲もうとしなければ効果を発揮することがありません。
特に、心を健康にさせる薬である仏教は、恥やプライドを捨てなければその薬が患部に届くことはありません。
逆に言えば、ちゃんと飲まなければ仏教は薬にならないのです!
そこで僧侶がもつ役割は、相手に合わせてその薬を飲みやすくすることなのだと、私は考えています。
その薬にどんな効果があるかを勉強し、その薬を飲みやすくするために、法話をしたり、こうした文章を書くのだと思うのです。
そしてさらに、僧侶は自分自身が身を以って、その薬の効果を実感していなければ説得力がありません。
言うなれば、グルコサミンのCMでバリバリ農業をこなしているおじいさんと同じ役割です。
膝の痛みが消えてバリバリ働けるようになった!という体験があるから、その薬の効果は説得力をもつのです。
そういった意味では、僧侶の立場は自分自身がしっかりとその薬を服用し、病が癒えたという経験をもつ、元患者でもあるべきなのかもしれません。
これからの時代は、仏教はいい薬なんですよ!素晴らしいんですよ!という宣伝の方法だけではなく、飲み方を考えていくことが、今後はより必要になるような気がします。
仏教が薬に例えられるのは、苦しみを癒す効果と共に「飲む」ということの重要さ、難しさという側面が含まれているのかもしれませんね。

そして余談ですが、先ほど登場した5年目の先輩というのが実はこの人でした。
_190726_0050-min-300x200.jpg)
今こうして一緒に活動しているのが不思議でなりません。
8月2日にお誕生日を迎えられた亮道さん。
今後ともよろしくお願いします!