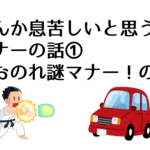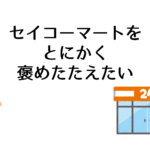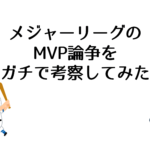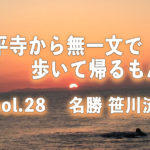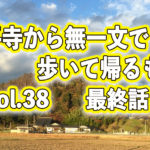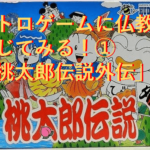スポンサードリンク
「ミーム」という言葉をご存知ですか?
ごく簡単に定義すると「コピーされて広がる文化伝達の遺伝子」(わかりづらい!)であり、
Wikipediaによれば日本語の訳は「模倣子、模伝子、意伝子」(ますますわからん!)となり、
習慣や技能、物語といった文化的な情報もミームにあたるそうです。
ただ、インターネット・ミームと言った場合は、文化とか物語とか高尚(?)なものではなく、インターネット上でコピーされ拡散される言葉・画像・言い回し・ネタなどを指す場合が多いようです。
インターネットが一般に普及し始めてから、およそ20年。
多くのミームが生み出され、流行り、廃れる中で、
ネット上の匿名掲示板や動画サイト、SNSなどから、新しい文化や流行が形成され、発信されるという光景も、もはや日常のものとなってしまいました。
ちなみに、インターネット・ミームの例としては……
「釣り」
「はい論破」
「大草原不可避」
などの言葉が挙げられます。
そういったインターネット・ミームを毎回一つ取り上げ、雑感を述べていこうと思います。
Contents
インターネットに「○○ンゴw」が生まれた日
第一回のテーマは「○○ンゴw」。
一見して、何の意味やら予測もつかないこの言葉。
今ではだいぶ廃れてしまって見かけることも少なくなりましたが、実はこの言葉は私にとって思い入れの深いミームなのです。
その理由は、インターネットの混沌の中に「○○ンゴw」が産声を上げるその瞬間を、まさに目撃したからに他なりません。
「○○ンゴw」の由来は、速球派でならした元東北楽天ゴールデンイーグルスのドミンゴ・グスマン投手です。
およそ10年前。当時私は、テレビで野球観戦をしながら、インターネットの匿名掲示板を閲覧することを楽しみにしていました。
2008年のシーズン序盤。件のドミンゴ投手が、あるゲームを締めくくる抑えのピッチャーとして起用されました。
しかし、ファンや首脳陣の期待とは裏腹に、バカスカ打たれまくるドミンゴ投手。

抑えのピッチャーは勝ちを確実なものとするためにチームが送り出す、いわば切り札的な存在です。
それだけに、抑えが打たれて負ける、というのは応援するファンにとって本当に悔しいもの。
しかもそれが、2試合も続いてしまいました。
連夜の抑え失敗劇に、「2試合連続して大事な場面で打たれるなんて、ドミンゴ何やってるんだよ(笑)」という意味で、
「ドミンゴw」
と、誰かが掲示板に書き込みました。
「○○ンゴw」誕生の瞬間です。
成長していく「○○ンゴw」
ミームの面白い点のひとつは、多くの人に使われるうちに意味が変わっていくところです。
いつしか、その言葉はドミンゴだけでなく、大事な場面で失敗してしまった様々な選手に対して用いられるようになります。
(例:久保田ンゴw、西田ンゴw)
そして語感の面白さも相まって掲示板に定着していきました。
さらに「またしても大事な場面で打たれて負けた(笑)」という意味で使われていた「○○ンゴw」は、シーズンが進むにつれ、
「ピッチャーが大事な場面で打たれた(笑)」
→「ピッチャーが打たれた(笑)」
と、少しずつその意味を変えながら使われていきました。
2008年のプロ野球シーズン。私はこの「○○ンゴw」の変遷を、わが子の成長を見守る親のように温かく見守っていました。
ひとつの言葉が生み出され、そして移ろいゆく……その姿が何とも愛おしく、それを見守ることの出来た自分が誇らしいと思う気持ちすらありました。
しかし、物事に流行り廃りはつきもの。(インターネットの世界では、そのスピードが特に早い気がします。)
私自身も匿名掲示板をあまり利用しなくなるに合わせて、いつしか、この「○○ンゴw」も見かけることが少なくなっていきました。
「○○ンゴw」との再会
時は流れ、私は「○○ンゴw」と思いもよらない形で再会を果たすこととなります。
それはつい一昨年のこと。
にわかには信じられませんでしたが、この「○○ンゴw」をツイッターなどで女子大生たちが使っていると言うのです!
その意味は、はじめのそれとはほとんど別物に置き換わっていました。
例えば、

のように、語尾につけることで「(笑)」のように使われていたのです。
そこにはドミンゴもいなければ、野球というスポーツもない。
それどころか、もはや用法すら原型をとどめていません。
インターネットの匿名掲示板は、かつて「トイレの落書き」のようなものだと言われていました。
「○○ンゴw」が生まれた当時、まさか女子大生が使うようになると想像できた人が、果たしてどれだけいることでしょうか。
大海に飛び出した鮭が、生まれた川に再び帰ってくるように……
10年の歳月を乗り越え、しぶとくネットの海を生き残り、思いもよらぬ形で私の前に帰ってきた、「○○ンゴw」。
そこには何とも言えない感慨がありました。
形を変えながらも伝わっていく言葉
さて、この「○○ンゴw」のように、私たちの身の回りには本来のそれとは異なった意味で使われている言葉が数多くあります。
普段、私たちが特に意識することなく使う、そうした言葉。
言葉の乱れが嘆かれて久しい現代ですが、移り変わり、まったく違う形で浸透していくというのもまた当然のことかもしれません。
禅語の中にも、今も使われながら、本来の使われ方と全く異なるものがあります。
その代表が「挨拶」です。

挨拶とはもともと、師匠が弟子の力量をはかるための問答を指す「一挨一拶」という言葉でした。
片や、相手の懐に飛び込み、核心を鋭くえぐる問いを投げかければ。
片や、質問を全身で受け止め、渾身の力で切り返す。
命を懸けるほどの、問答の応酬。
それが本来の「挨拶」です。
現代で一般に交わされる挨拶からは想像もつかない姿。
一方、現代の挨拶にも、互いを尊び、重んじ、思いを寄せるその精神性は生き残っています。
必然、移り変わっていく中で、必要とされるものは残され、不必要なものは失われてゆくのかもしれません。
まあ、「○○ンゴw」の場合、残すべきものは、何もないかもしれませんが……