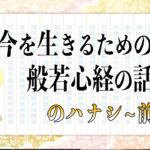スポンサードリンク
突然ですが、読者の皆様は数の単位をどこまでご存知でしょうか?
小学生の頃、何かの拍子に始まる数字合戦。
「おれ1億〜!」
「おれ1兆〜!」
「じゃあおれ1000億兆〜!」
こんなやりとりは、算数の授業で教わる「無量大数」によって終止符が打たれるその時まで続いたものです。
さて、そんな日本の数の数え方にはインドの哲学が大きく影響していることはご存知でしょうか?
「0」という数字はインドで生まれたというのは有名な話で、そこには仏教の教えも関係しています。
今回は仏教の経典に登場する、想像もつかない数の世界を少しご紹介します。
Contents
数字編:恒河沙
まずは有名なところからいきましょう。
こちらの『妙法蓮華経』「提婆達多品」の一節をご覧ください。
廣爲衆生説於妙法。恒河沙衆生得阿羅漢果。
ざっくり言えば、「広く衆生のために教えを説くと、恒河沙の衆生が阿羅漢という悟りの位に至った」という意味のこの一節。
ここにでてくる恒河沙というのは、10の52乗、1に0が52個付く数のことです。
恒河といのはインドを流れるガンジス川のことで、沙というのは砂。
つまり、この恒河沙というのは長さ2525km、流域面積1,080,000 km²川を誇るガンジス川の砂ほどの数なのです。
おそらく私たちは一生使うことのない数ですが、経典には頻繁に登場するあたり、やっぱりすげえと思わされます。

時間編①:劫
続いては時間の長さ編です。
こちらの「開経偈」という、今でも説法の前などにお唱えする短いお経の一節。
無上甚深微妙法 百千万劫難遭遇
「この上なく深くありがたい教えには、百千万劫あっても出遭うことは難しい」という意味なのですが、この百千万劫という言葉。
そもそも百千万というのが謎ですが、それはさておき、「劫」という時間の長さを表した例えがあります。
あるところに寿命が尽きない天女がいます。
その天女が百年に一回地上に降りてきて、一辺6kmほどある立方体の岩を羽衣でひと撫でします。
この摩擦によって岩がなくなっても、まだ1劫には至らない。
もうツッコミどころが満載ですが、古代のインドの数学者たちが計算したものでは、1劫はおよそ43億年だそうです。
こんな常軌を逸した時間の概念は、経典などでは「果てしない長さ」を表す単位として用いられるようになりました。
上に出てくる百千万劫というのは、仏教に出会えた奇跡、その嬉しさを、果てしない時間を使って表現していたわけです。
そして、日本でもこの劫は「非常に長い時間」を意味する言葉として定着しており、面倒で仕方がないことを「億劫」と言います。
つまり、これは43億年の一億倍の時間やる気になれないということなんですね。
「リモコン取りの行くのが億劫」って、どれだけ面倒なんでしょう(笑)

時間編②:刹那
先ほどの劫が長い時間を表したのに対し、経典には非常に短い時間の単位も登場します。
いはんや刹那刹那に生滅してさらにとどまらず
これは経典とは少し異なりますが、曹洞宗の道元禅師が著した『正法眼蔵』「出家功徳」の巻の一節。
刹那というのは、「一瞬」という意味で日本語としても定着していますが、実はインドではその長さをきちんと整理しています。
指をパチンと鳴らすこの時間の長さを「1弾指」といい、このパチンと鳴る間に65刹那あるそうです。
つまり、指がパチンとなる65分の1の時間が刹那ということになります。
ちなみに、一瞬の「瞬」もインドでできた時間の長さの単位だそうで、20瞬で1弾指だとか…。
もうなんのこっちゃ(笑)

仏教と時間の関係
いかがでしたか?
はるか昔から、数や時間をこんなに細かく考えてきたインドの哲学には、本当に驚きの連続ですよね。
これ以外にも世界の捉え方などもすげえ…ってなることがたくさんあります。
実はこれには仏教の考え方が大きく関係しています。
仏教では、0から1を創り出した創造神をおかず、全てのものものは縁によって起こるとしてきました。
宇宙の誕生から私たち一人一人に至るまで、あらゆる存在は原因(因)と条件(縁)の組み合わせに生まれると考えた仏教。
ということは、原因と条件が組み合わさるその前の、何もない状態があるはず、という考えから生まれたのが「0」という数です。
インドの言葉ではこれをシューニャといい、漢字では空と訳される概念がこうして考え出されたのです。
そして、0から1が生まれるならば、そこから先には限りがなく、時間の長短も同様に果てしなく存在すると、古人は考えたのでしょう。
経典を読んでいるとピンと来ない時もありますが、古代のインドの人々は今でいう「ヤバさ」「半端なさ」を数で表現しようとしたのかもしれませんね!!