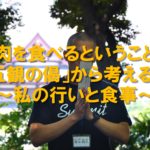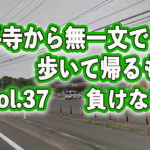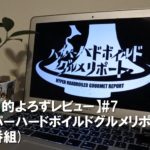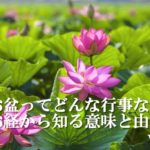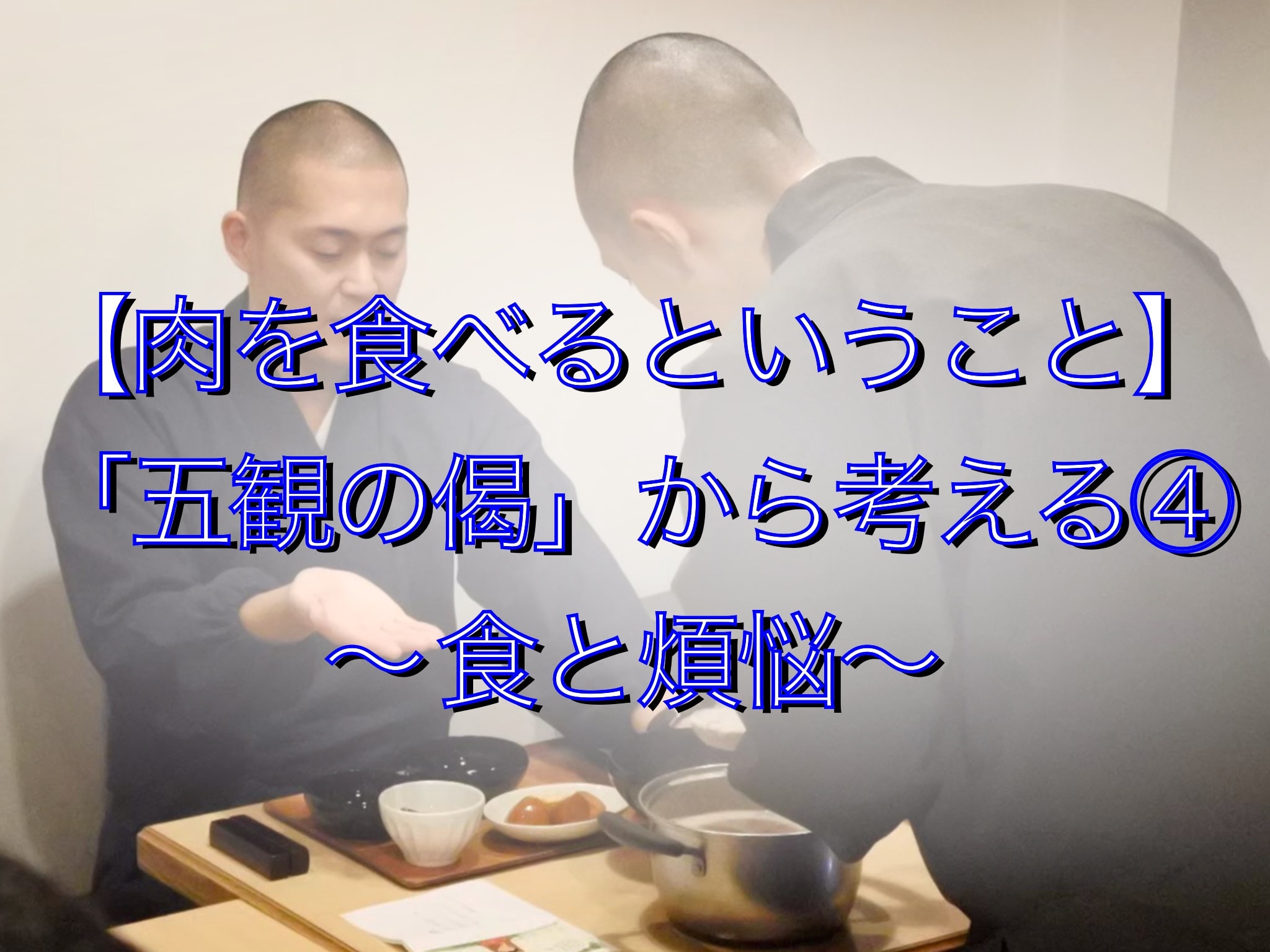
スポンサードリンク
曹洞宗僧侶の視点から肉食を考えてきたこちらの企画。
今シリーズでは食事の際のお唱えごとの一つ「五観の偈」を読みながら、改めて肉食や食べることそのものを考えています。
前回の記事はこちら
そして、今回は第3の視点
「三つには心を防ぎ過を離るることは、貪等を宗とす」
について考えます。
実は、5つの文の中で最も我々を悩ませるこの一文。
少し複雑になりますが、何卒お付き合いください。
Contents
食事と欲
ここまで、「一つには〜」で食事、「二つには〜」で己の在り方を見つめてきました。
そしてここからは、実際に食事をどのようにいただくか、ということが主題になっていきます。
まずは前半部分からみていきましょう。
心を防ぎ
ここでいう「心」というのは、講談社学術文庫『典座教訓・赴粥飯法』の語注によれば、「妄心」を指すとのこと。
妄心というのは、煩悩心とも言い、間違いを起こす心のことです。
そして「防ぎ」というのは現代とそこまで意味は変わらず、「起こらないようにし」といったところでしょう。
つまりは「心を防ぎ」は
妄心が起こらないようにし
という意味になります。
過を離るることは
続いて、過というのは、読み慣れないですが「過ち」という風に読むことを考えると想像しやすいですね。
間違いや失敗、罪のことをいいます。
つまりここは単純に
過ちを離れるということは
という意味になります。
心と過の前後関係
この、「心」と「過」の関係について、江戸時代に活躍された曹洞宗の面山瑞方禅師は『受食五観訓蒙』の中で「心」が原因となって「過」が起こると指摘されています。
つまり「心を防ぎ過を離るる」とは、「妄心を防ぐこと+過を離れること」ではなく、
「妄心が起こらないようにする=過ちを離れる」という構造になっているようです。
ということでこの部分をまとめると、
「妄心が起こらないようにして過ちを離れるということは」
という風に訳すことができます。

貪等を宗とす
続いて後半の部分に「貪等を宗とす」とはどういうことかが説かれます。
貪等を
ここで登場するのが、貪という言葉。
これは以前アラジンの記事やYoutubeでも触れた、根本煩悩と呼ばれる三毒の一つです。
そこで触れたように、煩悩というのは一つ一つが単独で起こるのではなく
自分の思い通りにしようと貪り(貪)
→思い通りにならなくて怒り(瞋)
→我を見失って過ちを犯す(癡)
という三毒の連鎖がループして起こります。
この瞋と癡が「等」という字には含まれていて、「貪等を」というのは「貪瞋癡の三毒を」と言い換えることができます。
宗とす
続いて「宗」というのは、現在では「曹洞宗」のように宗派を表す時に用いることが多いですが、元々は物事の根本を意味する言葉として用いられていました。
家の大元を「宗家」と言うのはそのためですね。
転じて、この字は宗教などの教えの根本、趣旨を意味します。
そこでこの部分の訳をまとめると、
貪瞋癡の三毒を根本とする
となります。

ややこしさの理由
ということで、「三つには〜」の訳をまとめると
三つには、妄心が起こらないようにして過ちを離れることは、貪瞋癡の三毒をその根本とする
ということになるわけですが、「貪等を宗とす」の部分がどこか釈然としません。
実はこれが、曹洞宗の食の教えを学ぶ人の頭を悩ませてきた部分なんです。
ここに関して、先ほどの面山禅師は「宗というのは[真っ先に]という意味がある」と述べられるのですが、多くの曹洞宗僧侶がお世話になっている「つらつらwiki」を運営する菅原研州先生によれば、その訳はどうも怪しいとのこと。
また、臨済宗妙心寺派などでは
「心を防ぎ過貪等を離るることを宗とす」
と読むそうで、こちらの方が「過ちや三毒を離れることを根本とする」という訳になるので、意味はわかりやすいですね。
この点については「実は読み間違いなんじゃないのか説」などもあったりして、はっきりとした結論は出ていないんです。
そこで、ここでは私なりの受け止め方を考えてみたいと思います。

修行としての食事
私個人としては、「過を離るることは貪等を宗とす」と読むからには、「過貪等を離るることを宗とす」と同じ意味としてしまうのはもったいないような気がします。
それは面山禅師が指摘された「心」を原因として「過」が生まれるということと、貪瞋癡のメカニズムのリンクに大きな意味があるように感じるからです。
心によって過が起こるように、貪から瞋と癡が起こる。
この構造を、講談社学術文庫版ではこの部分を次にように訳しています。
常日ごろ、迷いに心が起きないように、また過ちを起こさないように心掛けるが、
その際に貪りの心、怒りの心、道理をわきまえぬ心の三つを根本として考える。
食事の場においても同様である。『典座教訓・赴粥飯法』(講談社学術文庫)より
こちらの訳では三毒に振り回されないように心がける日ごろの仏道修行を、食事の中でも実践します、という意味で捉えています。
以前、食事作法の記事や動画でも取り上げたように、食事は生物としての本能に直結するため、坐禅や作務と比べてひときわ煩悩に囚われやすい行いです。
また、煩悩は一度抑えたら二度と出ないものではなく、次々に湧いてくるもの。
そこで重要なのは、生きている限り煩悩は生じるのだから、その度に抑えていこうと心に誓うことなのです。
これを食事の前に確認し、心に留めながらいただこう、ということがこの一節の趣意なのではないでしょうか。
そうした点から、私はこの一節を次のように受け止めたいと思います。
三つには、食事の中で妄心が起こるのを防いで過ちを離れるのは、
貪を抑えて瞋と癡を離れることを根本とする。
学術的な正確さには欠けてしまうかもしれませんが、食事における煩悩のコントロールの話として捉えてみました。

まとめ
今回は、この一文の訳や捉え方、さらには読み方に関しても諸説ある一番の難所をご紹介しました。
この一文で言わんとしているのは、欲を満たすための食事ではないのだから、心して食べましょうね、ということなのではないかと、私は捉えています。
以上、やや結論としては曖昧になってしまいましたが、「三つには〜」の考察でした。
次回は「四つには〜」について考えます。

※「五観の偈」は曹洞宗だけではなく、他宗派でもお唱えするものですが、その内容や読み方はそれぞれ微妙に異なります。
他宗派や別バージョンのものを知りたい方は、菅原研州先生のブログをご覧ください。
私が研究のご指導をご指導をいただいている先生で、見識の幅が尋常ではない方です。
また、今回の記事に関して、同ブログのこちらの記事を参考にさせていただきました。