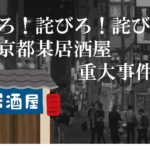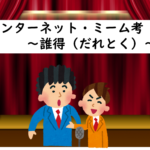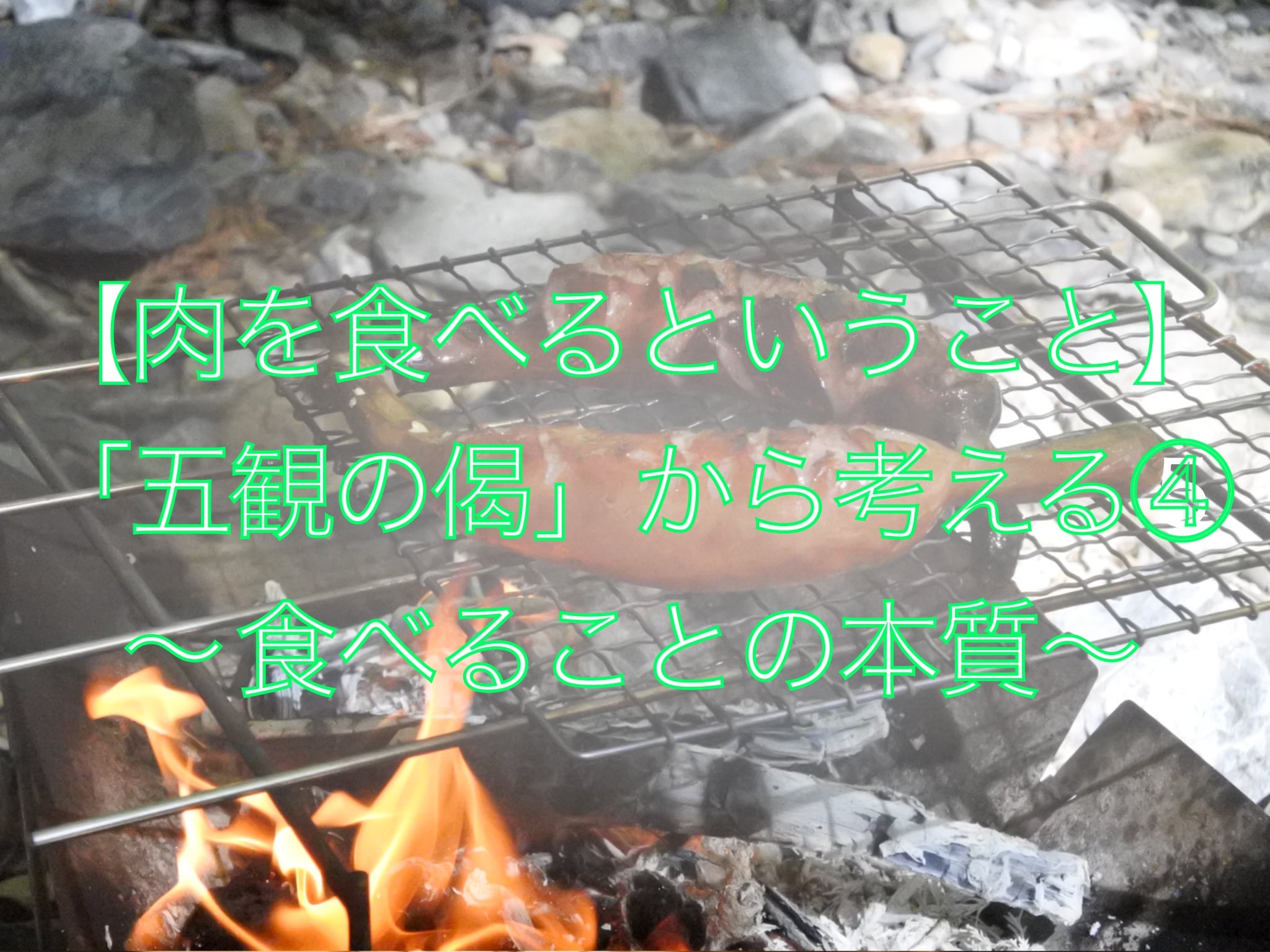
スポンサードリンク
曹洞宗の僧侶として、肉食や食肉加工に携わる方々への差別、そして「食べる」ということを考えるこちらの連載。
今シリーズでは、食前のお唱えとして有名な「五観の偈」から、曹洞宗としての食の在り方を考察しています。
前回は折り返し地点。
「三つには〜」を考察しました。
今回考察する一文はこちら。
四つは正に良薬を事とするは、形枯を療ぜんが為なり。
前回は私自身も頭を悩ませた一文でしたが、今回はシンプルな内容になります。
しかし、とても重要なポイントになっていきますので、じっくり考えてみましょう。
Contents
食べることの本質
ここまで私は、それぞれの一文を
「一つには〜」が目の前の食事の在り様を見る視点、
「二つには〜」は食事に向かう自分を省みる視点、
「三つには〜」は欲を満たすためのものではないという自戒の視点
という風に捉えてきました。
では今回の一文はどのようなものかというと、ずばり「食べるということの本質を見る視点」だと私は思います。
それでは実際に文をみていきましょう。
正に良薬を事とするは
まずは前半。
文章そのものはあまり難しくありません。
「正に」というのは「ちょうど今」「現に」といった意味で、もっと砕くと「こうして」という意味ととっても良いと思います。
「良薬を」は読んで字の如く、「良い薬として」という意味ですね。
「事とするは」は「それを仕事とする」という意味もありますが、ここでは「それを専らにするのは」という意味になります。
ということで前半部分をまとめると、
「こうして良薬とすることを専らにするのは」ということになりますが、少し読みやすくして
こうして(食事を)専ら良薬とするのは
という現代語訳になります。
形枯を療ぜんが為なり
続いて後半部分。
「形枯を」は、まず「形」は姿形、ここでは私たちの「身姿」のことを指します。
そして「枯」はそのまま「枯れる」という意味で、「形枯」とは身姿が枯れてしまうこと、要するに「痩せ衰え死んでしまうこと」です。
そして「療ぜんが為なり」というのはそのままで「治療するためだ」といったところです。
ということで後半部分は、
痩せ衰え死んでしまうのを治療するためだ
という訳になります。

食べなかったら、人は死ぬ
ここまでの訳をつなぎ合わせると、この一文はこんな意味としてとれます。
四つには、こうして食事を専ら良薬としていただくのは、
身体が痩せ衰え死んでしまうのを治療するためである。
そう、言っていることはごく当たり前のことなんです。
「食べないと死んでしまうから、食べる」という、ただそれだけのことです。
私たち人間は、老若男女国籍を問わず、「食べなければ死ぬ」という不治の病を抱えて生まれます。
その病を食い止める方法は唯一「食べる」ということです。
しかも、ただ食べればいい、食べれば食べるほど良いというわけではありません。
栄養や量、薬で言うところの用法用量を守らなければならないのです。
そんなこと今更言われなくてもわかっている、と思われるかもしれません。
しかし、私たちは本当にそれをわかっているでしょうか?

「食べる理由」と「食べる物」
現代では、食事というものは単なる栄養摂取に止まらない様々な役割を果たしています。
例えば、人と一緒に食べること。
不思議なことに、人はどれだけ距離を隔てても歴史を遡っても、人生の節目や出会い・別れの場では食事を共にするという行為が広く行われてきました。
なぜなら、生きることに直結する食事を共にする、あるいはそれを振舞うということは、同時にその人が生きることを認めるということを意味するからです。
親しくなって「ご飯でもいきましょう」というのは、そうした潜在意識があるからこその人間の習性ともいえるでしょう。
人と一緒に食べることは、一緒に生きていこうという意思確認の役割を果たしているのです。
他にも、SNSに投稿することで生活ぶりを認めてもらえたり、食のこだわりや知識によって他人から認められるといったように、食はステータスとしての役割も果たすようになりました。
それが悪いこととは言いません。
「食べなければ死んでしまう」という条件を持つ生物の中で、人間だけが唯一「食べ方」を考えることができる生物です。
それは同時に「生き方」を考えるということでもあります。
だから何を、どれだけ、どう食べるかは人生で非常に重要なことで、心の栄養とも言えるでしょう。
ただし、そこにばかり意識が向かうと、食べるということの本質を見失ってしまうことがあるのです。

本質の上に考える
以前、当連載の「曹洞宗の立場から考える〜 食べ物といのち 後編」で、曹洞宗の立場からすれば肉も野菜も全てがいのちで、そもそも「食べていい物」なんてない、ということをお話しました。
私たちはいのちをいただかなければ死んでしまうという、逃げようのない性質の上に生きています。
どれだけ理屈をこねても変えられないその性質がある以上、私たちはその現実を受け止めて生きなければなりません。
そしてそこに伴う責任が、「良薬を事としていく」ことなのです。
健康であるための良薬として食事をいただく。
そのためには欲をかいて食べすぎたりしてはいけないので、自然と「三つには〜」とも関連してきます。
いただくいのちは生きていくための薬にしていくのであって、身体を壊す毒にしていけない、ということが「四つには〜」の一節で説かれていると、私は捉えています。

まとめ
食に関する様々な主義主張や価値観が存在する現代。
根っことしては「死なないため」に食べているはずなのに、時には自分の主義主張を通す材料になって他者を責めたり、争いの火種になることもあります。
そんな現代にこそ、「私たちは食べなきゃ死んじゃうから食べる」という食の大前提を見直すことが重要なのではないでしょうか。
こうして五観のうちの四つめの視点として、食べるということの本質を踏まえることで、次の一文がより生きてくるのです。
次回は、「五つには〜」について考察していきます。
続く