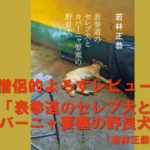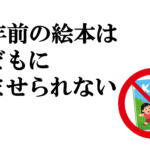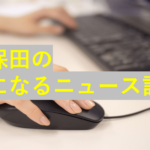スポンサードリンク
自分が観た・聞いた・読んだものを僧侶の視点からレビューする【僧侶的よろずレビュー】。
前回はお笑いコンビ、オードリーの若林正恭さんの著書「表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬」をご紹介しました。
若林さんの繊細で、細かな心境の描写に心を打たれた一冊でした。
そして今回ご紹介するものも、そんな繊細な部分を笑いに変える天才の著書になります。
私には、敬愛する3組のラジオパーソナリティがいます。
それは、オードリー、アルコ&ピース、そして伊集院光さんです。
その中でも今回は私が一番リスナー歴の長い伊集院光さんが、解剖学者である養老孟司先生と対談した「世間とズレちゃうのはしょうがない」をご紹介します。
Contents
作品紹介
今回ご紹介する「世間とズレちゃうのはしょうがない」は、タレントの伊集院光さんと解剖学者で東京大学名誉教授である養老孟司先生との対談が収められた一冊。
高校中退後、落語家・三遊亭楽大として芸の道に入り、素性を隠してラジオパーソナリティ「伊集院光」として人気を博し、現在ではラジオのみならずテレビでもご活躍する伊集院光さん。
そして、東京大学医学部を卒業し、解剖学者であると共にベストセラーとなった「バカの壁」(新潮社)など、数々の著書はがある養老孟司先生。
学歴や立場で考えればかけ離れたお二人ですが、共通していることがあります。
それは世間と自分の間に「ズレ」を感じてきたということ。
世間との間に感じた「ズレ」とどう向き合ってきたか、どう受け止めてきたかについて、様々な角度や姿勢の違いが窺える対談となっています。
異なる「ズレ」との向き合い方
この本のテーマである「ズレ」というものは、一言で表されていながら非常に多くの意味と影響力を持ったものだと、私は考えます。
私の体験で言えば、みんなが美味しそうに飲むビールが私は苦手で、絞った後のカットレモンの果肉を美味しく食べられる、といったように味覚のズレのような些細なものもあります。(これも人や状況によって死活問題になりますが)
一方で、価値観や考え方のように、世間とズレると非常に不便さや不自由さを感じるものもあります。
伊集院さんは、ご自身の大きな身体が、幼い頃に感じた最初の「ズレ」だったそうです。
身体の大きさ故に、喜びも恐怖も経験し、それをコンプレックス兼長所することで、世間との折り合いをつけた伊集院さん。
一方、ご親戚から
「おまえみたいな愛想の悪い人間は会社に合わない」(原文ママ)
と言われ、そのまま納得して研究の道へと進んだ、いわば世間とズレたまま生きることを選んだ養老先生。
世間との「ズレ」に対してとった立場は違えど、お二人は世間とズレることを人としての「欠陥」とは捉えていません。
もちろん、ズレることで点数や成績など取れないものもありますし、損だってするでしょう。
でもズレているからこそ見えるもの、言えることがある、そんな風に捉えているお二人の姿勢が非常に印象的です。

レッテルとズレ
お二人の対談は他人とのズレや自然との乖離など、様々な話題に触れながら進みます。
養老先生いわく、人間は意味不明なものが嫌で、自分のわかるようにラベリングをするそうです。
確かに、海外などで初めて食べたものは「〜と似ているな」とか「日本で言う〜かな」というように、自分が知っている、食べたことのある物と照合して分類したり、ラベリングをします。
そこで分類やラベリングがうまくいけば、「ああ、これは安心して食べられる味だな」となるわけですが、例えようがなく、経験もない味には戸惑ってしまいます。
これは味覚に限らず、人間関係もそうでしょう。
それまでの人生で経験した出会いやコミュニケーションから、「この人はこういう人だな」「こういう人は自分と合わないな」などと分類とラベリングをして、その人との付き合い方を判断するわけです。
当然この分類とラベリングは、自分自身もされています。
そして社会の大多数からされた分類とラベリングに漏れること、これが世間との「ズレ」なのだと思います。
この分類とラベリングは「普通」や「一般的に」や「常識」という言葉に置き換えられ、多くの人がここからはみ出さないように気をつけながら日々を過ごしているのです。
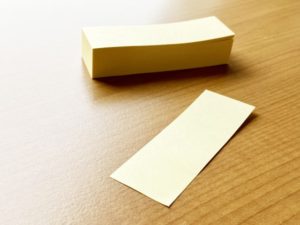
仏教と「ズレ」
この「ズレ」という言葉は、見る角度によって仏教の様々な言葉で言い表せます。
例えば、世間とズレてしまうことに悩んでいる時は、自分の思い通りにならないこと「苦」という言葉で表せます。
このズレは苦、つまり思い通りにならないものなんだ、とあっさり受け止めたのが養老先生、苦であることを武器にしたのが伊集院さんです。
逆に、自分からみて「あの人ズレてるな」という時には、物事を自分の視点からだけで見る「分別」をしてしまっていることになります。
このように、仏教が社会や人間関係を考える時、世間との「ズレ」は非常に重要なテーマであったともいえるでしょう。
そして私がこの本をすごいと思ったところは、それをご自身の言葉や非常にわかりやすい例を用いて表現されている点です。
それぞれに世間とのズレによる生き難さや疑問を感じ、それを見つめてきたお二人だからこその内容になっているように感じました。

まとめ
今回触れたのは、お二人の対談の中で私が気になった一部分です。
おそらく、この対談に全て共感できる方はいらっしゃらないでしょう。
ただ、「あ、確かに少しわかるかも」という内容があって親近感を覚えると、次の瞬間には「全然わからん!」と思わせるような揺さぶりが癖になる一冊です。
自分は共感できるだろうと思って読み始めましたが、実は私もお二人のおっしゃる世間の一部だと気づいて、少しショックでした(笑)
対談形式で章の区切りも細かくあるので、気軽に読めますので、ぜひ手にとってみてはいかがでしょう?
☆こんな方にオススメ☆
・人間関係や社会についてライトに考えてみたい。
・活字は苦手だけど読みやすい本を探している。