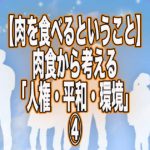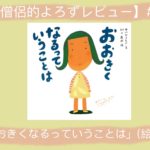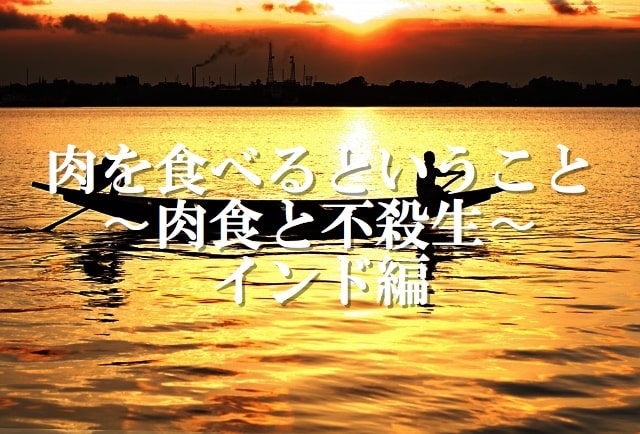
スポンサードリンク
仏教と食を考える上で、避けて通ることのできないテーマである肉食。
不殺生戒という仏教の戒が言葉として有名になり、いつしか「仏教は肉食を禁じられている」という情報は一般常識レベルにまで浸透しました。
実際に私達僧侶は肉を食べるのかどうかを聞かれることが多々あります。
単純な疑問として聞かれることもあれば、時には特定の思想を持った方から、意図を持って聞かれることもあります。
当コラムではここまで三回にわたって、食肉加工場の見学の様子、そして食肉加工を巡る差別の歴史に触れてきました。
そして、私は実際に食肉加工の現場で、仏教の不殺生という言葉が、その仕事に携わる方々に罪悪感を抱かせてきたという事実と歴史を知りました。
仏教徒は本当に肉を食べてはいけないのか、いけないとしたら何故なのか。
ここからはインド・中国・日本のそれぞれの仏教と肉食について探っていきます。
今回はまず、原点であるインド仏教の肉食についてのお話です。

Contents
インド仏教〜托鉢〜
仏教はおよそ2500年前、現在のインドにあたる地域でお釈迦様によって説かれました。
お釈迦様は元々シャカ族という小国を治める王族の王子として生まれましたが、自身に迫る老・病・死という恐ろしい現実を克服する為に出家をします。
出家と言うと日本では僧侶になることがイメージされやすいですが、当時のインドではすでにバラモン教をベースに様々な思想家や宗教が乱立しており、出家という言葉は家を出て修行者となることを指しました。
そして当時の出家者は托鉢によって食事を得て、一箇所には留まらない遊行が修行の基本スタイルでした。
それではこの托鉢という食事スタイルの中で、肉は食べられていたのでしょうか?
托鉢と肉食
托鉢というのは、在家信者から食物をもらうことをいいます。
当時のインドでは、在家者は出家者に食事を与えることで間接的に功徳を得る、という信仰と風習がすでに根付いていたのです。
また托鉢では、基本的にはその家の食事を分けてもらうことになります。
そこに用意されている食事は一般の家庭料理ですので、当然肉も入っています。
むしろ、肉であろうが野菜であろうが、美味しかろうが不味かろうが、極端な話傷んでいようが、与えられたものを食べるのが托鉢という食事の在り方でした。
石と排泄物は食べなくて良い、という程なので、ほとんどの物は食べたということですね。

インド仏教の肉食
それではここからはより具体的にインド仏教における肉食について見てみましょう。
『四分律』という、後に中国、日本へ色濃く影響を及ぼす修行僧の生活規則には、食べて良いものと悪いものが事細かに書かれています。
食べて良い肉、悪い肉
食べて良いものと悪い物は、お釈迦様が弟子の質問に答える形でが説かれます。
例えば、「病気にかかった者がいたら肉を食べても良いですか?」という問いに対して「いいでしょう。」という具合に、穀物・魚・野菜、その他には薬を口にすることが許されます。
その一方で、馬や蛇、犬など、一部の動物の肉は食べることが許されません。
ただし、理由を見てみると、当時のインドの社会にある風習に根ざしたものが多く、仏教というよりは社会とのバランスに配慮したものであるような印象です。
あるいは、食べることが禁じられた動物が持つ菌や毒などを踏まえていたのかもしれません。
三種の浄肉
また『四分律』では、「三種の浄肉」という、食べても良い肉の条件が説かれています。
その条件とは「故見・故聞・故疑」ではない肉のことです。
故見とは自分の為に殺されるところを見ていないこと、故聞とは自分の為に殺したと聞いていないこと、故疑とはその疑がないとことという意味です。
つまり「私の為に殺された動物の肉」を食べることが禁じられていたのです。
これは一つ間違えると、漁師さんや料理人さん、と畜解体に携わる方の仕事を否定することにつながり、仏教信仰を妨げる原因にもつながる為、受け取り方に気をつけるべきでしょう。
この三種の浄肉に関しては、人権問題なども含めてまた改めて取り上げたいと思います。

インド仏教と肉食の特徴
インド仏教においては、肉食自体は殺生として禁じられませんでしたが、人を含めた動物を殺すことは一切禁じられており、料理や狩猟はもちろん、虫を殺す可能性のある掃除なども禁じられました。
こうしたインド仏教の肉食の特徴には、出家者と在家者の立場がはっきりと分かれていた、当時のインドの社会構造が大きく関係しています。
お釈迦様がおられた当時のインドでは、修行するのは出家者だけに限定され、在家者との間にはっきりとした境界線がありました。
修行者は供養をする在家者の功徳の為にも、特別な存在である必要があったのです。
こうした明確な立場の線引きがあったからこそ、言ってしまえば「自らの手を汚していない肉は食べて良い」とも取れる三種の浄肉という考え方が生まれたのかもしれません。
そしてお釈迦様の死後、インドで仏教は衰退していき、徐々に肉食を禁じる他宗教が興隆していきます。
この社会の変化に合わせて、仏教もまた肉食を避ける方向にシフトしていくのです。
食肉加工業の立ち位置
またインドでは、カーストという職業や生まれによって定められた社会階級があります。
一番上にいるのがバラモン、今で言えば司祭のような、独自の言語や儀式によって宗教を司る人々でした。
王族より上の階級であったことを考えると、当時の宗教がどれだけ力をもっていたかがわかります。
そこから下っていくといくつも細かい階級がありますが、そこに含まれないアウトカーストと呼ばれる階級がありました。
この階級の人々はいわゆる被差別階級で、触れることはおろか、時には見ることさえ避けられていました。
そこに位置付けられる「不浄」とされる職業が、掃除や死人の処理、そして食肉加工だったのです。
ヒンドゥー今日が主流になると、神聖とされる牛の肉を食べることが避けられるようになります。
ただし、食肉加工をする人々を除いて。
ヒンドゥー社会では「不浄」であるとされる、食肉加工業の人々には死んだ牛の解体と肉を食べることを許しました。
しかし、その牛を食べることが、彼らを「不浄」とするさらなる根拠にされてしまったのです。
その差別は暗黙のうちに現在もネパールなどの一部地域で残っています。
そこで食肉加工をする人々は牛肉を食べることをやめるようになったそうです。
日本にも通ずる、「不浄」を根拠とした職業・身分差別がインドには存在したのでした。
まとめ
インド仏教は、六道輪廻をはじめとする、バラモン教の教えが根付いた風土の上に成立しています。
お釈迦様が説かれた言葉の中だけでは知ることのできない、当時の風土や風習というものが混ざり合ったことで、インド仏教独自の特徴が生まれていったのです。
以上が、今回ご紹介するインド仏教の肉食の特徴です。
今回のインド仏教における肉食に関しては、
・托鉢という民間に根付いた信仰の習慣があったこと
・肉を食べること自体が禁じられていたわけではなかったこと
・食肉加工業が差別される社会背景があったこと
の三点を抑えていただき、次回、中国編に進みたいと思います。
つづく