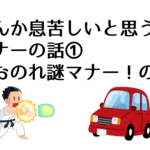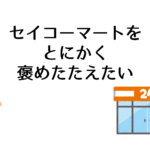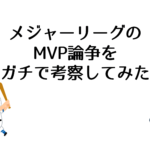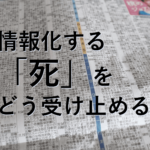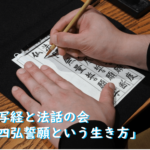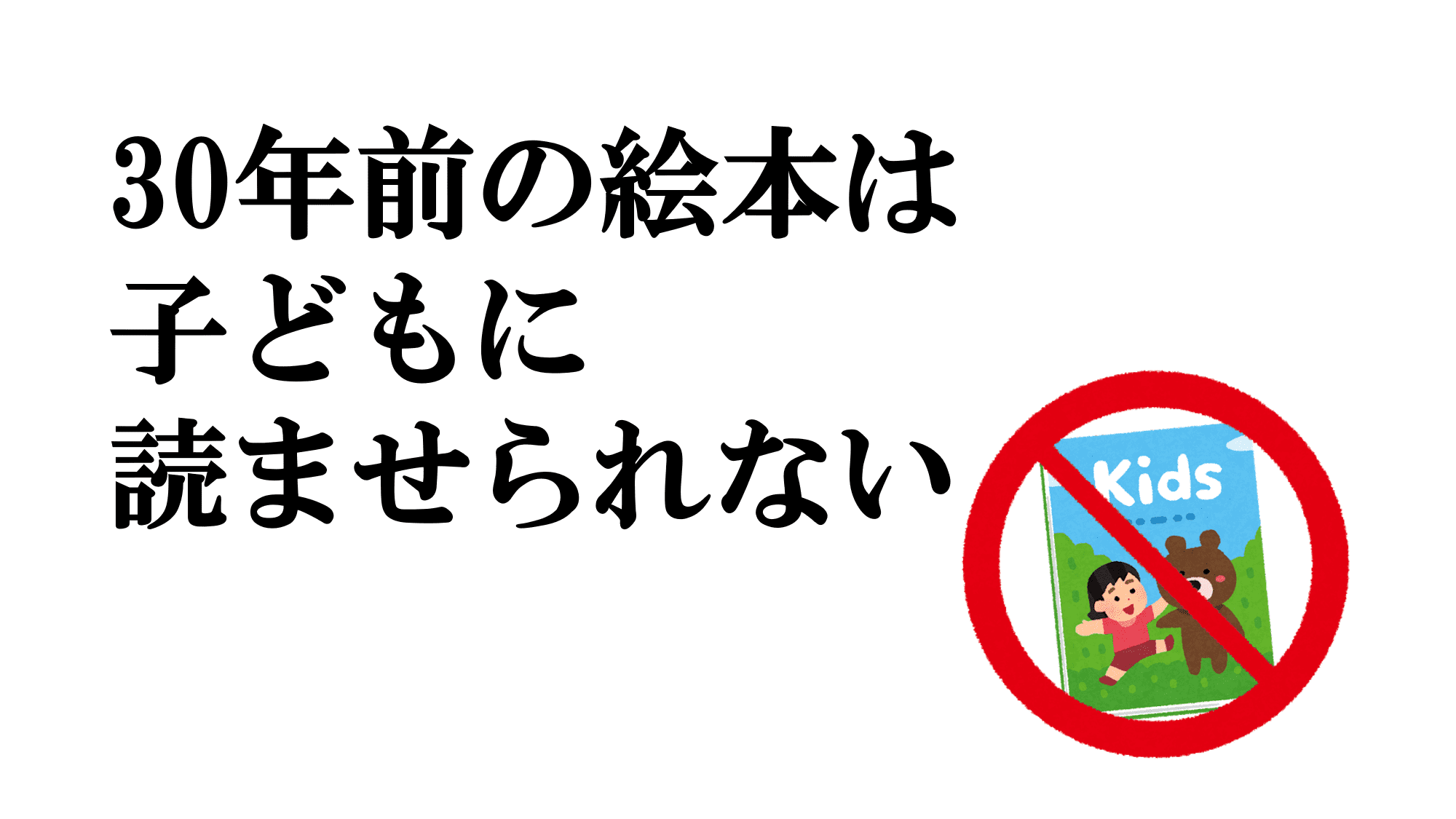
スポンサードリンク
桃太郎、金太郎、力太郎。
はなさかじいさん、かちかち山、さるかに合戦。
幼い頃、多くの人が慣れ親しんだ絵本。
冒険に心躍らせ、子どもの夢を膨らませてくれた愛すべき物語たち。
先日、実家の本棚に並べてあった絵本を眺め、
「親子で同じ絵本を読んで成長するってのもいいなあ」
と思い、ページをめくっていきました。
幼い頃繰り返し読んで、ところどころ痛みもある絵本に懐かしさを感じながら……
「うん。これは子どもに読ませられないな!」
と思いました。
なんということでしょう。
35年の時を経て、
かつて私が慣れ親しんだ物語は、現代の世相にそぐわない不適切書籍へと変貌していたのです。
今回は、古い絵本における「問題」表現を取り上げて考えていきます。
Contents
①人命軽視、残酷、暴力、復讐
古い絵本を読んで一番最初に目に付いたのが、これです。
「割とえげつない暴力」がさらりと描写されているケースが目立ちます。
たとえば、
・シンドバッドの冒険→一生肩車してもらいながら生活しようとする謎のおじいさんを、酒で酔わせて岩に叩きつけて殺す
・アリババと40人の盗賊→アリババの兄がバラバラにされて殺される。盗賊の親分は心臓を一突きにされて殺される。盗賊の子分たちは煮えたぎった油で殺される。
などです。
日本の物語で言えば、
・カチカチ山→おばあさんは撲殺される、狸は復讐されて死ぬ(ともに生存verあり)
・さるかに合戦→カニのお母さんは殺される、サルは復讐されて死ぬ(ともに生存verあり)
・三枚のお札→和尚さんが山姥をモチにくるんで食べちゃう
など。
そのほかにも、
宝島では当たり前のように登場人物が「ころせ!」と口走っていたり、
幼児向けとは思えないほど、血なまぐさい描写が使われていました。

②立身出世、結婚END多すぎ
次にあげたいのが、こちら。
立身出世、結婚END多すぎ問題です。
原作準拠ということも当然あるでしょうが、特に日本の昔話をモチーフにした絵本は、
「活躍が評価されて仕官に成功or財宝を手に入れて金持ちになる」
「良家のお嬢さんを嫁にもらうor婿入り」
といった「立身出世」や「結婚」で終わりがちです。


これの何が問題かというと、いわゆるステレオタイプを生むということです。
もちろん出世も結婚も、人が幸せを得るための一つのカタチと言えるでしょう。
しかし、これも当然のことですが、幸せの形はそれだけではありません。
仕官を断って実家に帰ってもいいし、結婚してなくても幸せになれるはずです。
出世END、結婚END自体が悪いというわけではありませんが、物語の結末がこればかりというのはどうにもアンバランスであるように思えました。
③差別・人権問題
そして、最も大きな問題がこれ。
差別や人権問題につながりかねない表現があることです。
たとえば、誰もが知っている昔ばなし「桃太郎」では、犬・サル・キジを「家来」にします。
これは当時の時代背景において、主従関係が明確にあったことを踏まえれば当たり前の描写かもしれません。
しかし現代の人間関係において雇用関係や師弟関係などはあっても、主・従という関係性はあってはならないものとされています。
あってはならない主従の関係性を求めれば、それはパワハラの一種とされることでしょう。

また、「一寸法師」は鬼を退治した法師が、打ち出の小づちで身体を大きくしてもらうことで姫様と結婚できるというストーリーです。
身体の小ささを活かして鬼を退治したのに、
結局、小さいままの法師は姫様と添い遂げることはできないのでしょうか?
考えすぎかもしれませんが、これは「小さい」=「足りない」ということになってしまいかねない描写だと思います。
どこまで脚色するべきか
古い絵本には、様々な問題があると思います。
一方で、「ちびくろサンボ」のように長く親しまれてきた物語を「不適切だから」という理由で闇に葬ってしまうのもあまりに短慮ではないでしょうか。
親と子が同じ物語を読んで育つということは、大きな意義があることだと思います。
そこで、必要になってくるのが問題のある表現の脚色です。
過激な描写は少し柔らかに。
むやみやたらと登場人物を殺す必要はありませんし、
復讐というストーリーも「恨みを晴らす」から「懲らしめなければならない」という義憤に置き換えることも可能だと思います。(それでも私刑という問題は残りますが)
ただ、物語をあまりに大きく変えてしまう脚色は、その物語が本来持ちえた教育上の意味を損なわせる可能性もあります。
その例として挙げたいのが「おばあさんが殺されないカチカチ山」です。
「おばあさんが殺されないカチカチ山」が失ったもの
カチカチ山のストーリーには、おばあさんが殺されないものも含めていくつかパターンがありますが、私が読んだカチカチ山はおおむねこのような内容でした。
狸を殺そうとしたおばあさんが逆に殺されてしまう
↓
ウサギが怒り、狸を痛めつける
↓
悪事を悔いた狸は、心を入れ替える

このストーリーについて、私は幼いながらに大きな疑問を感じていました。
「大切な人を殺された恨みを、痛めつけたくらいで果たして許せるものだろうか」
「おじいさんはなぜ狸を許してしまったのか」
物語上のこととはいえ、幼い私にはどうにも納得がいきませんでした。
しかし、歳を経るにつれ、おじいさんが狸を許したことに大きな意味があるように思えてきたのです。
現実の世の中では……悲しい話ですが、暴力や争いは絶えていません。
報復という行為も繰り返されているのが現状です。
しかし、当たり前の話ですが暴力に暴力で返すという行いを繰り返している限り、絶対に暴力はなくならないのです。
「おばあさんを殺した狸ですら、おじいさんは許した。」
これは私にとって、争いについて考える原体験となりました。
もし私が読んだカチカチ山が「おばあさんが殺されないカチカチ山」だったとしたら、私はここまで深く考えなかったでしょう。
「殴ったから殴り返されたんだよね。悪いことをしたら、報いを受けるんだね。」
というところで、考えは止まっていたと思います。
まとめ
私たちが生きる社会には、残念ながら未だ暴力も差別も存在しています。
そこで、子どもたちに読ませる物語に必要となるのは、
「悪いことは悪いこととして描く」ということだと思います。
悪いこと、不都合なことをことごとく物語の中から排除していったとしたら何が起きるでしょうか。
私は、物語に描かれる理想の世界とはほど遠い姿をしている現実の世界への絶望が残ってしまうと思います。
子どもが物語を読むことの意義が、
「物語を通じた学習によって現実の社会を生きる知恵を身に付ける」
ことだとしたら、物語の世界で暴力や差別を描かないことには大きな問題もあるのではないでしょうか。
時代とともに、物語もまた変化していくのは当然のことかもしれません。
しかし、願わくば、その変化の中で物語が伝える大切な部分が失われないことを望みます。