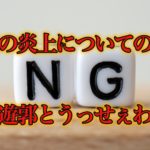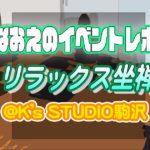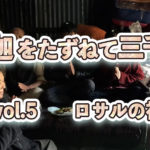スポンサードリンク
曹洞宗僧侶の立場から肉食を捉え直すこちらの連載。
前回から、肉食と人権について考えています。
肉を食べること、ひいては猟(漁)やと畜解体が仏教的な罪業と結びついたことが、
後の職業・身分・部落差別の大きな要因となっていたことは歴史からみても明らかです。
そこで今回は、改めて曹洞宗の視点から肉食に関する職業について見直し、人権問題について考えてみます。
Contents
動物性食品の生産は殺生?
まずはじめに、曹洞宗の立場から見たとき、猟(漁)や食肉加工といった動物性食品の生産が殺生なのか、という点について考えてみましょう。
ここで重要なのは
①殺生とは何か
②職業でも殺生となるのか
ということです。
実は①については過去に触れているのですが、それを応用するという意味でもう一度お話しします。
殺生とは何か
殺生とは、仏教的にも一般的にも生物の「いのち」を奪うことを意味します。
人はもちろん、動物や魚のいのちを奪うことは「殺生」であり悪行である、という認識も一般的でしょう。
ここで重要なのが、いのちの定義です。
仏教では、仏になれる存在をはじめは出家者に限定していましたが、そこから在家者も仏になれるとし、やがて動物も含まれるようになりました。
こうした、仏になる可能性を仏性といい、この仏性の有無が仏教にとってのいのちの有無の判断基準となっていると私は捉えています。
そして仏性を有するものの範囲は大きく広がり、宗派によって山川草木にも仏性がある、と言われるようになっていきます。
その中で曹洞宗の道元禅師は、やや異なる視点で仏性を捉えていました。
それは、仏性とは仏としての性質であり、今この世の全てのものが「仏のいのち」としてはたらいていると説かれたのです。
そうなると、仮に食べることや食物として生産すること、生きるための消費が殺生となるなら、
曹洞宗の信仰の上では猟や食肉加工はおろか、野菜や果物の収穫、木の伐採、建築、お香を焚くことですら全て殺生になってしまいます。
そこで重要になるのが不殺生という言葉の解釈です。
曹洞宗では出家をする時の受戒では『梵網経』に従って不殺生戒を含む16の戒を説かれ、授かります。
そして修行を経て、一人前の僧侶として師匠から教えを継ぐ際には道元禅師の『教授戒文』に従って戒の内容を改めて説かれます。
『梵網経』では、不殺生戒は比較的シンプルに殺生を戒める形で説かれるのに対し、
『教授戒文』では「仏祖の慧命を続ぐ」という説かれ方をします。
以前お話しした通り、「仏祖の慧命を続ぐ」とは仏のいのちとしてのはたらきを生かすということ。
これは生物としての生命活動が止まることではなく、縁起の上で形を変えながら続いていくということです。
この『梵網経』と『教授戒文』の間にあるものは修行、つまり仏教の実践です。
教えの実践を通して初めて納得のできる不殺生の在り方が、『教授戒文』では説かれています。
曹洞宗にとっては、生命を奪うことではなくはたらきを止めることが殺生であり、
自分自身の生き方によってそのはたらきを止めずにつなぐことが不殺生なのです。
職業でも殺生なのか
そこで改めて動物性食品に関する生産業が殺生であるか、ということを考えてみましょう。
これは結局のところ、その職業にどう携わっているかによって変わります。
曹洞宗の宗典である『修証義』の第四章「発願利生」には
治生産業固より布施に非ざること無し。
とあります。
「治生産業」というのは職業から生活に至るまでの全ての社会生活のことで、ここではその全てが布施にならないことはない、という意味です。
布施というのはお金のことではなく、「貪らない行い」のことです。
つまり、全ての社会生活が、自らの利益を貪らないことで布施という仏行になるわけです。
そして仏行である布施は、同時に不殺生の実践でもあります。
これらを合わせて考えると、欲や身勝手さに振り回されて行うならば、お花屋さんだろうとお医者さんだろうと殺生をしていることになります。
しかし、他の為を思って行われるならば、食肉の生産も猟も布施行であり不殺生の実践となりうるのです。
曹洞宗の教えと職業差別
ここまで曹洞宗の仏性、不殺生、布施の教えを元に動物性食品に関する生産業が殺生かということを考えてみました。
結局のところ、曹洞宗の教えの上では業種によって殺生とすることはなく、重要なのは携わる姿勢や経営の仕方であることがわかりました。
また、殺生となるような働き方や経営をしたからといって、差別をしていいということにはなりません。
差別とはそもそも坐禅から最も離れるレッテル貼りや決めつけである「分別」です。
そのため悪い「業種」はないけれど悪い「働き方」はある、というのがここでの一つの答えとします。
その上で、やはり職業やそれによる部落などの差別はあってはなりません。
しかし、曹洞宗には、故人の職業や出身を理由に差別戒名をつけてしまった歴史があり、これに対する反省と繰り返さないための学習が、宗派全体をあげての取り組みとなっています。
こうしたことが起こってしまったのは、今回ご紹介したような教えの上に社会を見るということができなかったということが原因の一つといえるでしょう。
逆に言えば、きちんと教えを学び、その視点から社会を見渡した時、曹洞宗には人権問題を大きく改善していく可能性があるということなのではないかと、私は考えています。