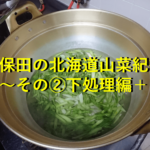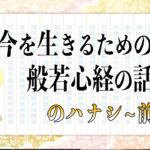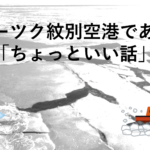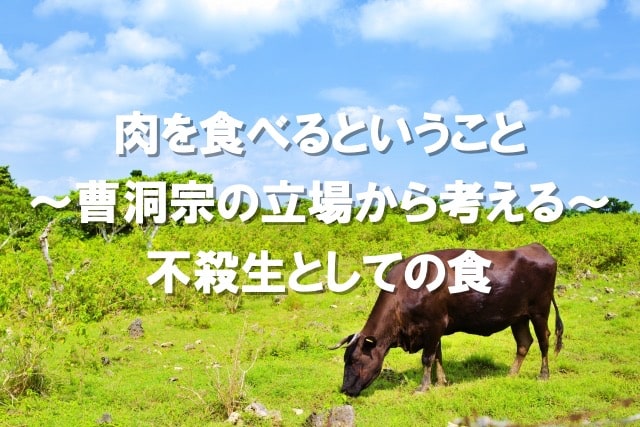
スポンサードリンク
食肉加工場の見学をきっかけに、肉食に関連した差別や対立について、僧侶の立場から考えるこちらの連載。
前回から、いよいよ曹洞宗としての不殺生の捉え方について書き始めました。
動植物はもちろん、鉱物や加工物に至るまで、この世界にあるもの全てを「仏の命」として捉える曹洞宗にとって、不殺生というのは「動物の命を奪わない」ことではなく、「あらゆる命を生かしきる」ことである、というのが前回お伝えした内容です。
それでは、具体的に「生かしきる」とはどういうことなのでしょうか。
今回は「仏の命を生かしきる」という不殺生の実際の在り方についてお話します。
Contents
曹洞宗にとっての「殺す」とは?
まず、「仏の命を生かしきる」ことを考える前に、曹洞宗の立場から「殺す」とはどういうことか改めてを考えなければなりません。
ここまでに触れたように、仏の命とは「はたらき」や「在り様」という言葉で表現することもできます。
例えば牛には歩き、草を食み、糞をして、夜には寝るという在り様。
それが加工され、食品となった牛肉には、タンパク質やビタミンとして人や肉食動物にとっての栄養源としての在り様。
樹木は土に根を張り、日光や水分によって二酸化炭素を取り込んで酸素を吐き出し、季節によっては花や果実をつけるという在り様。
それが切り倒されて加工されれば、屋根を支える柱や机、紙、燃えて灰になれば今度は灰としての在り様があります。
この、それぞれの在り様として存在しているのが、曹洞宗にとっての仏様の命という状態です。
つまり、この在り様やはたらきを無下にしたり止めてしまうこと、これが殺すということにあたるわけです。
ということは、食べるという行為も殺すことになってしまうのでしょうか?

「生かしきる」とは?
在り様やはたらきを止めてしまうことを「殺す」というのであれば、「生かしきる」というのは、そのはたらきや在り様を受け止め、無駄なく次の命へ引き継ぐこと、といえるでしょう。
「次の命へ引き継ぐ」というと、より抽象的になってしまうかと思いますが、曹洞宗の経典である『修証義』の第五章「行持報恩」にはこんな一節があります。
我らが行持によりて諸仏の行持
見成し
諸仏の大道通達するなり『修証義』「行持報恩」
行持というのは坐禅や食、排泄まで、仏教に基づいて行われる生活全てのことで、要するに修行生活のことです。
ここでは、私たちが実践をすることで、お釈迦様から私たちに至るまで、道を伝えてくださった全ての人々の行持がここに現れ、その偉大な道が繋がる、と説かれています。
つまり仏道は、経典をガラスケースに保管して残るのではなく、それを実践する人がいて初めて受け継がれ、実践する人がいなければ絶えてしまう、ということです。
一見、肉食や不殺生とは関係なさそうな一節ですが、ここには曹洞宗の非常に重要な精神性が込められています。
それは、「今、自分がどう生きるか」が問われているということ。
お釈迦様からの道は、私たちの生き方次第で繋ぐことにも絶やすことにもなります。
同様に、私たちの生き方が、口にした命を生かすか殺すかの分かれ目になるのです。
肉は一切食べず、菜食を貫いたとしても、自分や他者を傷つけて生きれば、食べた植物を殺生したことになります。
逆に、肉を食べたその栄養を、自分や他者を思いやって生きることに費やせば、それは肉となった動物の命を生かしきったことになります。
これは、菜食を批判し肉食を勧めているわけではありません。
食べるという行為は、食べ方とその後の生き方によって殺生にも不殺生にもなるのです。

食べ方と生き方。
そして、この不殺生を実践していくには、食べる人に限らず、生産者や調理する人の姿勢も重要になります。
生産者の不殺生
食物を生産する人は、動物にしろ植物にしろ、「仏の命を生かしきる」というつもりで作業に従事しなければなりません。
食肉加工場の職員さんは、牛や豚の肉や臓物、脂や皮を無駄にしないよう、衛生面や品質に細心の注意を払い、極めて丁寧に作業をされていました。
案内をしていただいた職員さんは「かわいそうとか申し訳ないという感情はない」と仰っていましたが、それはそのお仕事を全うすることこそが、牛や豚、そしてご自身の命を生かしきる道であることを無意識に悟っておられたのかもしれません。
もちろん農家さんや漁師さんも同様です。
ご自身の限りある命を、生産や漁に費やし、消費者に食物として届ける。
そこで欲に目が眩んで嘘や慢心があれば、たちまちその生命を殺すことになってしまいます。
生産者は生産する物と消費者に対して真摯に向き合うことで、その命を生かしきるのです。
調理人の不殺生
そうして運ばれてきた食物の命は、調理をする人に託されます。
特性や栄養を理解し、無駄なく美味しく調理をする。
下処理を丁寧にすることも、食材の命を生かしきる重要な手順です。
久保田さんが山菜の下処理の途中で、食べられない部分は土に返していましたが、食べるべきところを食べ、そうでない部分は自然の循環に戻すということも、調理人に求められる判断です。
また、生産者と同様に、自分の利益や名誉に目がくらんで嘘をついたり慢心することなく、食材と食事を口にする人に対して真摯に向き合うことで、その命は生かしきられていきます。
食べる人の不殺生
そうして、生産者と調理人によって食事という形に紡がれた命は、食べる人へと託されます。
この時に問われる食べ方こそが、禅活がワークショップでお伝えしている曹洞宗の食事作法なのです。
以前「家庭でできる!曹洞宗の3つの食事作法」に書いたように、曹洞宗の食事作法は食器を丁寧に扱うところから、口への運び方に至るまで、食事に対する姿勢が事細かに説かれます。
それは紛れもなく、食事に対しての敬意や真摯な姿勢をおろそかにし、命を殺してしまわないための作法だといえるでしょう。
そして食べた後は、僧侶であるなしに関係なく、自他を尊重して自己中心的にならずに生きていくことが必要になります。
この、生産から食べるに至るまでのプロセスと食べた後の生き方が仏教として正しいものであった時、食事は不殺生戒を積極的に実践した行いとなっていくのです。

命の在り様と問われる姿勢
どのように生産され、どのように調理され、どのように食べるか。
そしてその後どのように生きるか。
自分がどの過程に関わるとしても、命を無駄にせず、最善の形で扱っていく姿勢、これが曹洞宗の不殺生戒の実践であり「命を生かしきること」であると、私は考えています。
生産や調理には、必ずしも全員が携わるとは限りません。
そしてそこに携わる人が仏教徒であるとは限りませんし、そうでないことの方が多いでしょう。
しかし、食べるという行為は老若男女全ての人に共通します。
だからこそ、少なくとも食事をいただく私たちの、食べ方と生き方によってその命を「生かしきろう」とする姿勢が求められるのです。
何度も申し上げているように、そこには食品が動物性か植物性であるかは関係ありません。
曹洞宗の立場から考える不殺生は、「何を食べるのか」ではなく「どのように食べ、どのように生きるのか」という、その姿勢を問うものなのです。

次回以降について
これで、十分とは言えないながらも、曹洞宗の立場からの命の捉え方と不殺生の在り方について書き終えました。
そしてこれからは、より具体的に不殺生戒の実践としての食の在り方について書いていければと思っています。
次回からはまた新たなフェーズとして、皆様のお目にかかりたいと思いますので、ぜひお付き合いください。
肉を食べるということ〜曹洞宗の立場から考える〜完