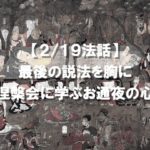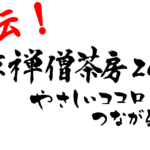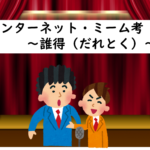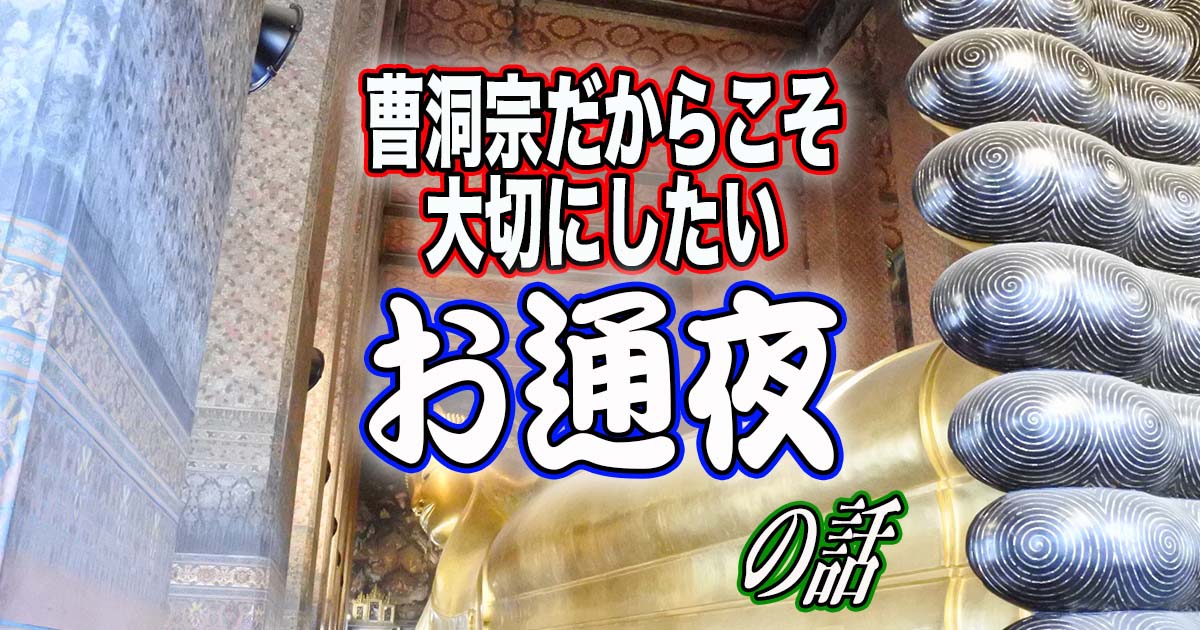
2月15日はお釈迦様に関する三つの行事、三仏忌の一つ涅槃会です。
涅槃会とはお釈迦様のご命日のことで、これが曹洞宗のお通夜に通じているというお話は、過去にした通りです。
今回は、コロナ禍で省略されるケースも増えてきたお通夜が、
実は曹洞宗だからこそ意義深くて、大切にしたいお勤めであるというお話です。
禅宗なのにお通夜を大切にするその理由について考えてみましょう。
Contents
お通夜と涅槃会
まずはお通夜について簡単に確認しておきましょう。
お通夜は、お釈迦様のご最期、涅槃に入られた時のご様子が由来となった法要です。
お釈迦様は周りを囲むお弟子様たちにご遺言を遺し、
「私の死にゆく姿が最後の説法だからよく見ておきなさい」と仰って最期を迎えられました。
その夜お弟子様たちは夜通しお釈迦様の遺され教えを確認し合い、お釈迦様亡き後の歩む道を定められたのです。
この「夜通し教えを確認し合った」ということが元となって、私たちはお通夜を営みます。
亡くなった方をお釈迦様として、ご遺族は遺された弟子たち、
そして僧侶はご遺言として故人に代わってお経を唱えます。
お通夜とはまさに、個人をお釈迦様に見立てた涅槃の再現なのです。

高野山金剛峯寺所蔵
曹洞宗とお通夜
では私が、曹洞宗こそお通夜を大切にすべきと思う理由はどこにあるかというと、
曹洞宗がどこまでもお釈迦様を大切にする宗派だからです。
これは他の宗派が大切にしていない、ということではありません。
曹洞宗の教えを伝えた道元禅師は、どこまでもお釈迦様を仰ぎ、敬い、慕った方でした。
お釈迦様が覚られた姿であるから、坐禅をすること自体がさとりであり、
修行とさとりは一つ「修証一等」なのだ、と説かれましたし、
食事作法や洗面にいたるまで、生活の一つ一つをお釈迦様のように行うことが、曹洞宗の修行です。
道元禅師はご自身をお釈迦様と重ねることを突き詰めていった方、と言ってもいいでしょう。
その徹底ぶりは、そのご最期からもうかがえます。
道元禅師の遺された『正法眼蔵』という87巻の書物の最終巻は、タイトルを「八大人覚」といいます。
これは、100巻を目指して執筆されていたものが体調が優れず、最期を悟って書かれた一巻です。
ではその最期の一巻でどんな言葉を遺されたのかというと、
実はほとんどがお釈迦様のご遺言のお経『仏垂般涅槃略説教誡経』の引用なのです。
八大人覚というのは、お釈迦様がご自身の死後、
お弟子様たちがしっかりと仏道を歩めるように遺された8つの心構えのことで、
道元禅師はこれを引用してご自身のご遺言とされました。
それまで、日本の歴史にも名を残すような教えや言葉を記してきた道元禅師が、
最期の最期でなぜ、ご自身の言葉を遺さなかったのでしょうか。
それは、ご自身の最期すらもお釈迦様と重ね、お釈迦様のように人生を締めくくろうという、
道元禅師の信仰の姿がそこにあったからなのです。

禅宗なのに?
曹洞宗は、臨済宗、黄檗宗と共に、坐禅を信仰の中心に置く、禅宗に分類されます。
そのため、坐禅をする宗派なんだからお通夜や葬儀、
供養をするのはおかしいという意見が内外から聞こえることもあります。
よく考えてみましょう。
曹洞宗が坐禅をするのは、お釈迦様のように在るためです。
そしてその信仰の先に、お釈迦様の最期にちなんだお通夜をお勤めする。
これほど意義深いことはあるでしょうか。
禅宗だから坐禅をしていればいいのではなく、
坐禅をするからこそお通夜に深い意義を見出すのだと、私は思います。

これから先の未来に
現在、コロナ禍において葬儀を一日にまとめたり、簡略にするケースも増えています。
それは葬儀の場で感染者を出したくないという、ご遺族や関係業者さんのお気持ちとしては当然のことだと思います。
ただ、一度安易に省略してしまったら、今後情勢が変わった時に、
「お通夜は省略してもいいものだ」となってしまわないでしょうか。
これはお通夜を省略していいか悪いかの話ではありません。
曹洞宗としてお葬式をするならば、今一度お通夜の意味を見直し、ご遺族が故人を仏様として
関係を結び直すためのその「心」だけでもお伝えるする必要があるのではないでしょうか。
曹洞宗の信仰の上にお葬式が営まれるならば、
ご遺族、葬儀社、そして我々僧侶も、お通夜の心を忘れずにいたいものです。
【関連記事】
【関連動画】