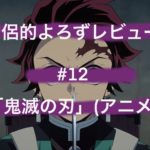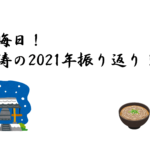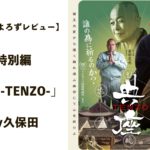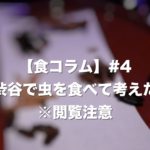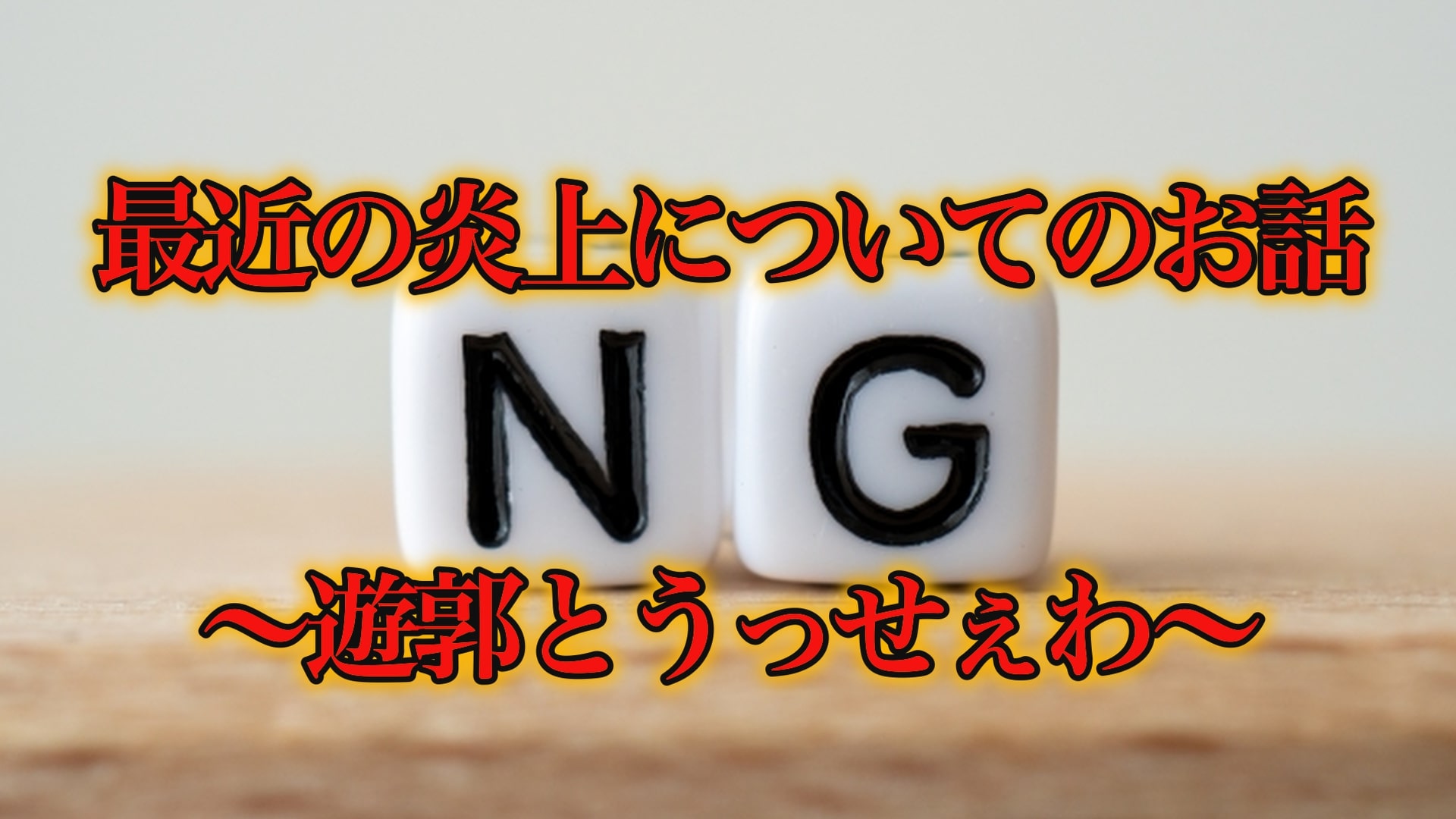
スポンサードリンク
今年で30歳になるワタクシ。
比較的新しいものも受け入れられるタイプだと思っていたのですが、ついにこれを言う日が来ました。
近頃の流行についていけない!
中学生の頃、当時大好きだったORANGERANGEを「うるさい音楽だな」という師匠に向けた軽蔑の眼差し。
それが自分に向く日もそう遠くはない、いや、すでに向けられているのかもしれません。
ただ、いくら流行についていけなくても、社会問題に対する感覚のアップデートは必要なことなので、一応話題は追うようにしています。
そこで今回気になったのが、保護者視点から起こった二つの炎上です。
今回は人気アニメ「鬼滅の刃」で遊郭を扱う問題と、流行の曲「うっせぇわ」に関するお話です。
Contents
アニメ鬼滅の刃「吉原炎上編」
以前記事でもご紹介しましたが、今や国民的人気を誇る漫画「鬼滅の刃」。
そのアニメは幅広い層から大人気で、劇場版が放映されるや歴代興行収入1位を記録するなど、日本のアニメ史に名を残す作品となりました。
そしてさらにアニメの続編の公開も決まり、さらに勢いをつけていく…
かと思いきや、思わぬブレーキがかかりました。
それは、続編が「遊郭編」であったということ。
先に申し上げておくと、これ原作通りの内容で、遊郭に潜む鬼との戦いを描くストーリーとなります。
しかしここで、一部の保護者から、「子どもが見るのに遊郭は不適切ではないか」という意見が出たのです。
遊郭とメディア
漫画やアニメで遊郭を扱うのは、なにも「鬼滅の刃」に始まったことではありません。
「ONEPIECE」だって今のシリーズでは遊郭の設定が登場します。
「銀魂」にも吉原炎上編というシリーズがありました。
また、ドラマにもなった「仁-JIN-」でも、かなり具体的に江戸時代の遊郭についての話があります。
(この「仁-JIN-」に関しては、私もかなり当時の問題について学ぶことができたので、ぜひ原作の漫画をお読みになることをお勧めします。)
他にも遊郭に関連して、当時の位の高い遊女・花魁は、今や服装の一つとして見られているのか、キッズ用の衣装や花魁風の振袖などもあります。
実は鬼滅を観ずとも、日本は遊郭や花魁に関係する情報が子ども入りやすい環境なのではないでしょうか。
鬼滅と教育
そしてこれは以前から指摘されていましたが、鬼滅の刃は映画版はPG12指定、「12歳以下には助言・指導」が必要となっている他、Amazon Prime Videoにおいても、暴力の描写が含まれると表記されています。
以前の記事にも書きましたが、鬼滅の刃はかなり血が飛び交う他、ショッキングなシーンが多数あります。
「北斗の拳」ですらアニメでは血を光で表現していたのに、鬼滅では真っ赤な血が吹き出します。
これが悪いというわけではなくて、なぜこの時点で問題にならなかったんだろう、と私は不思議に思いました。
そしてそれも踏まえて考えると、遊郭が問題になる理由は、大人側から上手く説明できないというというところにあるような気がします。
恐らく日本人のほとんどが、歴史上遊郭や花魁という人が存在したことは知っているでしょう。
しかし名前より先の、その実態や考えるべき女性の人権問題についてのことはほとんど知らないのかもしれません。
そしてよくは知らないけれど、性に関することだから教育にはよくないだろう、という「臭いものには蓋」的な状況が、今回の炎上の背景にはあるのではないでしょうか。
うっせぇわ/Ado
そしてもう一つの炎上案件が、高校生にしてメジャーデビューを果たしたAdoさんの「うっせぇわ」という曲です。
この曲のサビの「うっせぇ うっせぇ うっせぇわ」というフレーズが流行すると共に、子どもが真似したらよくないということで問題になっているとのこと。
この曲自体は、価値観や規則や正しさなど、様々な押しつけを振り払おうとする10代の力強い想いが込められたものです。
お子さんにはこのメッセージ性を理解するのは難しいでしょうから、サビの「うっせぇ うっせぇ うっせぇわ」が楽しくなってしまうのは無理もありません。
では、この「うっせぇ うっせぇ うっせぇわ」という言葉が、昨今のメディアにおいてそれほど乱暴な、教育に悪い言葉かというと、そうでもないような気がします。
バラエティ番組やYouTube、子ども向けのアニメですら、「うっせぇわ」くらいの言葉は出てくるでしょう。
しかし、なぜこの曲が槍玉に挙げられて教育に悪いものと言われてしまうのかと考えると、それは「音楽だから」なのかもしれません。
現代版ええじゃないか
言葉というのは、節回しや曲をつけることによって、使いやすく、響きやすくなるものです。
そして、この「うっせぇわ」というは、リズムと反復によって、保護者の言うことに対して子どもが使うには非常に勝手の良い反抗手段になり得るものです。
江戸時代末期「ええじゃないか」と呼ばれる大衆騒動がありました。
社会の潮流の変化を感じた民衆が「ええじゃないか」と連呼しながら踊り叫ぶこの騒動は、当時の権力者にとっても非常に厄介なものであったようです。
そして、保護者にとってこの「うっせぇわ」は、子どもたちによる「現代版ええじゃないか」になりうるという危機感が、ひょっとしたらあるのかもしれません。
教育によくないものとは何か?
インターネットやスマートフォンが普及した昨今、特定の情報だけを子どもの目に触れないようにする、というのはかなり難しいことのような気がします。
ご家庭で目に触れることがなくても、友達同士や外出先など、思いもよらぬところで情報というものは入っくるものです。
そうした現代においては「教育によくないもの」という認識を少し改める必要があるのかもしれません。
たとえば、歴史上に存在した遊郭という存在は、鬼滅の刃を観ずとも何らかのきっかけで子どもの目や耳に触れることがあるかもしれません。
保護者が閉めた臭いものの蓋も、子どもがいつの間にか開けてしまうかもしれないのです。
それならば、遊郭で言えば女性の人権など、触れること自体を悪とするのではなく、その問題の所在を把握し、説明できるだけの知識をつけておくことが、大人には必要なのかもしれません。
お釈迦様は、自らの教えを薬に喩え、それを飲むか飲まないかはその人次第とされました。
それと同じとは言いませんが、表現として作られた作品に関して、大人が子どもにすべきことは、それ自体を悪とするのではなく、適切な関わり方を導こうとすることなのではないでしょうか。
少なくとも、自分自身の不都合を理由に遠ざけては、大人側にも成長がありません。
「教育によくないもの」は「触れてはいけないもの」ではなく、「扱い方に気をつけなくてはいけないもの」という捉え方が、今後は必要になってくるのではないかと、私は思います。