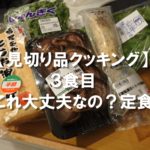スポンサードリンク
日本に数多く伝わる昔話。
その内容はファンタジー要素満載なものから、子供にはオブラートに包まなければ伝えられないようなスプラッター系のものまで、様々です。
そして、中には大人も唸ってしまうような深い教訓を示してくれるものもあります。
今回、私が気になったのは、超メジャーロングセールスミリオンヒットエピソードである「鶴の恩返し」。
私はこのお話、なんだか煮え切らない気分になるんです。
登場人物に誰一人悪人はいないのに、切ない終わり方をするこの話は、我々に何を伝えたかったのでしょうか。
「いや、メッセージとかないから」
と言われればそれまでですが、私はこの物語には仏教的な意味合いがあるのではないかと、考えてみました。
今回は「鶴の恩返し」を仏教的にこじつ…解釈してみました!
Contents
あらすじ
まずは、簡単に内容を整理してみましょう。
①あるところに決して裕福とは言えないおじいさんとおばあさんが暮らしていた(若い男一人暮らしパターンもある)。

②おじいさんが道端で罠にかかっている鶴を見つけ、助ける
③その夜若い娘が訪ねてきて泊めることになる。
④お礼に上等な反物を織ってくれる。
⑤反物が高く売れたのを喜んでいると、「絶対織っているところを覗くな」と言い、もう一仕事してくれる。
⑥次の日、また織ってくれるがおじいさん&おばあさんはつい覗いてしまう。
⑦娘の正体は助けた鶴だった!!
⑧「覗かないでって言ったのに!さよなら!」と鶴は飛び去った。
終了
いやはや。
やはりなんとも切ない終わり方ですね。
「したきり雀」などの強欲は身を滅ぼす系の教訓とも違いますし、「かさじぞう」のような善人は報われる系でもありません。
このエピソードの中にどんな教訓があるのでしょうか。
仏教と恩返し
今回、キーワードとなるのはやはり「恩返し」でしょう。
仏教でも両親からの恩であったり、教えを伝えてくださった祖師方への恩が説かれることがよくあります。
しかし、他宗派ではわかりませんが、曹洞宗に限って言えば「恩返し」や「恩を返す」という言葉が出てくることはありません。
変わりに出てくるのは「報恩」、「恩に報いる」という言葉です。
他者がもたらしてくれた恵みや助けである恩は、返すのではなく報いるものとして説かれるのです。
では、受けた恩恵に対して同等以上のお返しをする「恩返し」に対して、「恩に報いる」とはどのようなものなのでしょうか。
曹洞宗の経典である『修証義』の最終章、タイトルはズバリ「行持報恩」に、こんな一節があります。
唯当に日日の行持、其の報謝の正道なるべし
『修証義』第五章「行持報恩」第二十九節
行持というのは、起きてから寝るまでの仏道にかなった行い、修行生活のことです。
そして報謝の正道というのは、恩に報いる正しい道のこと。
つまり、「ただ日々の修行生活こそが、恩に報いる正しい道である」という意味になります。
では修行生活が恩に報いる正しい道とは、どういうことなのでしょう?

返すのではなく、報いる
私の知人に、永平寺での修行中にお父上であるお師匠様が体調を崩された方がいました。
修行中は離れた家族や友人が何よりも心配になるものです。
そこにお師匠様が体調を崩されたとあっては、いても立ってもいられなかったはずです。
すぐにでも修行をやめて看病をしたかったことでしょう。
しかし、その方は一度お見舞いに行ったその後二年、修行生活を続けたのです。
その時私は、そのことを自分に置き換え、私が僧侶になることを楽しみにしていた祖父がもし生きていたら、自分が体調を崩した時に帰ってくることを望んだだろうかと、考えてみました。
答えはNoです。
私を心から思ってくれる人ほど、修行に行っている私に望んだのは修行に打ち込むこと、精進することでした。
その方はお師匠様の恩に報いたいからこそ、より一層修行に励む道を選んだのです。
つまり、恩に報いるというのは、恩人に対して単純に同じことをして返すのではなく、恩人が最も望むであろうことを、生き方によって示していくことなのです。

鶴の恩返しの仏教的真実
そして、報恩という視点から「鶴の恩返し」を解釈すると、実は主人公は老夫婦ではなく、鶴であったことがわかります。
鶴は自分とは異なる世界を生きるおじいさんに救われ、恩返しをしたいと願うわけです。
そう考えると、おじいさんというのは仏様、あるいはもう言葉を交わすことができない恩人を意味するのではないでしょうか。
するとおじいさんと同じ立場であるおばあさんも、自動的に同様の存在となります。
そして鶴はどうにかおじいさんに恩を返す為、姿を変えて同じ言葉や服装を用いて接触し、自らの体を削って恩返しをしようとします。
そんな自分の身を削った恩返しを見られてはまずいと、老夫婦に機織りをする姿を覗かないようにいいますが、覗かれてしまいます。
それは、仏様や恩人である人々は、どんなに隠しても無理をしていることなどお見通しであるということを表しているのではないでしょうか。
そして何より、自分たちの世界にきて身を削って恩返しをすることなど、望んでいないのです。
鶴を助けた恩人であるおじいさんが望んだのは、鶴が鶴らしく、虫をついばんだり、空を飛ぶ姿を見ることであったはずなのです。
勘の良い方はお気づきでしょう。
この鶴とは、私たちのことです。
生死に関わらず、本当に私たちのことを想ってくれている恩人が望むことは、育ててくれた養育費や、奢ってくれた食事代、お正月にくれたお年玉を返すことではありません。
恩を受けながら歩む自分の人生を、自分の持ち場で目一杯生きることです。
私たちが恩を返せるようになった頃には、恩人はもうこの世にいないこともあるでしょう。
両親、先輩、上司、祖父母、友人…恩返しをしたいと思った時にはもういなかった方々に私たちができることは、生き方で示すということだけです。
鶴のように姿を変えて会いには行けない私たちだからこそ、今自分が修めるべき行い、これを修行として勤めていくことが大切です。
ちなみに、法事は三十三回忌までが追善供養といいますが、、五十回忌からは報恩供養と言います。
普段は自分の為すべき行いをして、ご命日などには手を合わせる、これも立派な報恩です。
もしかすると「鶴の恩返し」は、供養の心にも通ずる、私たちと仏様の間にある「恩」の在り方を教えてくれる話だったのかもしれません。
私はこうして、数えきれない恩に報いるべく、今日もパソコンに向かっています。
あくまでも個人的な見解ですが、おもしろいと思っていただければ幸いです。
それでは、
でん!でん!でんぐりがえってバイバイバイ!