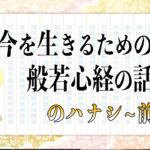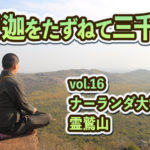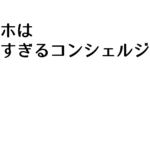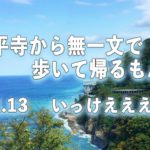スポンサードリンク
これは2016年に私、深澤亮道と愉快な仲間たちが、インド・ネパールにあるお釈迦様の聖地を巡った旅の記録である。
Contents
前回のあらすじ
前回は、お釈迦様がお悟りを開かれたブッダガヤ、マハーボディーテンプル(大菩提樹寺)を観光しました。
高さ52mの仏塔、そしてその裏に生えている菩提樹、世界各国から集まった仏教を信仰する人々。
その一つ一つの様相が、お釈迦様のお悟りを讃えている証であり、ここが仏教徒にとってどれだけ大切な場所かを表しています。
前回の記事はこちら↓
これまでの記事はこちら↓
以前にお釈迦様が出家をした動機やその時の様子なんかをお送りしましたが、今回はお釈迦様が出家をしてからお悟りを開かれるまでをお送りしたいと思います。
2人の師匠
29歳で、妻と子、家族と王子という地位を捨ててお城を飛び出たお釈迦様は、2人の師匠の元で修行を行います。
最初は「アーラーラ・カーラーマ師」、次は「ウッダカ・ラーマプッタ師」。
2人の師の教えに従い、坐禅・瞑想の修行を積みますが、お釈迦様は簡単に師匠の教えを理解してしまいます。
それは、極限の集中状態の中、「何もない状態」そして「無いものでもなく、有るでもない」境地に達してしまいました。
つまり、一言でいうと瞑想の達人です。
いや、ここまでいけば悟っているといっても過言ではないのか!?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
でも、この瞑想法はお釈迦様にとっては、ひとときの精神状態、ひとときの幸福状態であり、普遍的、根源的な老・病・死という苦しみから抜け出せるものではありませんでした。
苦行でも悟れない
瞑想で悟りきれなかった、お釈迦様は何を思ったか、苦行、つまり肉体を痛めつけるような修行方法を始めることになります。
これは皆さんがお坊さんの修行法と言えば想像する、滝に打たれたり、火の上を歩いたりといったものに近いかもしれません。
つまり、肉体を痛めつけ、我慢をしたり辛抱することによって目的に近づこうとする修行法のことを言います。
この苦行の方法は様々ありますが、裸で暮らす、草・牛糞・森の樹木や果実食べる、髪を抜く、立ったまま生活する、茨の道上で寝食を行う、断食などが一般的だったそうです。
当時のバラモン教では一般的に行われていたと言われますが、今でもインドに行けば「サドゥ」と呼ばれる修行者を見ることができます。

ここでお釈迦様は、激しく厳しい苦行を6年続けることになりますが、1番多く選んだ苦行の方法が「断食」です。
お釈迦様がお悟りを開かれた、菩提樹の元から車で約1時間ほどのところに前正覚山という山があります。

この写真の遠くに見える、フタコブラクダのような山です。
正しく覚る前の山と書きますが、お釈迦様はお悟りになる前にここの山の洞窟で断食を行っていたとされています。
洞窟の中には、骨と皮だけになるまでにガリガリに痩せたお釈迦様の苦行像が安置されていました。

どんな思いでここで苦行を行っていたのでしょうか。
この苦行像は、曹洞宗などの禅宗寺院では置いているところが多くあると思います。
しかし、お釈迦様は6年に及ぶ苦行でも、普遍的・根源的な苦しみから逃れることができない。
逆に悟るよりも先に衰弱死してしまうと、苦行は間違っている気づくわけです。
どんなに肉体を傷つけても、我慢しても解決することはできないと思い、ついに苦行を放棄します。
この苦行の放棄は、お釈迦様の失敗談ではありますが、苦行によっては悟ることがきないと明確に打ち出しているエピソードになります。
苦行を放棄したお釈迦様は前正覚山を下り、近くを流れていたネーランジャー川で沐浴をし体を清めた後、麓の村にいき托鉢を行います。
そして、この時に出会った村娘スジャータから乳粥を施され体力を回復されます。
今でもこの村は、スジャータ村と呼ばれており、仏教徒にとって大切な場所なので、多くの信者さんが訪れています。


余談ですが、乳製品やアイスクリームで有名な「スジャータ」という会社は、この故事にあやかっています!
余談の余談ですが、スジャータさんのお墓はめちゃめちゃでかいです。
村娘とは言いますが、結構なお金持ちの娘さんだったようです。

菩提樹の下でお悟りを開かれる
スジャータさんから乳粥の施しを受けたお釈迦様は、ブッダガヤにある樹の根元に座り、静かに坐禅を始めます。
太陽の強いインドで、再び体を傷つけることなく、風通しの良い肉体的に楽な場所に身を寄せて、ただ集中して自分と向き合う。
それは、これまでの修行で出会った、アーラーラ師やウッダカ師の瞑想法も思い出したでしょう、そして失敗に終わった苦行のことも考えたでしょう。
それらを総括して、お釈迦様が脱したかった普遍的・根源的な老・病・死という苦しみはなぜ起こってくるのか。
静かに静かに観察されました。
そうして静かに坐禅を行い、ついにお釈迦様はお悟りを開かれました。
このお悟りのことを「菩提」といい、お釈迦様が身を寄せて座っていた樹のことを「菩提樹」と呼ぶようになりました。
またブッダという名前も覚った人という意味です。
そして、皆さんが1番気になる点だと思うのですが、何を悟ったのか!?
うん、みんな気になると思いますが・・・・
実ははっきりとわかっていません!笑
ただその後に語った内容によると、この世の出来事は全て原因と結果の因果法則によって動いていくが、それは常に移ろいでいく。
しかし、自分の心も悩みも不安も幸せも不変なものはないけれども、人間は変わらないものを求めてしまう。
この変わらないものを求めてしまうから、苦しみがどんどん生まれてしまうという世の中の理を見つけたと言われています。
こうして、私は、生もなく、病もなく、老もなく、死もなく、愁いもなく、けがれもない、無上安穏の涅槃を求めて、ついにこれを得ることができた。
迷いの人生は尽きた。清浄なる修行はすでに確立した。もはや、ふたたび迷いの人生を受けることはない。
『中阿含経』羅摩経
梵天さんの要請
私たち曹洞宗に伝わる故事によると、お釈迦様は菩提樹下において坐禅に入られて1週間でお悟りを開かれた、とされていますが、仏典を見てみると菩提樹下で坐禅をして初めてお悟りを開かれて、そこから7日間の間、お悟りの楽しみを味わったとされています。
さらに、合計1ヶ月にも及びますが、7日間ずつ別々の樹の下で、お悟りの愉悦に浸っていたとされています。
そんなある時、空から梵天さんというインドの神々の中でも最も偉い神様が下りてきて、
「あなたがお悟りになった真理は、この世を救う教えになるので、どうか多くの人々にお説きください」
最初は「私の悟ったのは、あくまでも自分自身の苦しみを除くためであり、人を皆救えるわけではありません。」と断ったそうです。
しかし、梵天さんの再三に及ぶ要請にそれならばと立ち上がり、ついに人々に世の苦しみを除く理を説く決意をされました。
次回予告
お釈迦様はこの布教の決意をして、初めての説法の地「サールナート」に向かい5人の修行者たちに法を説くわけですね。
梵天さんの要請は、本当はいっぱい書きたいことがありましたが、何はともあれ梵天さんがお釈迦様に進めなければ、仏教は始まらなかったというエピソードとして、とても重要視されています!
はい、そして次回はまた場所を移動しまして、お釈迦様がよく説法をされてた霊鷲山やお釈迦様の仏教教団が修行を行ったとされる竹林精舎なんかをめぐりたいと思います!
「vol.15 お釈迦様は何を悟ったか?」をご覧いただきありがとうございました!