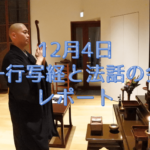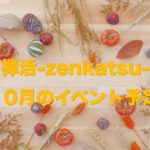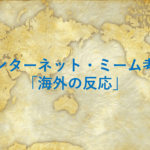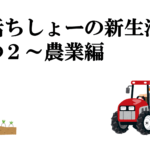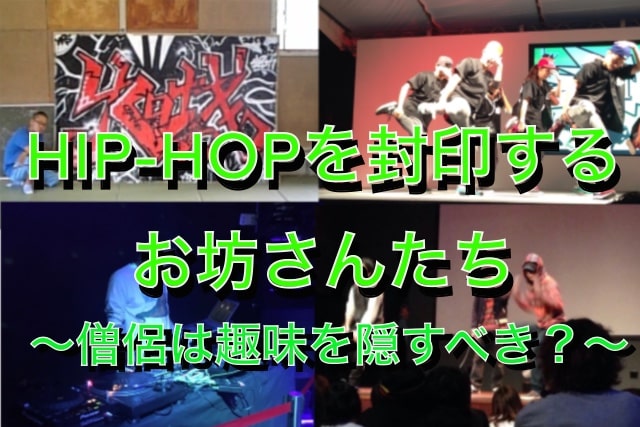
スポンサードリンク
カードゲーム、プラモデル、釣り、etc...。
突き詰めることはなくとも一時的に没頭した趣味が多数ある私。
そんな中でいまだに続いているものが、高校生の時に出会ったHIP-HOPカルチャーです。
実はHIP-HOPというのは、4つの要素を総称した名前です。
4つの要素というのは、ブレイクダンス、ラップ、グラフィティ、DJです。
ブレイクダンスは回ったり逆立ちしたりするあれで、グラフィティというのはバンクシーなどに代表されるストリートアートのこと。
私はとある映画をきっかけにブレイクダンスと出会い、そこからグラフィティやDJもかじり、ラップは今でもよく聴いています。
おっと、今回は別にHIP-HOPカルチャーを語る回ではありません。
実はHIP-HOPに限らず、お坊さんの中にはこうした青春を捧げたものがありながら、出家を機にやめる、あるいは隠すようになる方が非常に多いんです。
そこで今日は、僧侶は自分の趣味や親しんだ文化とどう向き合っていくべきかについて考えたいと思います。
Contents
実は多い、HIP-HOP僧侶
「類は友を呼ぶ」という言葉がありますが、HIP-HOPカルチャーが好きな私は、不思議と同じくHIP-HOPカルチャーを愛するお坊さんとご縁をいただくことがあります。
お彼岸の棚経のお手伝いに行っていたお寺の物静かな若さんが、実は東京でDJとしてイベント出演やCD制作をしていた過去を持っていたり、法話の勉強会では現在もラップをやっている方と出会いました。
そういえば、仏教学部があったこともあってか、私が大学時代に所属していたストリートダンスサークルだけでも、お寺の子が5、6人はいました。
このように、その気になればイベントができるくらい、HIP-HOPカルチャーが好きなお坊さんはたくさんいるんです。
ところが、多くの方はやめてしまったり僧侶としてはそれを公にしないなど、後ろめたさを感じているようなのです。
そしてその原因多くははどうやら、お檀家さんや世間からのイメージを気にしてのことのようです。

趣味とイメージの間で
かくいう私も、その気持ちはよく分かります。
私の師匠はダンスが「とにかくなんか嫌い」というタイプの人で、私が学生の頃は出先でもそれを嘆いていたそうです。
いまだに私が体を鍛えようとすると「ダンスはもうダメだからな」と釘を刺してくるくらいのなので、余程嫌だったのでしょう。
確かに、私も実際にその文化の中に身を置いてみて、仕草や成り立ち、曲の歌詞など、そこに僧侶としては肯定しきれない要素があることも確かです。
特に、HIP-HOPというカルチャーに含まれる、有名になってお金を稼ぎ成り上がることを目指すという要素は、仏教と反する部分ともいえるでしょう。
そうした、世間からのイメージや僧侶という生き方との折り合いのつかなさから、私は大学卒業を機に、一度HIP-HOPカルチャーに見切りをつけたのでした。

あの時間は無駄だったのか?
それから、永平寺での修行生活が始まると、まず始めに雑巾掛けが立ちはだかります。
私はこの時、ダンスでつけた体力にずいぶん助けられました。
まず褒められることなどない最初の一週間に、先輩から「お前めっちゃ拭けるな!」という独特な褒め言葉をいただきました。
それから、坐禅での背骨の使い方や体の支え方を理解するには、ダンスの基礎でもある倒立の感覚が役立ちました。
仏教書を読んでいると、聴いていたラップの歌詞がお釈迦様の教えと結びついて非常にわかりやすくなったこともあります。
このブログにも頻繁に登場するように、ラップの歌詞には僧侶でもハッとするような表現がありますし、バンクシーがグラフィティを通して表現したメッセージにはいつも感銘を受けています。
DJがその場の空気や雰囲気を掴んでいく技術だって、大いに参考にすべきです。
そんなことを考えているうちに、私は自分が親しんできたHIP-HOPカルチャーが、必ずしも僧侶という道と全く相反するもの、無駄なものとは思えなくなったのです。

過去を背負って、今を語る
お釈迦様のお弟子さんに、ソーナという方がいました。
ソーナは、日本でいう琴の名手で、出家後は非常にストイックに修行をされたそうです。
しかし、それでも自分から欲が湧き出てくるため、修行を諦めかけていました。
そこでお釈迦様とソーナの間で、こんな会話が買わされたそうです。
「あなたは琴が上手なようですが、弦を張り過ぎたら良い音は出ますか?」
「いいえ、出ません。」
「では弦が緩かったらどうですが?」
「それでも音は出ません。」
「そう、張り詰め過ぎても、緩め過ぎても琴から良い音が出ないように、修行も極端になってはいけないのです。」
ソーナはこの言葉によって、修行の在り方というものに気づくことができました。
このエピソードは「中道」という教えを説いたもので、お釈迦様の喩えの素晴らしさはもちろんのことですが、ソーナが琴をやっていたからこそ理解することができた、とも言えるでしょう。
仏教では、人の思考や価値観というものは、その人の経験や行動によって形成されていくと考えます。
ということは、今僧侶として生きる私も、決してそれ以前の人生と切り離されたものではないのです。
HIP-HOPカルチャーに親しんだからこそ見えるもの、浮かぶ考え、言葉があります。
そして、そんな私の言葉だからこそ仏教を届けられる人がいるのではないでしょうか。
当然、僧侶として避けるべきことに対しては線引きをしていかなければなりません。
そうして、自分が親しんだ文化や競技も仏教を理解したり伝える術となったとき、それに熱中していた時間すらも仏道になっていくのではないかと、私は考えています。
これはあくまでも私にとっての趣味や文化との向き合い方で、「きっぱり過去の趣味や特技とは分けるべきだ」という方もいらっしゃるかもしれませんし、それもいいと思います。
しかし、せっかく一度熱中したものを、僧侶になると同時に封印してしまうのではなく、僧侶だからこその関わり方を見つけるという道があっても良いのではないかと、そう思えてならないのです。