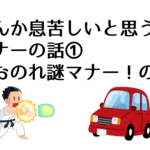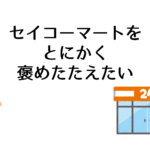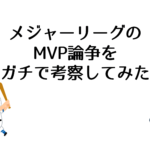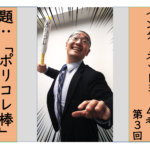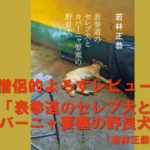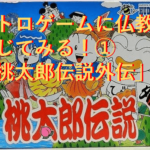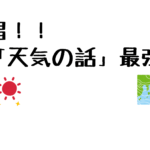スポンサードリンク
今回は時事ネタ!
今夜、ついに始まるアメリカ大統領選挙。(執筆時は11月3日)
大国アメリカの、そして世界の趨勢を占う上でも重要な選挙が始まろうとしています。
バイデン氏優勢と言われる中、アメリカの国民はどのような判断を下すのでしょうか。
政治について、あまり深入りして語るつもりはありませんが、
今回の記事は、選挙戦の報道を見ていて久保田がもっとも気になった点について書いていこうと思います。
Contents
選挙戦に見るアメリカのお国柄
アメリカの選挙戦報道を見ていて久保田がもっとも気になった点。
それは対立候補への遠慮のない攻撃です。
たとえば選挙前の事前討論で行われた、対立候補への「口撃」や、
支持者による、選挙運動の妨害行為。
これは現大統領のトランプ氏側によるものでしたが、
対立候補のバイデン氏の側も、相手を徹底的に批判し、自陣営の正当性をアピールし続けています。
そこに「いい戦いをしよう」などというスポーツマンシップのようなものは、微塵も感じられません。

自分の正当性を声高に叫び、相手を貶めるという行為は、いわばアメリカの「お国柄」のようなものかもしれません。
一昔前のTVのコマーシャルや、あるいはスポーツ選手へのインタビューでも、
ライバルを攻撃し、自社や自分への評価を高めるという表現手法が当たり前に通用しているという話を聞いたことがあります。
思えば、4年前、現職のトランプ大統領が当選した要因の一つには、
トランプ氏の「反ポリコレ」の姿勢が有権者に評価されたということもあるそうです。
自分の意見をオブラートに包むことなく、ストレートに表現するトランプ大統領。
時に差別的ともとれる表現すらいとわない大統領は、
人々の心に潜在的に存在する「言いにくいこと」をはっきり言う、
言わば一部の人々の代弁者のような立ち位置であったとも聞きます。
「あいつらが悪い!」
「あの国は最悪だ!」

常日頃から遠慮のない「口撃」を繰り返すトランプ大統領。
そこには確かに品性が欠けているように感じられます。
しかし、はっきりとモノを言うトランプ大統領が「民衆の代弁者」として支持を集めたとするなら、
アメリカ国民の多くが潜在的に持っている意識は、トランプ大統領の「問題発言」を支持するというものでもあるのではないでしょうか。
逆に言えば、抑圧された民衆感情の発露として、トランプ大統領が誕生したのかもしれません。
(※ちなみに私が思う抑圧された民衆感情とは、それぞれの心の中にある「偏った正義」です)
アメリカと「分断」
連日報道される選挙戦の様子を見ていて、
「アメリカの社会は、特に対立が引き起こされやすい構造をしているのではないか?」
という思いが沸き起こってきました。
政治のシステムは二大政党制で、人種のるつぼと呼ばれるほどの多民族国家であること。
貧富の差が激しい国であること。
さらに歴史を紐解けば農村部と都市部での内戦(南北戦争)や、本国との間での独立戦争を経験し、
資本主義陣営の旗頭となって世界各地の紛争に介入してきました。
特に、国際関係で言えば「世界の警察」として明確な立場を取り続けてきたのがアメリカです。
こうしたことを背景に、より強い正義、より強いリーダーシップを求め、
対立や競争を受け入れ、「二極化」の中で成長していくビジョンを正当化していったのがアメリカという国なのかもしれません。

一方で、対立や競争を肯定してきたツケは、アメリカの大きな問題となっているように思います。
人種差別を問題の根本に置く、BLM(Black Lives Matter)の問題。
環境問題や軍縮に関する消極的態度。
これらの問題はアメリカだけの問題ではありませんが、
大国であるアメリカの方針は、世界に大きな影響を与えます。
こうしたことに真摯に向き合えるリーダーが登場することを切に願うばかりです。
言うまでもなく世界は、正義と悪の2つにはっきりと分けられるような姿をしていません。
人種、思想、文化圏、気候、どこを切り取ってもそれぞれに個性を持った存在が共存しているのが、
この地球という世界です。
そしてアメリカはこれから世界が向かっていく方向を決定づけてしまうほどの強大な力を持つ大国です。
それだけの大国であるアメリカが持つ二極化という構造は、そうした問題を考える上での、大きな障害となるような気がしてならないのです。

妄想する莫れ
禅語「莫妄想」。
読み下せば「妄想する莫かれ」となります。
ここでいう妄想とは、自分勝手な空想や、根拠のない思い違いというだけに留まりません。
自分勝手な執着や思い込み、そして、
正義と悪・快と不快・勝ち負けなどという風に物事を2つに分けて考えてしまうことも含まれます。
私たちは、物事を整理して理解するため、つい2つに分けて考えるということをしてしまいがちです。
しかし、その考え方は果たして正しいものでしょうか。
古今東西、世界の様相は往々にして、たった2つに分けられるものの方が少なく、実際はずっと複雑です。
もちろん、何かを比較して考えるということは、有用ではあります。
ただ、その比較という考え方も、便宜的に2つに分けているに過ぎない、と一歩引いて見つめることが必要ではないでしょうか。
2つの区別のどちらかに絶対的な正しさがあると思い込んでしまったら、
決定的な対立や不必要な誤解が生まれ、また物事を正しく把握するということも難しくなることでしょう。

とはいえ実際には、私たちは社会生活を送る上で、何かを常に選ばなければなりません。
それは2者択一のみならず、もっと複雑な問題もあることでしょう。
さらに様々な選択を繰り返す中でしか、私たちは日常を送ることができないというのも一つの真実です。
その中にあっても、自分が選んだ選択肢に執着しないという態度が必要なのではないでしょうか。
自分が選択をするように、反対意見の人もまた同じように選択をしているに過ぎず、異なることは悪ではないのです。
世界のグローバル化、多様化が叫ばれる昨今、できるだけ多くを受け入れることのできる考え方こそが、
今求められていることなのだと思います。