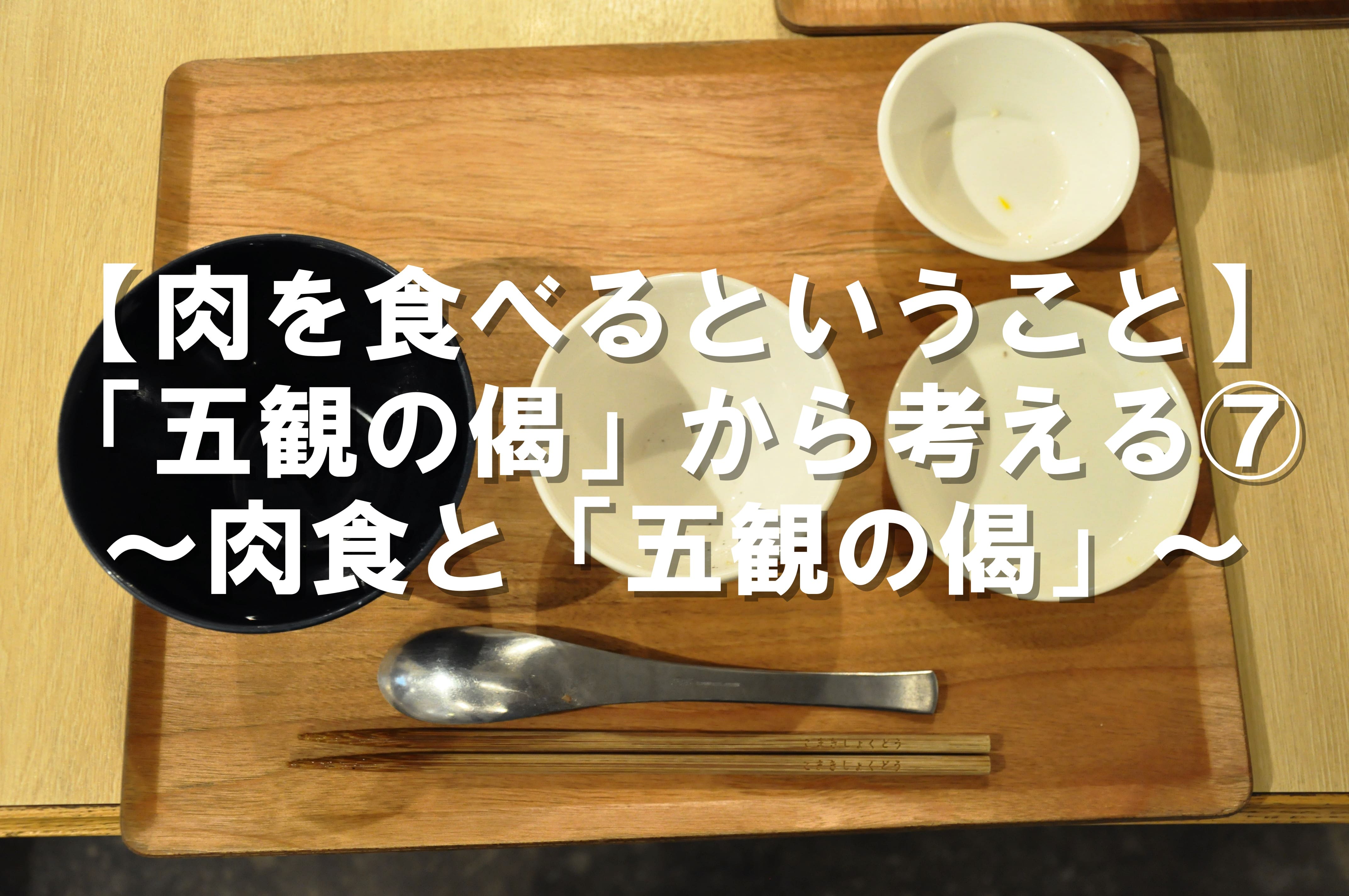
スポンサードリンク
曹洞宗の僧侶として、肉食や食肉加工に携わる方々への差別、そして「食べる」ということを考えるこちらの連載。
今シリーズでは、食前のお唱えとして有名な「五観の偈」から、曹洞宗としての食の在り方を考察しています。
前回は「五観の偈」の最後の一節、「五つには〜」を考察しました。
ここで、食べるということは仏道を成す為であり、仏道を成すことで食事が仏行となる、ということをお話ししました。
そして今回は、この連載の主題である肉食を、「五観の偈」に当てはめて考えていきたいと思います。
Contents
作られる肉と、食べる私
これまで書いてきたように、私は「五観の偈」は一と二で過去を振り返り、三と四で食事の何たるかを確認し、五でその後の生き方を誓うという構成になっていると考えます。
そこでまず、一と二から考えてみましょう。
一つには功の多少を計り、彼の来処を量る
この一節は、非常にわかりやすいようですが、現代の日本では容易なことではありません。
野菜でさえその生産過程に触れる機会は少なく、私たちは漠然と畑と農家さんに思いを馳せるくらいしかできない場合もあります。
それが肉となると、意図的にその生産過程が人目に触れないようにされてきた歴史があります。
元は狩猟や漁によって、生き物が肉に変わっていく様子を目にしてきた私たちの祖先でしたが、いつしか牛や馬、豚の屠畜は陰で行うようのになっていったのです。
それは、やがて身分差別へとつながり、現在も色濃く残っています。
しかし、曹洞宗の立場から考えれば、あらゆる存在が仏様のいのち、仏性です。
動物か植物か、哺乳類か魚類か、などは関係ありません。
この一節から考えれば、私たちは口にするものや使用するものの一切に対して、そのご縁にいただいて生きていくという責任を負っているのです。
二つには己が徳行の、全欠を忖って供に応ず
次に、そんな責任を負っていく私はどんな生き方をしているか?と自問するのがこの一節です。
それは、前の食事で「成道の為の故に今此の食を受く」と誓ったことに対する反省でもあります。
肉を食べようが野菜を食べようが、その栄養をしっかりと仏道に活かすことができたか、と振り返ることで、過ちに気づくことができたなら、それも一つの仏行となっていきます。
この、作られた食事と食べる私の両方を考えることで、食べたものがなんであれ、しっかりと仏道に活かされていくのではないでしょうか。

肉と煩悩と栄養
次に、三と四についても考えてみたいと思います。
三つには心を防ぎ過を離るることは、貪等を宗とす
ここでは、食事の中で煩悩に振り回されないように貪瞋癡の三毒と向き合うわけですが、肉は煩悩とも関連させられる場合があります。
たとえば、『正法眼蔵随聞記』の面山本というバージョンには、こんなお話があります。
昔、中国でとある修行僧が、「病気になったので薬(肉)を服用したい」と師匠に申し出た。
それを聞いた師匠は、病人が療養する部屋で服用することを許可した。
ところが師匠はその様子が気になり、部屋を見に行くと、肉は修行僧が食べているのようで実は頭の上の餓鬼が食べていた。
あくまでもこれは話の概要ですが、要するに薬として食べていた肉は、その修行僧の煩悩が食べていただけだった、というお話です。
実際に、牛肉や豚肉には必須アミノ酸や必須脂肪酸と呼ばれる成分が含まれ、それらの一部は脳内でトリプトファンやテストステロンなどの「幸福物質」と呼ばれるものに変換されます。
古くから人間が肉を「ごちそう」と認識したように、肉食にはこうした一種の快楽に近い要素があるのかもしれません。
そう考えると修行や坐禅には適していないのではないか、とも思えるのですが、ここで次の四に話を移しましょう。
四つは正に良薬を事とするは、形枯を療ぜんが為なり
食事とはあくまでもこの体が朽ちないための良薬です。
体に負荷をかけたり、不健康になるようでは、良薬とは呼べません。
実は、肉食禁止の色が濃かった日本仏教でも、「薬食い」として肉を口にすることがありました。
確かに「幸福物質」に依存し、食欲に囚われれしまってはいけませんが、必要な栄養を取らずに不健康になってしまっては、本末転倒です。
結局、この三と四を合わせて考えた時に導き出される答えは
バランスよく食べる
ということなのではないでしょうか。
極端に食べすぎても、極端に無くしてもいけないのです。
それは修行の本質とも通じているのかもしれませんね。

最終的に、生き方
そして最後にこの一節です。
五つには成道の為の故に、今此の食を受く
最終的に、ここで肉食をどう受け止めていくかが結論づけられていきます。
以前、不殺生とは自分の生き方によってそのいのちを生かしきることであるとお話ししました。
それは、そのままこの一節に通ずるものであるといえるでしょう。
何を食べるかではなく、どう食べるか。
そして食べてからどう生きるかが、牛や豚や鳥や魚のいのちを生かすか殺すかを決めるのです。
さらに言えば、たとえ何を食べようと一切のいのちを生かしきる生き方をしていこう、という強い意思が、この一節で説かれているのではないでしょうか。

まとめ
以上、非常に大まかになってしまいましたが、「五観の偈」から肉食を考えてみました。
勘の良い方はお気づきのことでしょう。
結局、普通の食事と変わらなくない?と。
そうなんです。
結局、曹洞宗の立場から考えれば、何を食べようと姿勢は変わらないんです。
野菜だろうと肉だろうと、その生産や調理の過程に知らない部分はあるし、ありがたく受け止めなければいけません。
また、どんな食べ物であろうと、そればかり食べようとすれば、それは煩悩だし、栄養が偏りすぎれば健康にも害が出ます。
そして、最終的に問われるのは、自身の食べ方と生き方なのです。
むしろ、そうした教えが全て含まれている「五観の偈」の奥深さを、私は今回ん執筆を通して改めて感じています。
この<「五観の偈」から考える>シリーズはこれで終了、また新たなテーマへと移っていきたいと思います。
まずはここまで前8回、お付き合いいただきありがとうございました。
【肉を食べるということ】「五観の偈」から考える 完

























