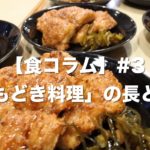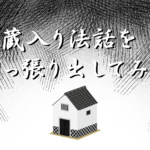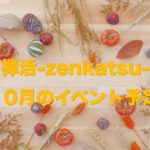スポンサードリンク
最近、動物系のYouTubeチャンネルをよく観る私。
動物といってもかわいいワンちゃん猫ちゃんが出てくるものではなく、珍しい爬虫類や昆虫や魚を飼育していたり、自然にいるものを捕まえて食べるという、ややワイルドめの動画に魅力を感じてしまいます。
思えばこの季節は、幼少期の私にとっては虫とりシーズンの到来でした。
お寺の境内ではトンボやバッタ、運がよければカブトムシ。
近所の川や田んぼに行けばザリガニ、トノサマガエル、カブトエビ、少しレアキャラになるとドジョウがとれたりしました。
魅力を感じる動画は、私のそんな思い出が刺激されているのかもしれません。
そんな中で、しばしば登場するのが外来種という言葉。
何かしらのきっかけで日本に持ち込まれた、本来日本にいない動植物のことです。
今回は、そんな外来種について考えてみたいと思います。
Contents
境内の桜の話
さて、まずは少し実家のお寺にある桜についてのお話をさせていただきます。
私が生まれたお寺の境内には、十数本の桜の木があり、春には綺麗な花を咲かせます。
平成元年のお寺の改築に合わせて植えられたものなので、樹齢は私の年齢とあまり変わりません。
田んぼに囲まれたお寺にこの桜が咲くと、遠目に見ても美しく、近所の方々もよく見に来られます。

そんな桜の木ですが、ここ数年花に元気がありません。
満開になっても花のつき方に隙間が多く、冬になる前にほとんどの葉が落ちてしまいます。
何か病気になってしまったのだろうかと、師匠が木を見てみると、あちこちに穴が空いていて、そこから出た木屑が積もっています。
これは、クビアカツヤカミキリというカミキリムシの幼虫が中に入りこんだ形跡で、これが桜の元気がなくなった原因でした。
クビアカツヤカミキリの幼虫は桜や桃などの木に卵を生むと、幼虫が螺旋状に幹を食べながら上に進んでいきます。
そのため観光や農業に大きな被害をもたらす危険があるため、2018年に特定外来種に指定、見つけ次第駆除するよう促されている、いわゆる害虫なのです。


(出典:群馬県HP)
外来種駆除への違和感
さて、このクビアカツヤカミキリですが、境内の桜が完全に枯れてしまうとなると困るので、植木屋さんの協力を仰ぎながら、見つけ次第駆除しています。
この外来種を駆除するという行為が、最近ある種エンタメ化しているような気がするのは私だけでしょうか?
「実はここにこんなに外来種がいて、在来種の存在を脅かしていたので全部捕獲して駆除し、平和を取り戻しました!」
というようなものです。
ここで確認したいのは、外来種と呼ばれる生物そのものは「悪」ではないということです。
そして、外来種の中にも、駆除されるものとされないものがある、ということをよく考える必要があります。
たとえば、トマトは江戸時代に観賞用の植物として持ち込まれた外来種です。
トマトだけではなく、キャベツや人参、アスパラなどもそうで、カレーに使う野菜のほとんどが外来のものです。
これらの外来の野菜や植物が駆除される対象ではないのは何故でしょうか?
それは人間にとって有用だから。
アメリカザリガニやウシガエルなどは動物の餌や食用として持ち込まれ、ミシシッピアカミミガメはペット用に輸入されました。
クビアカツヤカミキリは輸入された材木と共に日本に入ってきたらしく、これは一時期話題となったヒアリと同じです。
これらの外来種は害があるとして駆除の対象とされ、まるで悪者のように見てしまいがちな風潮に、私は違和感を覚えます。
なぜなら、人間が外国から持ち込んで害が生まれたら駆除をする、そこにあるのは全て人間の都合だからです。

命に良し悪しはつかない
仏教では、二見といって、二元論や相対分別でものを見ることを戒めます。
日本で特定外来生物と呼ばれる生き物は、あくまで日本にとっての外来生物で、元いた土地では通常の生態系の中に生きていた、日本の在来種と何も変わらない、生命です。
しかし、人間によって本来超えられなかった距離を超えてしまい、様々なバランスを崩してしまう。
それに対して私たちがすべきことは、正しいことをしているかのような顔ではなく、謝罪と反省を込めた、大きな責任を伴った駆除なのだと思います。
またできるならば、その命を次に活かせるような技術や仕組みが生まれるとよいのかもしれません。
外来生物をペットの餌として買い取るという取り組みもあるようなので、食用、肥料、飼料など、何かしらの形で殺して終わりにならない形が整っていくことを良いですね。
まとめ
駆除の対象となる外来生物は、私たちが生きるという都合のために命を奪わざるを得ない存在です。
(奪わずに共存できる道があれば一番いいのですが)
外来生物に限らず、しばしば話題になる熊や猪などの在来の野生動物も、時には害獣になります。
害獣も害虫も、存在自体が害なのではなく、人間の生活にとって害があるだけであることを忘れてはいけません。
雑草と呼んで刈り取る草もそうです。
生活で消費するだけでなく、私たちは日々数えきれないほどの命を背負って生きているのです。
これまで【肉を食べるということ】でも取り上げてきたように、私たちは肉を食べようが植物を食べようが、何かしらの命をいただいて生きています。
私たちにできることは、それを後ろめたく思ったり、罪悪感に苛まれることではなく、いただいた命の分の責任を負って生きるということに尽きるのかもしれません。
関連情報