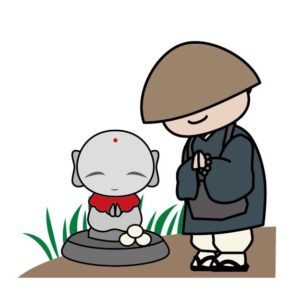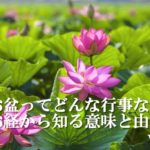去る2022年2月15日、秋葉原の精進料理カフェ「こまきしょくどう~鎌倉不織庵~」にて、
〝禅活しょくどう〟が開催されました。
曹洞宗の食の精神を学び、それを実践しながら精進料理を頂くという体験型イベント。
今回は私なおえが当日の様子をお伝えしたいと思います!
Contents
禅活しょくどうについて
ワークショップ開催とはいえ、世間はまだまだコロナに翻弄され、落ち着かないこのご時世。
当日は少人数規模で、ある程度テーブルとテーブルの間に距離を置き、一卓に一席。
そして透明なアクリル板も設置され、しっかりとした感染予防対策の上、開催されました。
そしてこの日の2月15日はお釈迦様の命日にあたるということで、
「~涅槃会晩ごはん~」がコンセプトでした。
今回の献立
そんな涅槃会に因んだ今回のこまきさんによる精進料理メニューはこちら
・茶粥
・飛龍頭
・切り干しダイコン
・大学芋
・ブロッコリーのインドいため
・漬物
・ごま塩
・いちご豆乳白玉あんみつ

当日の様子
まずはしんこうさんから食事作法についての説明があります。
食事作法といっても、行うのは主にこの3つ。
一、器や箸は両手で扱う
二、食べる時は器を口元まで持ち上げる
三、箸先は人に向けない
それから皆さん一緒に合掌をして、食前の偈をお唱えし、『いただきます』🙏
食事中に会話はせず、黙食。
ちょうど私の席は、しんこうさんの食事姿が視界にはいる位置だったので、
食事作法のお手本にするべくこっそりチラ見をしながら食事を頂きました。笑
さすがは禅活の食担当ことしんこうさん。
とにかく食事作法がスマートでキレイ!!
禅活のYouTube動画でもしんこうさんのただただ丁寧に食べるシリーズは人気企画のようですが、
動画で見ていたとおり!食事作法がキレイなのはもちろん、更には美味しそうに食べる姿も話題です。
正に今、その実写版が目の前に。笑
一方私自身はというと、このイベントには今回で四度目の参加になるのですが、なかなか作法に慣れず…。
一旦両手でお皿を置いて、
いやその前にお箸は自分の方を向けて持って...
と毎回脳内で食事作法をシミュレーションしながらの食事に大慌て
頭では分かっているつもりでも気を抜くと忘れてしまう自分と、
今回も何度も向き合うことになりました。
おそらく食事中の私は挙動不審だったことでしょう。笑
ただ、そんな脳内大忙しの一方で、一品一品ゆっくり時間をかけて口にするからか、
咀嚼する度に、お料理の美味しさが心の底から身に沁みて感じます。
『わぁ~~ 美味しい~😍』
と心の中で何度も呟いたり、お料理の中に入っている見た目や食感が卵やお肉に似ている物を、
一体何の食材で作られているのだろう?
豆腐?いや違うか...と自問自答したり想像したりしながら食べるのも楽しく、
思わず孤独のグルメの井之頭五郎さんに自分を重ねてしまいました。笑
最後に一枚だけ残すようにと事前に伝えられたお漬物を使ってお茶でお茶碗を洗います。
それを飲み干すと、お茶碗がピカピカに!
何とも嬉しく清々しい気持ちになりました。
食後はしんこうさんからデザートに入っていた白玉団子が涅槃会に因んでいること、
そして涅槃会が起源とされている現代のお通夜について、とても興味深いお話もありました。

参加した感想
普段はメイン料理として食べているお肉やお魚を一切使用していない精進料理は、
何か物足りなさを感じてしまうのでは?と思っていたのですが、全く要らぬ心配だったようで、
心もお腹も不思議なくらい満足感でいっぱいに。
食事作法に意識がいっているからなのか?
ハタマタ、こまきさんのお料理の魔法なのか?
永平寺の雲水さん達は毎日この食事作法と精進料理で修行生活を送っていて、
ましてやそれが何百年もの時を経ても途切れることなく、変わることなく、
未だにずっと続けられているということ自体、感銘を受けざるを得ません。
と同時に、1日3回あるこの食事の時間がいかに重要な意味を持つものなのかを非常に考えさせられます。
また、食べ物だけではなく食器に対してまでも敬意を払うかのようなこの曹洞宗の食事作法。
今回までの実践を通して、
『いただきます(命をいただく)』
という言葉の意味を改めて考えるようになりました。
今、自分の目の前にあるお料理は命ある素材それぞれが、
沢山の方の手によって生産され・運ばれ・調理され・存在しているということ。
辿って行くとキリがないくらいの無数のご縁です。
コロナ禍でお家時間が増えた昨今。
日常生活の食事でもこの食事作法を実践したり、食材を無駄なく調理する方法をもう一度考えてみたいと思います。
食べる時の『いただきます』には、無数のご縁を思い浮かべながら丁寧に。
心を込めて。
それから、いつか私もしんこうさんのようなスマートな食事作法を身につけられるよう、
日々精進してまいります笑