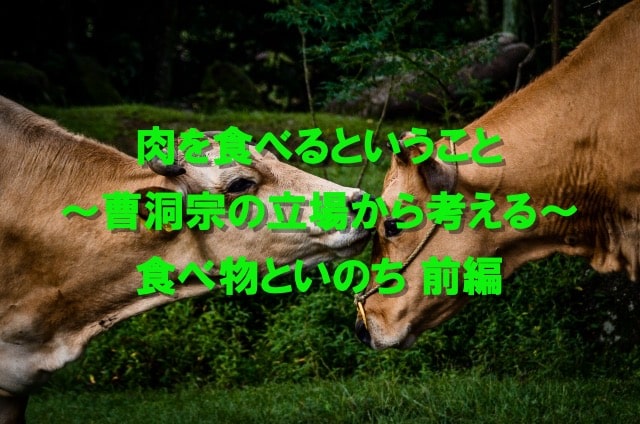
スポンサードリンク
前回新シリーズに突入した、曹洞宗僧侶として肉食を考えるこちらの「肉を食べるということ」。
今回からは肉食の前提となる「いのち」の捉え方について、2回に分けて考えてみたいと思います。
Contents
仏教といのち
まず、肉食と菜食の一番大きな違いはなんでしょうか?
それは当然、元が動物か植物かという違いです。
では動物と植物はどう違うのでしょうか?
血液が流れるかどうかならば、昆虫や無脊椎動物が命に入らなくなってしまいます。
細胞が働いているかどうかで言えば、動物も植物も同じです。
しかしそれでも、動物と植物、肉食と菜食が明確に分かれています。
そこでまずはお釈迦様がおられた頃のインド仏教まで遡って、その違いを見ていきましょう。

インド初期の仏教
まず、お釈迦様がいらっしゃった頃のインド仏教にはこんな特徴があります。
・出家と在家の生活がはっきり区別された
→出家者は調理や耕作ができない。
・基本的に肉食は問題無し
→「自分のために」屠畜されたのを見た・聞いた・その疑いがあるものはダメ
・食事は托鉢によって得ていた
→一般人の食事をわけてもらうので肉が入ってるのも当然だった
こうした特徴がある中で、お釈迦様は動物と植物の違いをどのように区別したのでしょうか。
それは、その生命体に「意思」があるかどうかでした。
動物は意思を持つことで喜怒哀楽を示し、意思によって自分の行動を決め、意思を持つことで痛みや苦しみを感じると考えたのです。
そこで、こうした意思を持つ(と考えられる)動物を有情物、意思のない(と考えられる)植物や鉱物を無情物として区別したのです。
そして、お釈迦様はこの有情物を殺すことを殺生としたのです。
現在では、この有情物は生き物全てを指しますが、お釈迦様は特に牛や豚や羊、猿、人間などの哺乳類のことを言っていたようです。
なぜなら、これらの哺乳類は、仏教よりも前からあったバラモン教という宗教の儀式で生贄とされていたからです。
お釈迦様はこの宗教儀礼での生贄を、厳しく禁じました。
それは、他を苦しめ、犠牲にして自分が幸せになろうとする自己中心的な考え方を戒めるためです。
そして、この生贄の否定こそが仏教が不殺生を説く原点だったとも言われています。
そのため、初期の仏教で殺生という場合には、主に陸上の動物を殺すことを意味したようです。
※ただし、僧侶は草木を傷つけてはいけないという戒律もあったので、植物なら何しても良いというわけではなかった
お釈迦様死後の仏教
そしてお釈迦様がお亡くなりになった後、教えを継いだ弟子たちによって仏教は論理的に整理されていきます。
その過程で、僧侶たちはどんどん研究者のようになっていき、仏教は徐々に出家した僧侶の学問のような性格を強めていきました。
すると段々、お釈迦様の説いた修行生活があってこその仏教の姿が失われていったのです。
そこで一部の人々によって、本来の仏教に立ち返ろうとする動きが出てきました。
しかみそれは、出家した僧侶だけでなく在家の一般人でもさとりを開ける、仏になれるという、より多くの人が救われるという新たな仏教の姿でした。
ここから生まれた仏教を「大きな乗り物」という意味で大乗仏教と言います。
中国や日本に伝わった仏教はこの大乗仏教の教えです。
そして大乗仏教では、人間にはさとりを開いて仏になるための素質、あるいは可能性が備わっていると考えるようになります。
この仏になる素質・可能性のことを仏性といいます。
はじめは、この仏性は修行ができる「人間だけ」に備わっていると考えられていました。
ところが、時代と共に徐々にその範囲が広がっていきます。
動物も意思を持っているんだから仏性があるんじゃないか。
それなら虫だって…。
そうして範囲が広がっていった結果、お釈迦様の死後数百年を経て成立したと言われる『大般涅槃経』というお経では
「一切衆生悉有仏性(一切衆生は悉く仏性有り)」
つまり「全ての生物には悉く仏性がある」と説かれました。
それによって、僧侶たちの間に仏となる可能性を持った生物を食べることに抵抗が生まれてくるのです。
さらには、この時インドで力を持っていたヒンドゥー教とジャイナ教は徹底した菜食を説いていたこともあり、世間は宗教に菜食を求める空気が流れていたようでした。
動物には仏性がある上に、世間では菜食ブーム。
こうした社会の影響も受けながら、大乗仏教は必然的に肉食を戒めるようになっていったのでした。

中国・日本へ
中国に伝わったのは、ざっくり言えば様々な過程を経て生物みんなが仏になれる、肉食は控えようという考えを持った、この大乗仏教の教えでした。
中国に伝わると、僧侶の修行生活は托鉢の習慣が無い風土に合わせて変化し、作務という形でインドでは禁じられた農耕や調理が可能になります。
そうした過程を経て、ついに仏教は日本に伝わるのです。
すると、日本には元々肉食をタブー視する考え方があったため、菜食の色が濃くなった仏教はすんなり受け入れられたのでした。
そして、日本に仏教が伝わってから約600年後、西暦1200年に生まれたのが、日本に曹洞宗を伝え、永平寺を開かれた道元禅師でした。
前半まとめ
次回は曹洞宗の立場から食べ物を考え、曹洞宗にとっての「いのち」とは何かについてお話しします。
今回抑えていただきたいのは、
・初期の仏教は動物の殺生は禁じたが肉食は許された。
・徐々に動物と植物の区別がなくなっていった。
という考え方の変化です。
なかなか複雑な話にはなってしまいますが、何卒お付き合いください。























