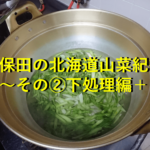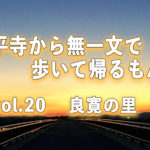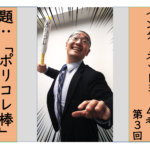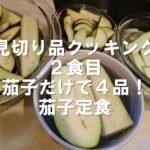スポンサードリンク
2018年もあっという間に過ぎ去り、大晦日を迎えました。
大晦日というと色々なカウントダウンがありますが、除夜の鐘もいまだ根強い人気があります。
煩悩の数である108回鐘を撞き、新年への気持ちを新たにする、そんな除夜の鐘についてちょっと考えたことを書いてみます。
Contents
除夜の鐘と煩悩
除夜の鐘の起源は中国にあり、日本には鎌倉時代に伝来したと言われています。
筆者は福井県の永平寺で修行していた頃、大晦日の夜中に撞いたことがありますが、そこでも回数は108回でした。
この108という数字は煩悩の数と言われていますが、たくさんあるという表現としての数字だそうで、実際には煩悩はもっと尋常じゃない数あります。
ともあれ、108の煩悩を鐘の音で滅する、というのが除夜の鐘の一般的な認識です。
では、鐘の音で煩悩を滅するとはどういうことなのでしょうか?
本当にそんなことができるのでしょうか?
あくまでも個人的な見解ですが、述べさせていただきます。

煩悩を断つ?
修行から帰ってきたばかりの頃、再会した友人に「煩悩断てた?」と真顔で聞かれたことがあります。仏道修行といえばやはり「煩悩を断つ」というのがキーワードになるようで、今もイベントの参加者様から煩悩の断ち方を聞かれることがあります。
さて、ここでいう「煩悩を断つ」という言葉。普通の言葉のように感じますが、煩悩って断ったり滅することができるものなのでしょうか?
まず、煩悩とは身心を乱す心の働きのことをいい、よく炎に例えられます。
しかしこの煩悩という炎の厄介なところはろうそくの火のように完全に消えるということがまずないんです。人は生きている限り常に身も心もフル回転で動き続けます。動いている限り、何かにつけて感情が生まれ、三大欲求というものも生まれます。
だから言ってしまうと、生きている限り煩悩はなくなるものではないんです。

「滅する」という言葉
では除夜の鐘で煩悩を滅することはできないのか、というと実はそんなこともありません。
正確にいうとこの「滅」という言葉が普段私たちの知っているものと意味合いが違うんです。
滅という言葉の元となるニローダというインドの古い言葉は「制する、抑止する」という意味を持っており、古いお経ではほとんどがこの意味で使われているそうです。
その意味で考えるなら、「煩悩を滅する」というのは煩悩を制する、つまりコントロールして暴走しないようにすることなのです。

お釈迦様式、煩悩の滅し方
古い仏教経典にはよく悪魔が登場します。この悪魔というのはお釈迦様を楽な方に導こうとしたり妥協させようとして耳元で色々とささやきます。
お気づきかもしれませんが、この悪魔こそお釈迦様の煩悩なのです。
この煩悩の化身である悪魔を、お釈迦様はある言葉で撃退します。
それは
「私はお前を知っている」
です。これを言われた悪魔は「この人は私が誰だか知っている」とうなだれて去ったと書かれています。
そう、悪魔の弱点というのは、自分の中にある弱さや汚さを認め、向き合うことでした。
つまり、煩悩を滅する方法、コントロールする方法というのは、自分が気づき、認め、反省することだったのです。

除夜の鐘の音に乗せて
筆者は昨年から、ご縁のあるお寺で除夜の鐘のお手伝いをさせてもらっています。
お手伝いの内容は、日付の変わる30分前頃からたくさんの方がお参りにきて、鐘を撞く横でお経を唱える、というものです。
合掌し、鐘を撞き、再び合掌。
その横でお経を唱える、というのを繰り返してると、少し変わった男性がいました。
ほとんどの方が鐘を撞いたら手を合わせて次の方に交代しているのに、その方は鐘の音が小さく、かすかになってもずっと目を閉じたまま合掌し、ついに音が止むと、少し名残惜しそうに去っていきました。
この時男性が何を想っていたのかはわかりません。
しかし、撞いた瞬間は大きく響き、徐々に小さくなっていく鐘の音に自らを重ね、来る新年をより良いものにしようという想いが、そうさせたのではないかと筆者は思います。
除夜の鐘がなぜ煩悩と結びついたのか、学の浅い筆者にはわかりません。
鐘の音とともに手を合わせ、今年一年の自分のわがままな部分や、それがきっかけでカッとなってしまう身勝手さ、そして気づかないうちに煩悩に振り回される自分に気づいた時、鐘の音が小さくなっていくように煩悩の炎もまた弱火になっていくのではないでしょうか。
仏教とは煩悩を断ったり無くしたりする教えではなく、上手に付き合っていく教えです。
除夜の鐘は楽しいカウントダウン行事の一つかもしれませんが、鐘を撞くその瞬間だけ、これまでの自分の煩悩と向き合い、来年に向けて手を合わせてみると良いかもしれません。