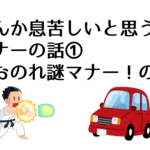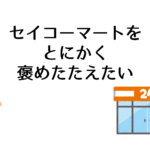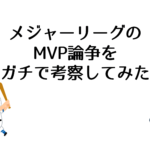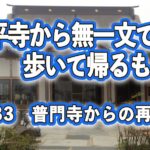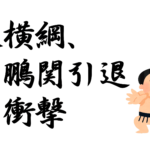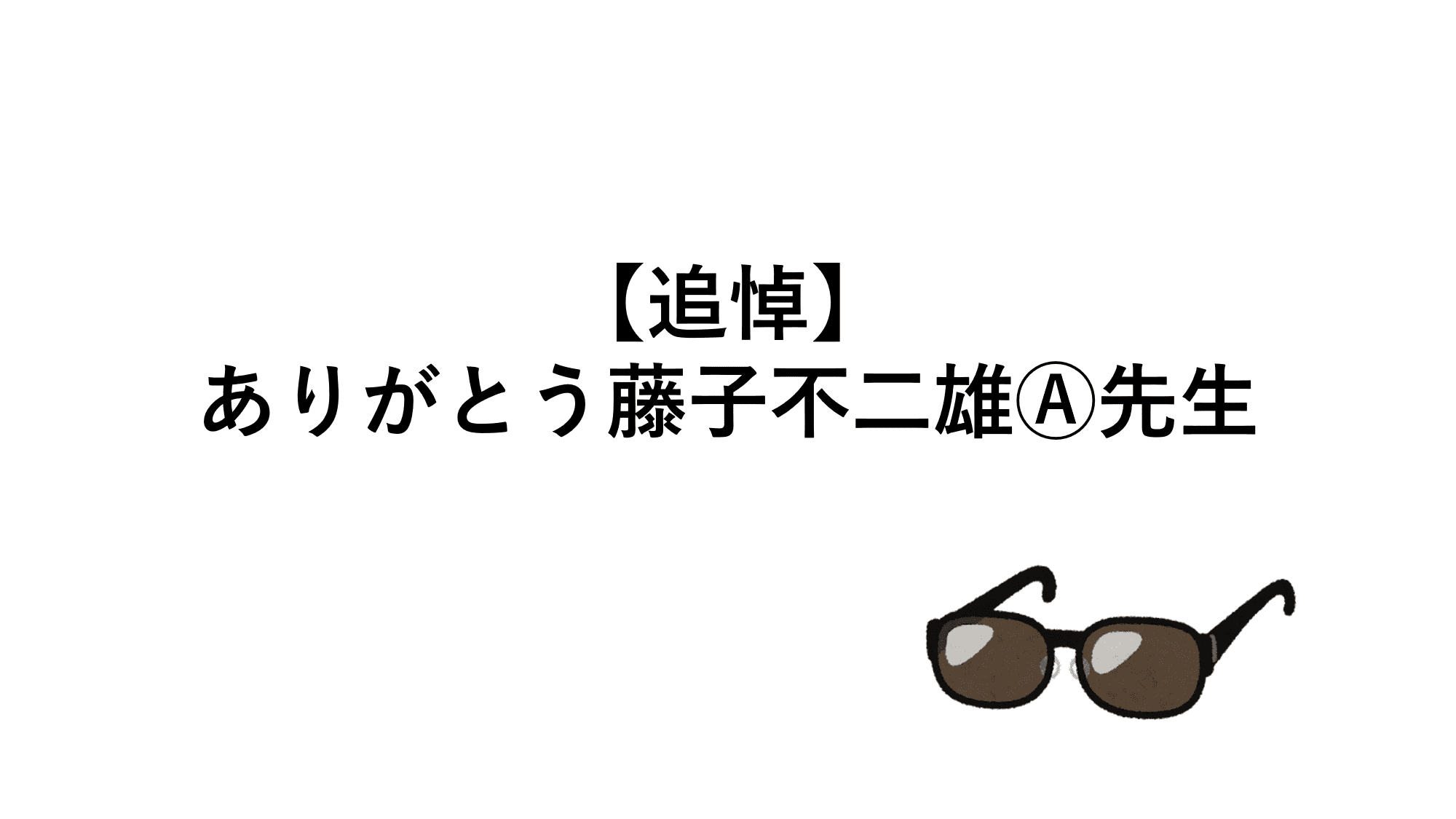
令和4年4月7日。
『笑ゥせえるすまん』『忍者ハットリくん』『まんが道』『少年時代』『魔太郎がくる!!』などで知られる、藤子不二雄Ⓐ先生の逝去の報がもたらされました。
Ⓐ先生の作品につきましては禅活のYouTube動画内の企画「禅活マンガ研究会」でも、
3度にわたって紹介させていただきました。(記事の最後に動画を貼り付けておきます。ご興味があれば是非。)
今回は、あらためて両先生とその作品への思いを、
ひとりの藤子不二雄ファンとして記事にさせていただきたいと思います。
Contents
藤子不二雄作品に育ててもらった
この記事を書いている久保田が生まれたのは、昭和58年(1983年)です。
折しも藤子両先生の活躍がもっとも目覚ましい時期に、幼少時代を過ごしました。
藤子不二雄旋風とまで言われた時代。
ドラえもん、エスパー魔美、チンプイ、21エモン、キテレツ大百科……
忍者ハットリくん、怪物くん、ウルトラB,、プロゴルファー猿……
テレビのゴールデンタイムから再放送、あるいは特別番組で……
当時の子どもたちの大多数は、藤子不二雄両先生のアニメをひたすら見続けて成長したと言っても過言ではありません。
もちろん私もその一人です。
『忍者ハットリくん』『怪物くん』『笑ゥせえるすまん』『プロゴルファー猿』など、
Ⓐ先生が作詞した楽曲の1番は今でも空で歌えますし、
少なくともサビのメロディは大抵覚えているほどです。
特にF先生のドラえもんに関しては、
登場するひみつ道具を丸暗記してノートに模写したり、
オリジナルひみつ道具をいくつも考案したり、
映画原作の大長編ドラえもんシリーズでは「いいシーン」のページ数を覚えてしまったりするほど、
大好きでした。
子ども向けアニメを藤子両先生が席巻した、その時代。
数ある藤子作品の中でもひときわ異彩を放つアニメがありました。
それが、Ⓐ先生の
笑ゥせえるすまんです。
通常放送は深夜の時間帯ということで、当時小学生の私が観ることはなかったのですが、
時折、21:00~23:00に特別番組として放映されていました。
不気味だけれども、どこか愛嬌のあるキャラクターの喪黒福造。
「ココロのスキマ お埋めします♥」
そのスキマに付け込まれ、破滅してしまう登場人物たち。
ほぼ同じ絵柄でありながら、
他の藤子アニメにはない残酷さや不条理さ、
扱うテーマのリアルさなどが相まって、
幼心に、不思議と魅力的に映りました。
藤子不二雄両先生のマンガ作品というと、子ども向け、という印象をお持ちの方も多いかもしれません。
しかし「笑ゥ」に代表されるⒶ先生のブラックユーモア作品や、F先生のSF短編作品群などは、子ども向けというよりもむしろ大人が読んでこそ楽しめる内容のものが多いと思います。
幼少時代から青年期まで、長くともにあったマンガ。
私にとって、それが藤子作品でした。
FからⒶへ
「笑ゥせえるすまん」が好きだったのは確かなのですが、もともと私はどちらかと言えば、F先生の作品の方を好んで読んでいました。
しかし、自分が成長するにしたがい、藤子作品への興味はしだいにⒶ先生の作品へと移っていきます。
その理由は、Ⓐ先生のパーソナリティに強く惹かれたというのが、もっとも大きかったように思います。
いつもサングラスをかけていて、社交的で、お酒やギャンブルも嗜む。
座右の銘は「明日に伸ばせることを今日するな」。
いわゆる「ダンディなちょいワル親父」という感じ、なんともカッコよく思えた。
そしてⒶ先生の生まれが富山県の曹洞宗寺院だったということで、親近感がわいた。
このように、興味を持つに至ったきっかけは本当にささいな共感だったと記憶しています。
また作品に目を向ければ、『笑ゥせえるすまん』や『ブラックユーモア短編集』の中には、
現実社会で自分が直面している悩みや問題を代弁しているかのような人物が登場したりもして、
ますます共感を強めていきました。
藤子不二雄Ⓐ作品の中でも…
そんな藤子Ⓐ作品の中でも、今なお私の心を捉えて離さないのはⒶ先生の描く青春群像劇です。
ここで、特に2つの作品をおススメとして紹介しておきたいと思います。
一つ目は「まんが道」。
そして二つ目は「少年時代」です。
「まんが道」は藤子Ⓐ先生自身をモデルとした作品です。
日本のマンガ黎明期の中で、手塚治虫と言う巨大なシンボルに惹かれながら、のちのマンガ文化の礎を築いていく赤塚不二夫や石ノ森章太郎らとトキワ荘で過ごした日々が描かれています。
一方の「少年時代」は、戦時中、学童疎開で東京の親元を離れて富山に移り済んだ少年が、時に残酷な子ども社会の中で成長していく姿を描いた作品となっています。
この両作品が描く「青春」は……
誰の心の中にもある、輝いて、色あせない、
あの頃。
を、くっきりと浮かび上がらせます。
郷愁、憧憬、懐古……
見るたび、読むたび、そうした感情を強烈に呼び起こしてくれるのです。
もう20年近く前のことと記憶していますが、
NHKBSで放送されたマンガ批評番組「BSマンガ夜話」にて「まんが道」が取りあげられた際の、
ある出演者の発言が今でも心に残っています。
「まんが道はねえ。正直なところ、やりたくないんだよ。」
「美しすぎて。」
「この作品に、とやかく言いたくないんだ。」
一言一句、正確に覚えているわけではありませんが、このような発言でした。
誰の心の中にもある、掛け替えのない青春。
色々な悩みを抱えながら、それでも夢中で何かに打ち込んだ、あの頃。
今なお美しく輝くそこには、誰も手出しができない。

マンガを批評する立場の出演者に「美しすぎて」「とやかく言いたくない」とまで言わしめた作品、「まんが道」。
ちょっと青春に帰りたい人には、是非読んでみてほしい作品です。
藤子Ⓐ先生の描く「青春」が魅力的に映るのは
ここからはやや批評っぽい内容になってしまうかもしれません。
藤子不二雄研究はすでに多くの方がなさっていることなので、
あくまで私個人の感想とお断りした上で、手短に「なぜ藤子Ⓐ先生の描く「青春」が魅力的に映るのか」を述べたいと思います。
その理由は、2つ。
徹底して登場人物の主観を描く。
マンガを描く際に、ネーム(絵コンテ)を切らないらしい。
「青春」は、まさに主観そのものです。
乱暴な言い方かもしれませんが、そこに他者の入り込む余地はありません。
マンガや小説などの創作において、時に主人公でない登場人物のストーリーが語られるケースがありますが、
こと青春を描くにあたっては、それは不要のものだと私は思っています。
そして、ネームを切らない(らしい)ことは、それだけ展開が荒くなりがちということでもあります。
そのため一見、不要に見えるコマも入り込みます。
必要な描写がこぼれ落ちたり、「不合理」なことも生まれやすくなります。
しかし青春とは得てして、「迷い」や「悩み」、「不合理」や「不条理」の中にあるものではないでしょうか。
無駄足や遠回りの末に、気づけば進んでいる。
ストーリーとしては「冗長」になってしまうことも多いかもしれませんが、
そんな青春の姿を描くにあたっては、「無駄」や「不合理」は省いてはならないように思います。
徹底して登場人物の主観を語り、不合理も不条理もそのまま描き出されるからこそ、
「青春」としてのリアルが生まれ、Ⓐ先生の青春群像劇が魅力的になっているのだ、と私は思います。
おわりに
今回は藤子不二雄Ⓐ先生の訃報に際し、追悼の意を込めて、思うところを述べさせていただきました。
記事を書いてみて、あらためてⒶ先生のマンガが、私にとって掛け替えのない青春だったんだな、と実感しています。
今は、なんだか、映画「少年時代」を見終えたときのように、心にぽっかりと穴が空いたような寂しさを感じています。
藤子不二雄Ⓐ先生。
そして藤子・F・不二雄先生。
すばらしいマンガをありがとうございました。
そして、お疲れさまでした。