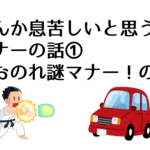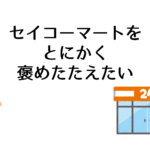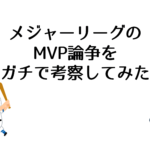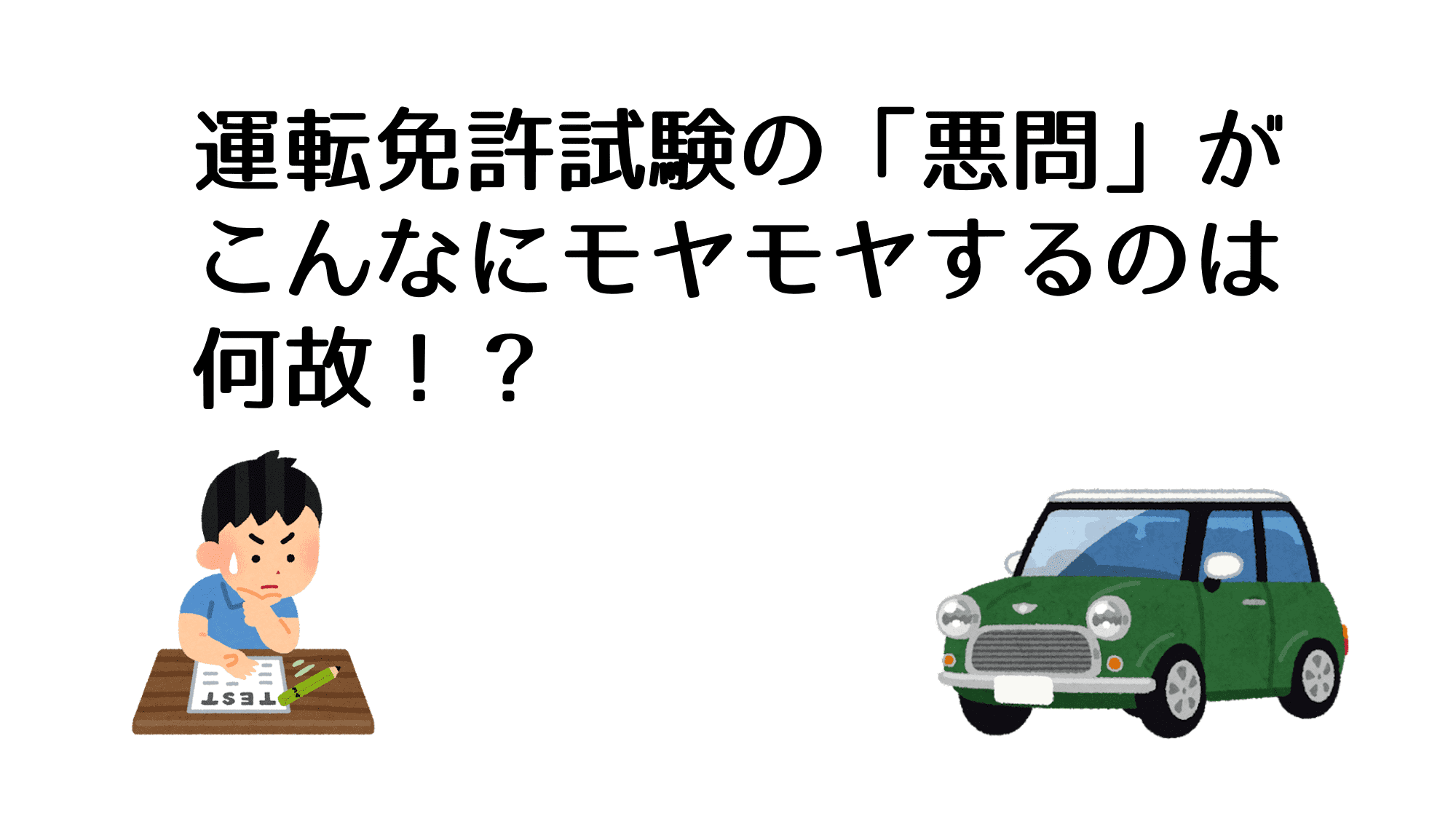
地元に、よく知られた一時停止の取り締まりスポットがあります。
そこは曲がりのきついカーブの先に一時停止位置があり、
さらに停止線の先が本線への合流になっていて、
本線の車の流れに気を取られていると標識を見落としやすい取り締まりのメッカのような場所。

先日、久しぶりにその場所を通ったときのことです。
いつもそこを通る時には、一時停止が必要な場所だとわかっているので、
あらかじめ十分に減速し、停止するようにしています。
その日は、前に先行車が3台いました。
先を行く車の後ろについて走っていると……
なんと!前を行く3台全車が一時停止を完全に無視したのです!
「いくらなんでも、3台のうち1台も一時停止に気付かないなんてことあるのか!?」
あまりの出来事に、呆気に取られてしまったのですが、自車が一時停止に差し掛かったとき、その謎が解けました。
先を行く3台すべてが一時停止に気付かなかった理由。
それは3つ考えられました。
① 一時停止「止まれ」の標識が、草やぶに隠れて見づらくなっている(カーブの途中で突然現れるような感じ)
② 停止線がかすれて、ほとんど消えかかっている
③ 前を行く車に気を取られていると、上記の標識、停止線になかなか気づけない
そこに一時停止があると知っていても、ともすれば停止位置を見落としてしまいそうな状況を見て、
「これで一時停止違反で取り締まられたら、先頭車両はともかく、後ろの車は納得いかないよなあ……」
と、思いました。
そしてこの時、運転免許試験の「悪問」が頭に思い浮かびました。
Contents
納得いかない運転免許試験の「悪問」
運転免許を取得する際には、学科試験をクリアすることが必要になりますが、
一部の問題文は「難しすぎる」とネット上でたびたび話題になります。
私が運転免許を取得した際にも、
「どうして答えが、コレになるんだ?」
と、自分の理解が及ばなかった問題文がいくつかあったのを覚えています。
とあるニュース記事に、そうした「悪問」の例がいくつか挙げられておりましたので、引用し、ご紹介いたします。
①「夜間の道路は危険なので気を付けて運転しなければならない」
答え:×(夜間以外も気を付けて運転しなければならないから)
②「赤信号では必ず停車しなければならない」
答え:×(救急車やパトカーといった緊急車両はその限りではないから)
③「原動機付き自転車は公道で50km/h以上で走ってはならない」
答え:×(正しくは「30km/h以上で走ってはならない」から)
④「公道を普通自動車で運転する際には必ずシートベルトを装着する必要がある」
答え:×(普通自動車でない大型、中型自動車でもシートベルトをしなくてはならないから)
⑤「制限速度30km/hの道路では、その制限速度を超えて走行してはいけない」
答え:×(非常時はその限りではないから)
いかがでしょうか。
「難しすぎる」というより「納得いかない」「意地が悪すぎる」という印象を持たれる方が多いのではないでしょうか。
実際に、今現在もこうした問題が出題されているのか確かめたわけではありませんが、
このような問題が運転免許試験に採用されているのだとしたら、
なんだかモヤモヤ、イライラして、非常に面白くない気持ちになります。
どうしてこんなに不愉快なんだろう?①~「悪問」の意図は?
ここで自分に対して、ひとつの疑問を抱きました。
「どうして私は、ただの問題文ひとつに、
こんなにも不愉快な気持ちにさせられてしまうのだろうか。」
……しばし考えた結果、
「悪問」から人の「悪意」じみた感情を受け取ってしまうからだろう、
と思いいたりました。
正直に言って、引用した問題文からは、
「とにかく間違えさせてやろう」
あるいは、
「意地悪な問題を作って受験者に嫌がらせしてやろう」
といった非常にネガティヴな感情が込められているように思えます。
悪問設定の意図を最大限好意的に解釈するならば、
「交通法規の中には、この問題のように、意味がないと感じてしまうものもあるかもしれないけど、ルールはルールとしてしっかり守ってね」
という思いが込められているのかもしれませんが、
自分で言っておきながら、これはいくらなんでもこじつけに過ぎる思います。
自動車は、ともすれば凶器になりうる危険なものです。
だからこそ運転免許を取得するための試験として出される問題は、
回答者に交通法規を正しく学ばせ、
注意を喚起し、
危険察知能力や法令順守の意識などを高め、
安全運転に向かわせるような設問こそがふさわしいと言えるでしょう。
先ほど紹介した「悪問」が「悪問」である最たる所以は、
その問題に正答(あるいは誤答)したところで、安全運転にはつながらない、
と考えられるからです。
一生懸命勉強して、
得られた教訓が、
「理不尽に思えるルールにも従わなければならない」
だけでは、あまりにむなしい。
どうしてこんなに不愉快なんだろう?②~「悪問」が損なう信頼関係
さらに言えば、私は試験というのは「言葉を用いたコミュニケーション」のひとつだと考えています。
人はコミュニケーションを通じて他者と信頼関係を築きます。
では、先述した「悪問」は、果たして人と人の良いコミュニケーションであると言えるでしょうか。
答えは否です。
「ひっかけてやろう」「間違えさせてやろう」という意志によって作られた問題文は、
「だまされた」「どこまでも意地が悪い」という印象を抱かせます。
そこで生まれるのは信頼関係どころか、不信感ではないでしょうか。
コミュニケーションは、人間にとってもっとも大切なものの一つです。
コミュニケーションは非常に繊細なものです。
すこしの努力でうまくいくこともあれば、どんなに努力してもうまくいかないこともある。
だからこそ、なるべく円滑なコミュニケーションをとれるように気を配る必要があります。
いたずらに人を陥れようとするような運転免許試験における悪問は、
私にとってみれば「コミュニケーションの軽視」です。
こうしたことも、「悪問」を不愉快に感じてしまう原因なのかもしれません。
おわりに:人を導くためには
人を導くための方法は、大きく分けて2つあると思います。
ひとつは、正しい方を向かせること。
そしてもうひとつは、誤った方に向かわせないことです。
これまでの話で行くと、
運転免許試験での悪問や、
停止線がかすれていて、草に隠れて標識が見えづらい位置での取り締まりは、
「わざと間違いを犯させてから、戒める」
というやり方です。
私にはこのやり方には、賛同できません。
人を安全運転という正しい道に向かわせるには、
適切な問題を設定したり、
停止線を引き直し、草刈りや標識の増設をしたり、
そもそも間違いを犯さなくても良いように配慮するのが真っ当なやり方ってもんじゃないでしょうか。
運転だけに、無用な衝突や軋轢を生まないようにしていきたいものですね。