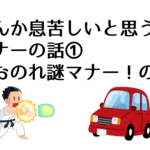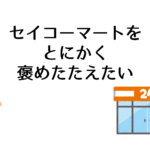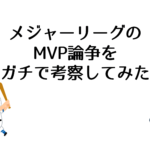スポンサードリンク
観世音菩薩(観自在菩薩)。
いわゆる、観音さま。
観音さまを篤く信仰していた祖父母の影響もあって、実は久保田にとって観音さまはちょっと特別な菩薩さまです。
仏教には様々な仏さまがいらっしゃいますが、その中でも観音さまの仏像を見ると、
優しかったおじいちゃん、おばあちゃんの顔が思い出されて少しほろりときてしまうのです。
……
地蔵菩薩さまと並んで私たちにもっとも身近な菩薩様である観音さま。
今回は観音さまのお話です。
Contents
観音菩薩のありかた
観音さまがどのような菩薩さまかと言いますと、
そのお名前「観世音菩薩」の通り、
世間に苦しむ人々の声を聞き洩らさず、救いの手を差し伸べてくださるという菩薩さまです。
私たちの苦しみには、様々な形があります。
当然、それを救うには一つの方法では事足りません。
そこで観音さまは、救いの手をまんべんなく広げるために、
救済の求めに応じてそのお姿を33種類に変化させると言われています。
日本の各地に、○○三十三観音巡りの札所があるのは、
観音さまの三十三のお姿に由来しています。
なんとか手を尽くして、私たちに救済の手を差し伸べようとしてくださる観音さま。
その在り方に、私は憧れを感じずにはいられません。
観音供養会(in北海道)
さて今回、観音さまのお話をしたのは……
ちょうど昨日(7月19日)、久保田が住職を務める北海道のお寺で「観音供養会」を行ったからです。
久保田が住職を務める報国寺の敷地には、外周1㎞(!)もある広大な池がありまして……
その池に沿って、三十三観音が安置されております。



それだけでなく、こちら……

高さ5mはあろうかという無駄に大きな観音さまもいらっしゃいます。
これだけの観音さまがいらっしゃるということがあって……
年に一度、7月に観音さまにご祈祷供養をするのが報国寺の年間行事の一つとなっています。
池のそばに建てたD型ハウスを法要会場に、

祭壇を設けて、

参加された皆さまのお願いが、観音さまへと届くようにご祈祷をいたします。
ちなみにこの日は観音さまへのご祈祷のほか、お仏壇やお札、古いお写真などのお焚き上げ供養(焼浄会)も行いました。
※お焚き上げに際しては、消防署の許可を受けております。
祈祷太鼓の魅力
さて曹洞宗のご祈祷と言えば……

そう!太鼓です!
普段の法要では木魚を叩いてリズムをとりますが、ご祈祷法要では太鼓を用います。
「お経とか、眠くなっちゃってどうも苦手なんだよね~」
という方も、ご祈祷法要でしたら最後まで起きていられるのではないでしょうか。
個人的な感想ではありますが、太鼓と僧侶の読経が織り成す心地よい響きは、是非皆さまに体感していただきたいところです。
また、ご祈祷法要では、参加された皆さま自身の願い事を届けるということになります。
日常的に行われている先祖供養とは少しだけ意味合いが違いますので、
普段、法事などに参列していて「お坊さんがよくわからない儀式をしている」と思ってしまう方でも、
「自分自身が参加している!」と、積極的に法要に臨めるのじゃないかな、とも思います。
法要への「参加」
ご祈祷法要で、
「自分自身が法要に参加している!」と感じると言ったのは、
実は久保田自身の感想でもあります。
幼い頃、父や祖父が行っている法要は退屈で仕方がありませんでした。
とにかく動きたい盛りの小学生にとって、30分以上の時間をじっとしているというのは「苦痛」でしかありません。
お盆やお彼岸の法要は「ガマンしなければならない」時間だったのです。
それが変わったのがご祈祷法要でした。
勢いの良い太鼓と読経が心地よく、また自分のお願いごとをしてもいいというのは、幼い久保田にとってまさに救いでした。
ご祈祷法要があったおかげで、幼き久保田は法要を(なんとか)嫌いにならずに済んでいたのです。
僧侶の道を志す以前から、法要がどこか遠い世界の話ではなく、自分も参加してよいものだと感じられるようになったのは、ご祈祷がきっかけだったのだと今にして思います。
願いを掛ける、ことの意味
さて、今回の観音供養会を通じて一つ気が付いたことがあります。
それは、
神仏の力を借りるということの本当の意味は、正しい願いを持つ神仏に願いを掛けることによって、自分の願いを正しい方向に導いてもらうことなのかもしれない。
ということです。
今回、参列の皆様には、はじめに「お願いごと札」を書いていただきました。
良縁成就、商売繁盛、交通安全など、お願いごとの書き方を例示して書いていただいたのですが、
もっとも多かったのは、「家内安全」と「無病息災」のお願いごとでした。
これは皆さんが新型コロナウイルスによって、日常的に不安を感じていることの証明だろうと感じました。
新型コロナウイルスという新しい脅威を受けて、自分とその周囲の安全を願うことは当然のことです。
そこに否定を加える要素はありません。
私が感じたのは、
あくまで自分のことだとしても、
それを観音さまに願ったときに、
その願いは自分だけのものではなくて、自分以外の人のためにもなる広がりを持った願いになるということです。
たとえば「新型コロナウイルスの不安から解放されたい」という、願いを掛けたとします。
その願いが本当にかなうのは、どういったときでしょうか。
それは、ワクチンの開発やしかるべき社会の体制が整うことを経て、新型コロナウイルスが巷にありふれている風邪と同程度の疾病になったときでしょう。
そう考えると、新型コロナウイルスの不安によって願われた「家内安全」や「無病息災」は、
自分だけのものではなくて、
人類すべてにとっての「家内安全」と「無病息災」と同じ意味を持ちます。
あるいは「商売繁盛」という願い。
この願いは下手をすると、自分だけの利益を追求することになってしまう可能性もあるでしょう。
しかし、これをすべての人を苦しみから解放したいと願う観音さまに願うならば、
「商売繁盛」の願いは「商売繁盛を通じて多くの人を幸せにしたい」という願いに変わります。
自分の願いを、正しい心を持った神仏に託すことで、正しい方向に導いてもらう。
ご祈祷の大きな意味はここにあるのではないでしょうか。
法要を終えて
記事のまとめに移ります。
今回は、「観音さま」「ご祈祷」「願いを掛けること」などをテーマに書いたわけですが、
法要が終わってみて純粋に思えるのは、
太鼓による読経は……
「やっぱり気持ちがいい!」
ということです(笑)
法要を終えて、普段より幾分かすっきりした気持ちになっている自分に気が付きました。
身体の芯まで響く太鼓の音は、難しいことを考えずとも、
それだけでどこか「小さな迷い」とか「小さな悩み」を打ち払ってくれる効果があるのかもしれません。
もし、この記事を見てご祈祷に興味を抱いた方がいらっしゃいましたら、
動画投稿サイトで「曹洞宗 祈祷太鼓」と検索してみてください!
それではまた!