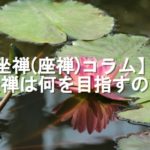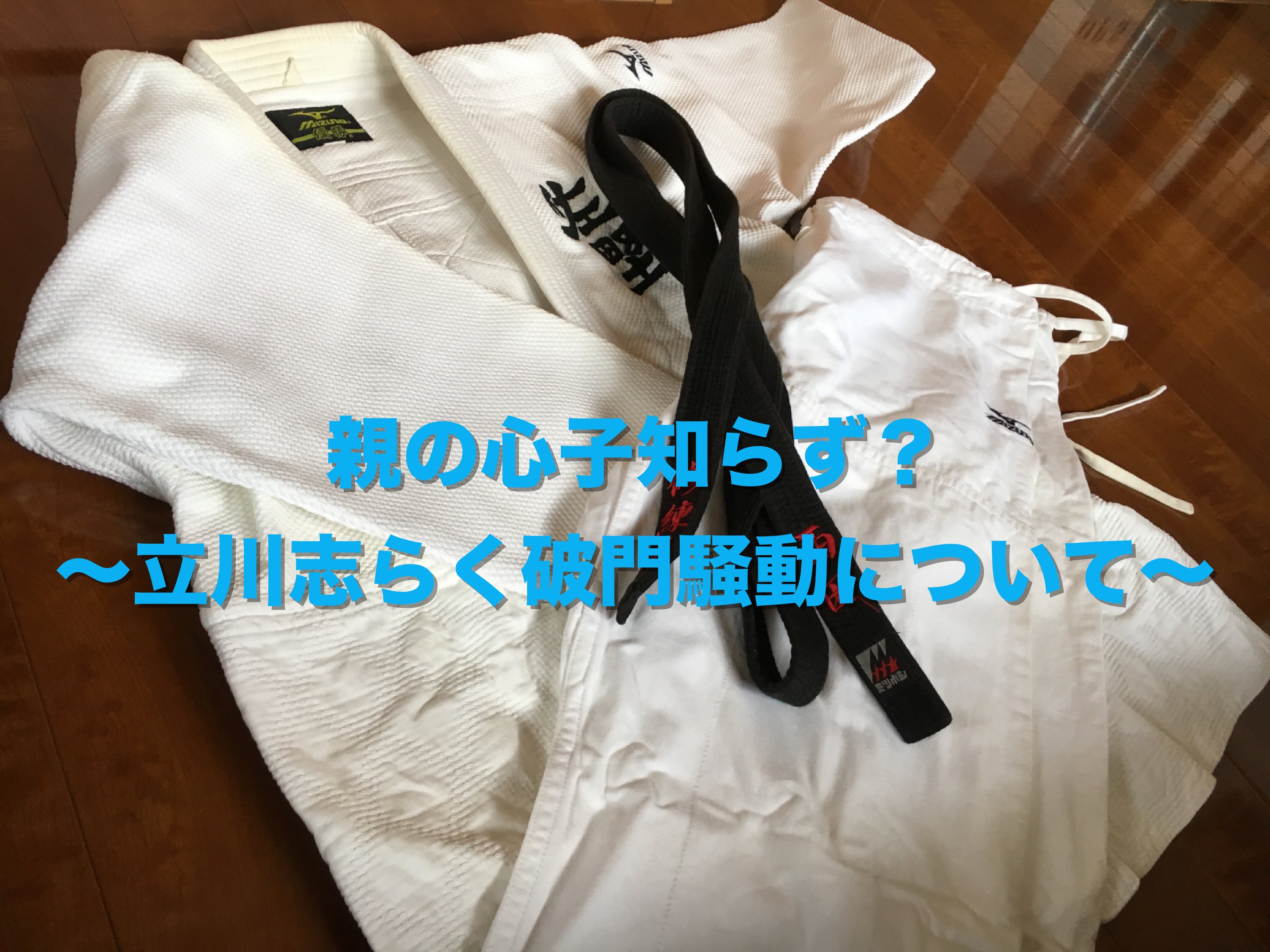
スポンサードリンク
最近少し話題になった出来事。
落語家の立川志らく(55)が、二つ目の弟子たちを全員、前座に降格させたことを明かした。
志らくは21日、ツイッターを更新し、「二つ目全員、前座に降格させました」と報告。今夏に真打ち昇進が決まっていた志獅丸をはじめ、3月に二つ目に昇進したばかりの志ら鈴も含む全員を降格させたという。ただ、期間限定のようで、「志獅丸は真打ち昇進前日まで。それぞれ期間を決めて前座修業をやり直させます」と説明した。
志らくは19日にツイッターで、自分が主宰する劇団の稽古に一門の弟子たちが1度も見学に来なかったことを嘆き、「芝居の押し付けではありません。師匠に興味があるかないかという師弟の根本の部分です。弟子が師匠に対して興味がないのなら弟子である必要はありません」と真意を説明した上で、「全員、破門にするか前座に降格するか、である」との考えを示していた。
そしてこれがTwitter上で「パワハラ」だとして物議を醸したのです。
今回は師弟関係を上司と部下の関係、支配関係に当てはめて考えるべきなのか、師匠の親心はパワハラなのか、考えてみます。
Contents
伊集院光さんの見解
この件に関して、元落語家として同じ道を通ってきた伊集院光さんは5/20(月)放送のTBSラジオ「伊集院光の深夜の馬鹿力」にて言及。
自身が三遊亭楽太郎(現円楽)の弟子だった頃に破門の危機に直面して学んだ「誠意の見せ方」を冗談半分ながらも話されていました。
空港で大泣きしながら土下座をして謝り、脚にすがりついたこと。
失敗を謝るために仙台まで夜通しバイクを走らせ、明け方にホテルのフロントに伝言を頼んで師匠には会わずに帰ったこと。
実はその裏には「空港で100kgを超える巨漢が師匠に泣きついている」という状況を作ったり、「電車もない時間に仙台まで謝りにきた」という状況を作って許さざるを得ない、もしくは許したくなるように「ギアをあげて」謝っていたのだそうです。
ただ、そうした師匠とのやりとりも含めて修行だったと語られました。
伊集院さんは、そんな思い出を振り返りつつ、今まさに弟子を育てている志らくさんに敬意を表します。
昔のままのやり方で指導していたら何を言われるかわからない社会で、「師弟」という関係を築くことの大変さを察するからでした。
稔光少年の柔道物語
私にも似た様な経験があります。
小学2年生から柔道の道場に通っていた私。
道場に通い始めたきっかけは、格闘技を「観る」のが好きな肥満児だった私に運動をさせようという母の策略でした。
それまでほとんど運動をしていなかった稔光少年にとって、柔道の稽古は当然苦行。
稽古がある月水金曜日だけ体調が思わしくなくなるという奇病(仮病)も発症するほどでした。
さらに、私には闘争心や負けん気というものがほとんど無く、初対面の人を投げたいとは思いませんでした。
じゃあなぜそんな柔道をやめなかったのかというと、それは先生が恐かったからです。
母に柔道をやめたいと言えば、「じゃあ自分で先生に言いなさい」と。
道場に入門するときは全部勝手にやってくれたのにそりゃないぜ!と今でこそ思いますが、当時は先生にそれを切り出せなくて通い続けました。
劣等感から救ってくれた言葉
もちろん、柔道が全く楽しくなかったわけではありません。
そこで出会った友達や、稽古や遠征の楽しい思い出もたくさんあります。
ただ、私が辛かったのは「強くならなければいけない」という強迫観念と「弱い自分」という劣等感でした。
私の道場には、道場のエースであり、実力は全国クラス、大学まで柔道の推薦で入学して、現在は総合格闘技で活躍しているケンシロウくんという同級生がいました。
道場の門下生を引っ張ってくれる存在であり、彼についていけばなんとかなる、そんな存在です。
そして時々、門下生が稽古に身が入っていないと、先生が「もうやらなくていい!帰れ!」と怒ることがありました。
そんな時は彼がみんなを率いて謝りにいき、なんとか続けさせてもらえました。
しかしある日、彼が謝っても先生が取り合ってくれないことがあり、同じ最上級生になっていた稔光少年に「西田謝ってみろよ」という恐ろしい矢印が向いたのです。
(リーダーであるケンシロウくんが謝ってだめだったのに、自分なんかが謝ったところで意味なんかあるもんか…。)
そう思いながらも、勇気を振り絞って先生の元に行きます。そして、
「先生、気合いを入れ直すので稽古をさせてください!」
というような言葉(緊張で覚えていない)を振り絞りました。
すると先生はこう仰います。
「そうか、わかった。西田がそう言うならいいだろう。」
私は驚きました。
それまで私は県内でも強豪と言われるその道場の中では劣等生で、先生方からは期待も関心もないと思っていました。
しかし、この一言で、先生が私を見てくれていたことに子供ながら気づいたのです。
見てくれているという実感
道場に通っていた頃、私は先生が門下生に「強くなること」を求めていると思っていました。
いわば「柔道の実力の伸び具合を見ている」と思っていたんです。
しかし、先生のその一言は、門下生の「人」を見ていたのだと、今ならわかります。
それは強い選手を育成して弱い選手を切り捨てるのではなく、柔道という「道」を通して人として育ってほしい、先生にはそんな願いがあったのかもしれません。
今私が身をおく仏道も、師弟関係を重んじられる世界であり、同じく通ずるものがあります。
今回の志らくさんの一件でも、武道や芸事の世界の人からは共感や理解が集まりました。
実際に志らくさんはTwitterで今回の件に関する自らの意図を述べられ、お弟子さんも「稽古させてください」と帰ってきたそうです。
ツイッターでこの一門の恥を世間に発信する理由は前にも申しましたが全てを晒すのが芸人だという談志の教えと、落語ファンの皆様にこいつらが馬鹿にならないように見ていてもらいたいからです。私のやり方は間違っているかもしれない。でもその私を師匠に選んだのだから仕方ない。矛盾にたえるのが修業
— 志らく (@shiraku666) 2019年5月20日
稽古場に弟子が来た。前座降格でも志らくの元で落語家をやりたいと。何故こうなったか彼らはまだ理解出来ないだろう。また繰り返すかも知れない。でも自分が師匠になったら分かる。それを期待している。甘いかも知れないが私の子供だから。 pic.twitter.com/6eGrgZGRiM
— 志らく (@shiraku666) 2019年5月21日
教え子の「人」を見ている人の叱責や厳しさというのは、時に大きな自信や安心、大きな気づきをくれるものです。
しかしそれは指導者の自己満足ではいけません。
相手の性格や個性をよく理解して、その人に合った方法で思いを伝えるのが、指導者の力量です。
あの時の先生の言葉は、私も「見てもらえている」という安心感をくれました。
時代が変わり、教育が変わり、社会が変わった現代では昔と変わらぬ師弟関係というわけにはいかないかもしれません。
それでも、「道を伝える者」と「道を継ぐ者」という関係は単なる主従関係ではないということ、それだけはこれからも変わらないし、変えてはならないと思います。
先生の遺言
結局私は中学で柔道部を引退した頃からブレイクダンスに関心がいき、高校卒業と共に柔道着を着ることはなくなりました。
時が経ち、大学4年生の冬に、私は先生の訃報を知りました。
そして先生は「お墓は西田のところに頼んでくれ」と言い遺されていました。
私が人生で初めてちゃんとお勤めした法事は、先生の四十九日となったのです。
先生が昔よく言っていた「おれが死んだらお前がお経あげてくれ」という言葉が冗談ではなかったことを私はこの時初めて知りました。
10年近く時が経って、柔道をやっていなくても先生は私を見てくれていました。
修行に行く直前の冬、先生は最後の最後に僧侶として歩き始める私の背中を押してくれたのでした。
その他、師弟関係をテーマにした記事