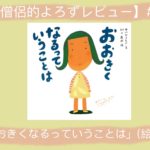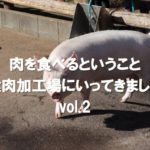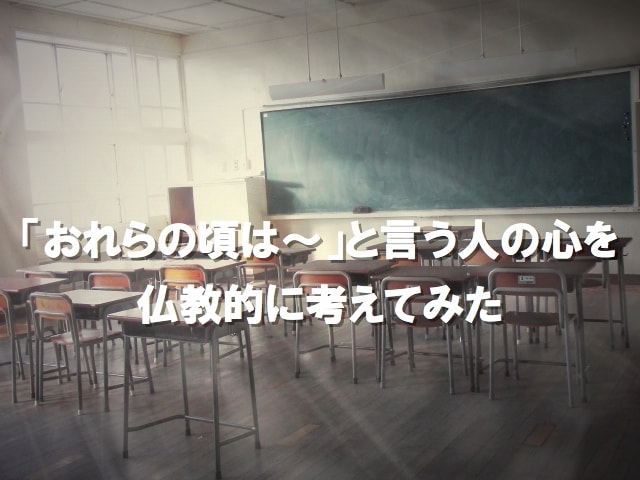
スポンサードリンク
私は平成3年生まれのいわゆる「ゆとり世代」。
小学校が土曜日も全休みになったのが、確か小学校中学年の頃だったでしょうか。
私がいる僧侶の世界は一般企業に比べて年齢層の幅がとても広い世界です。
お寺の息子さんで小学生の頃からお経を読んでお盆のお手伝いをしている子もいれば、かなりお年を召しているにも関わらずバリバリお葬式や庭掃除をする方もいらっしゃいます。
極端な話、還暦からが本番といってもいいくらい、若い僧侶からご老僧までそれぞれの立場でちゃんと役割があって、なかなか引退ということができない世界でもあります。
そうなると大変なのが世代間ギャップです。
それも、我々ゆとり世代の僧侶と団塊の世代の僧侶のギャップは凄まじいものがあります。
そこでよく言われるのが「おれの若い頃はもっと違ったけどな〜」です。
必ずしも否定的な意味で使われるわけではありませんが、多くはがっかりしたようなニュアンスで、ため息混じりに言われるのです。

Contents
ゆとられた覚えはないけれど世代
すごく、本当にすごく正直なところ、そんなことを言われても「そうですか」としか言えませんよね。
こちらは運動を起こしてゆとりを勝ち取ったわけでもなければ、なんならどれがゆとり教育だったのかすら自覚はないんですから。
ゆとられた覚えはないのに「ゆとり世代」と一括りにされ、挫折や弱音も世代のせいにされるのは、決して良い気分ではありませんでした。
ところが最近、私の中に変化がありました。
それは永平寺から帰ってきて、どこに行っても最年少だったのが、少しずつ後輩ができてきた最近のこと。
ふと気づけば「おれの時は〜」と口にしてしまっている自分がいるのです。
ああ、今は偶然自覚できたけど、無意識のうちに「あの頃」を語るおじさんになっていくんだな、とどこか切ない気持ちになりました。
いや、待てよ…。
今なら「あの頃は〜」と言う人の気持ちが少しはわかるんじゃないか?そう思いました。
そこで、仏教の視点から「あの頃は〜」という人の気持ちを考えてみることにしました。

「おれらの若い頃は〜」の深層心理
状況分析
まず私が「おれの頃は〜」と言った状況をよく考えてみます。
相手は後輩。
そして後輩は自分が一度経験した課題を今やっている。
それも、新しいやり方で。
この、自分の時と違うやり方をしている、というのは大きな要因なのではないでしょうか。
例えば、通信手段や、飲食店の種類、学校の勉強、飲み会の付き合いや飲み方。
こうした、自分が経験した、もののやり方や向き合い方が変わっている時に、つい「おれの頃は〜」と言いたくなるのかもしれません。
思い出と懐かしさと
私たちは誰もが思い出をもち、その思い出はなるべく綺麗なもの、誇れるものでありたいと大切にしています。
特に大変な思いをして達成した成功や成績、乗り越えた試練の数々は、思い出の中で永久保存版として保管されています。
しかし、時の流れは残酷で、当時は必要だからと言われて大変な思いで身につけたことや、耐えてきた理不尽が、次の若者には引き継がれていないとなったらどうでしょうか?
「あれは無駄だった」と思うのが一番怖いでしょう。
その次にはその良さを知って欲しいという思いもあるかもしれません。
とにかく、当時の自分が大切であるほどつい「あの頃」語りが出てしまうのです。

仏教から考える深層心理
では、「あの頃」という言葉が出る時、自分の中でどのような心の動きがあるのでしょうか。
実は、これは仏教のとても基本的な教えの部分です。
まずは諸行無常という現実があります。
あらゆる物事は移ろいゆくというこの世の道理で、これによって生まれるのが「苦」です。
四苦八苦という言葉がありますが、これは人間が出会う8つの「苦」のことです。
「生苦」「老苦」「病苦」「死苦」「愛別離苦」「怨憎会苦」「五蘊盛苦」「求不得苦」のうち、四苦という時は前の4つ、八苦という時はこの8つのことを言います。
そして「あの頃」という言葉を口にする時、心が直面しているのはこのうちの「愛別離苦」なのではないかと思います。
愛着があるものが別離する苦が「愛別離苦」です。
ここで「苦」を苦しいとしてしまうと「愛着があるものと別離するのは苦しい」ということで、ウンウン、わかるわかると共感だけで終わってしまいます。
しかし、この「苦」という言葉をちゃんとインドの言葉までたどると「思い通りにならない」という意味があるのです。
つまり、「愛別離苦」とは「愛着があるものが別離するのは思い通りならない」ということなんですね。
つまり、自分より年下の人に「あの頃は〜」と言っていしまう時は、教訓や親切心と一緒に、自分が愛した環境やシステムや状況が変わり、なくなってしまうことに対する切なさが含まれているのではないでしょうか。
自分が学生時代に住んでいたアパートが取り壊された時の、当時の自分の面影まで消え去っていくような喪失感。
これが「おれの頃は〜」のに含まれる成分のような気がします。

巡り巡る「あの頃」語り
私は、自分の世代に対して自分の若い頃の話を延々とする年上が嫌いでした。
それは、「おれらと比べてお前らはだめ。おれらみたいになれ」と押し付けられている気がしたからです。
しかし、その根底には、「あの頃はこんな思いをしたんだけど、それももう必要ないなんてなあ、寂しいなあ。」という本音が隠れていることもあるのかもしれません。
仮に、本当に怒りながらそれを押し付けてきたとしても、実はその人も愛別離苦に悩まされているのです。
諸行無常を受け入れるというのは、頭ではわかってもなかなか難しいことです。
もちろん、「温故知新」という言葉があるように先人たちの知恵や経験には学ぶことがたくさんあります。
我々僧侶の世界なんてその最たるもので、仏教という秘伝のタレをずーっと継ぎ足してきたからここまで残っています。
ただ、その言葉の中には、時が経って世の中が変わり、思い出がセピア色になっていくことへの切なさがあることもわかっておくと良いかもしれません。
良いところは吸収、悪いところは反面教師にして、実りがあれば最高です。
最初から、「うわ始まったよ…」と思わず、一旦聞いておきましょう。
なぜなら、私たちゆとり世代もなんだかんだ「あの頃」を語る日がくるんですから。