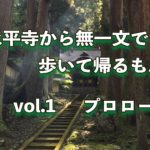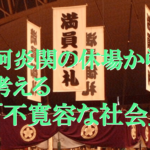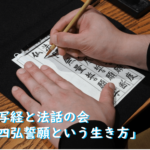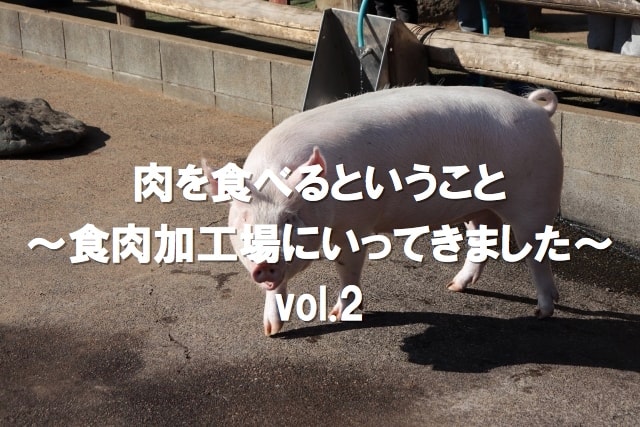
スポンサードリンク
明治時代以降に盛んになった食文化でありながら、今や日本人の食卓に欠かせない存在となったお肉。
曹洞宗の食事作法では、その食べ物がどのようにやってきたかを推し量る言葉をお唱えしますが、お肉は食卓に並ぶまでの「ある過程」が私たちの記憶からすっぽりと抜け落ちています。
その過程とは、「と畜」。
昔は屠殺という言い方をしまいしたが、現在は「と畜」に統一されています。
私は、現在所属している曹洞宗総合研究センターの研修カリキュラムで、これまでに2度、食肉加工場の見学をさせていただきました。
前回の記事では、と畜・解体をする食肉加工業に向けられてきた差別や偏見の歴史、そして現状についてお話ししました。
今回は食肉加工場で実際に見てきたこと、教えていただいたことをなるべく詳細にお伝えし、加工の過程をより多くの方に知っていただきたいと思います。
尚、今回の記事は、必ず前回の記事をお読みいただき、正しいご理解の上、お読みください。
Contents
芝浦と場のお仕事
私が見学させていただいた東京都中央卸売市場内、芝浦と場では、牛と豚のと畜・解体がそれぞれのラインで行われます。
ここで言うと畜とは、牛と豚のけい動脈を切り、血を抜く工程のことであり、そこから先の工程は解体と言います。
芝浦と場で一日にと畜が行われる頭数は、最大で牛が430頭、豚が1400頭。
この数が午前中だけで枝肉という状態まで加工されるのです。
かかる時間の短さからもわかる通り、その工程はどれも洗練された技術の結晶で、とことん無駄を省いたものでした。

東京都食肉市場・芝浦と場(HPより)
と畜解体作業の現場へ
ここからは実際に現場で見たことをお伝えします。
まず、見学をする際には白衣・長靴・帽子・マスクを着用し、手洗いやエアーシャワーなどで全身をくまなく殺菌します。
この工場全体を通して、衛生管理が徹底されており、作業工程の至るところにもその努力が垣間見えます。
豚肉のと畜解体
工場には、見学をするためのコースなどはなく、作業場の隙間を縫うように進んでいきます。
殺菌のためにお湯を使うので、場内はかなりの湿気です。
冷房も使えないため、夏場には室温が40度をゆうに超え、長靴の中でくるぶしの辺りまで汗が溜まるほどの酷暑の中での作業になるそうです。
まず初めに案内されたのは豚肉のと畜解体ラインでした。
前日のうちに全国から芝浦と場に運ばれてきた豚は検査を受け、体を洗浄された後、けい留所という場所で一晩を過ごし、翌朝、ラインへと誘導されます。
初めに、炭酸ガスで気絶させ、その間にけい動脈を切り、胸を開いて一気に血を抜く「放血」を行います。
ここでしっかりと血を抜かないとお肉としての味が落ち、市場での価格もガクッと下がるため、非常に重要な作業となります。
その後、ベルトコンベアで運ばれた豚は4本の足と頭が落とされ、シャックルというフックにかけられて次の工程へと移ります。
(足や頭は別のコンベアで運ばれ、それぞれに加工されます。)
次に、尻尾の切除と内臓を取り出す工程です。
この時に肛門を切り取り、腸の内容物が周りに付かないように処理をします。
取り出した内臓は部位ごとに検査をし、問題がなければ市場へと運ばれていきます。
この時に印象だったのが、内臓が全部繋がっていたこと。
今思えば当たり前のことですが、いかに普段お肉を部位ごとでしか見ていないかがわかる瞬間でした。
その後、皮と肉の間にナイフを入れて少し皮を剥がし、残りはローラー状の機械でつるんと剥がします。
芝浦と場で解体された牛と豚の皮は、それぞれ原皮という、加工前の皮として革製品を扱う業者や食品業者が買取ります。
この時、皮に穴が空くと市場価値が下がる為、薄く、穴を空けずに皮を剝がせるようになるまでが大変なんだそうです。
こうして頭、足、内臓、皮の作業工程が終わると、最後に背骨で豚を半分に切る背割りという工程に入ります。
小さな豚の場合はこれを機械で行ますが、大きくなると豚にも背骨の曲がり方などの個性がある為、巨大なチェーンソーで手作業で行います。
こうして背割りをして半分になったお肉を枝肉といいます。
この枝肉が競りにかけられ、市場に出回るのです。

牛肉のと畜解体
次に牛のと畜解体ラインを見学します。
牛の場合は一頭あたりの個体が大きい為、工程が少し大掛かりになります。
まず検査から洗浄・けい留所までの流れは豚と同じです。
しかし、その後の放血の工程が少し異なります。
牛の場合はと畜銃という、細い鉄の棒が高速で出る道具で、眉間を撃って気絶させます。
そこで倒れた牛はシューターで下の作業場に滑り落ち、暴れないように電流を流しながらけい動脈を切り、放血をします。
豚より体が大きい分、血の量も多く見えます。
この時、フックにかけると同時に皮一枚を残して頭を落とします。
さらに食道を縛って内容物が出ないようにし、ラインへ。
牛の場合はBSE(狂牛病)の問題以降、舌(タン)を残して頭は焼却処分することになっています。
それからの作業は基本的に豚と近く、足や角を落とし、内臓を取り出して、皮を剥ぎます。
豚よりずっと体が大きいので、内臓の量や皮を剝ぐ面積の広さに終始圧倒されてしまいました。
そしてすごかったのが背割りです。
先ほど述べたように、背割りは背骨の中心で切らないと価値が下がってしまいますが、牛は体が大きく背骨にも個体差がある為、全て職員さんがチェーンソーで行います。
人の倍以上の大きさの牛の真ん中をチェーンソーの刃が通り、向こう側に体格の良い職員さんのシルエットが浮かび上がる様は壮観でした。
こうして牛も枝肉となり、最後に洗浄・ランク付けが行われ、競りを経て市場に出回ります。
所要時間約2時間、と畜解体の見学が終了しました。

現場を見た感想
こうして職員さんの案内のもと、一通りのと畜解体の作業現場を見学して感じたことは、仕事の鮮やかさでした。
正直なところ、見学する前は「これを見たらお肉を食べられなくなるんじゃないか」と思っていました。
いわゆる「グロい」ものを見学することになるのでは、という恐怖があったのです。
作業現場では、もちろん血が跳ねてきたり、足元の側溝を血や脂が混ざった水が流れていったりもします。
しかし、作業の一つ一つはお肉の品質や衛生面を考慮した、迅速で洗練されたもので、カッコ良いとすら思えたのです。
そして、この感覚は何かに似ているなあと考えてみたら、マグロの解体ショーや魚の活け造りでした。
洗練された技術が、次々に生き物を食材に変えていくその様子は、私には「殺している」という表現がふさわしいとは思えませんでした。
魚と牛や豚の間にある差は、体の大きさなのか、血なのか、体温なのか、毛皮なのかはわかりません。
しかし、この作業工程を見て、と畜解体の仕事が差別されることが、やはり私には理解できませんでした。
そもそもいつ牛と豚は死んだのか、それすら判断がつかないほど仕事は鮮やかで、脂や皮も無駄なく利用する使い道があります。
そして何より、このお仕事が理由の全ては必要とする人間がいるからです。
そう考えると、やはりおかしい。
私の中にはと畜解体作業への感動と、今なお残る差別への不可解さの二つが残ったのです。
vol.3へつづく