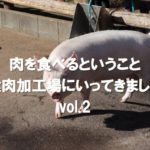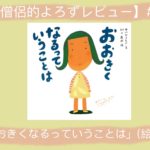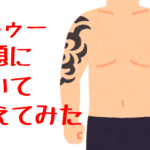スポンサードリンク
普段の食卓から、お祝いや景気付けなど、私たちの生活に欠かせない存在となっているお肉。
しかし野菜や果物、魚と違って、ほとんどの人が加工の過程を見ていない食物でもあります。
そこでこのコラムでは、実際に芝浦と場の食肉加工見学に行って目にしたもの・学んだことから、肉を食べるということについて考えてきました。
vol.1では、食肉加工という職業に向けられてきた差別の歴史と現状について触れました。
vol.2では、実際に見学した食肉加工の作業工程をご紹介。
と畜解体作業の無駄のなさと、「美味しさ」を追求して磨かれてきた技術の鮮やかさに驚かされました。
そして今回は、見学を終えた後の意見交換会でのお話です。
この日、私はその後の活動に大きく関わる経験をすることになります。

Contents
意見交換会にて
獣魂碑の存在と動物の魂
工場の見学が終わると、昼休みを挟んで意見交換会が行われました。
vol.1の意見交換会でもお世話になった高城さんが、工場でのお仕事を終えて再び時間をとってくださいました。
これは2017年に初めて見学に行った時の意見交換会での出来事です。
こちらからの質問にお答えいただく中で、話は工場敷地内の獣魂碑の話になります。
と場には獣魂碑と言われるど動物の供養碑があり、一年に一回僧侶が来て供養を行うことが多いのだそうです。
それに対して高城さんはおっしゃいます。
「私はあれはいらないと思うんです。なぜ食べる為に解体した動物の慰霊をするんですかね?そういう信仰がある人だけで勝手にやればいいんですよ。」
この言葉は、事前研修の際におっしゃっていた「私たちは牛や豚がかわいそうだなんて思っていません」という言葉と似た響きがありました。
日本で科学が発達する以前は、天災や疫病・飢饉というものは死霊の怨念によるものだとされてきました。
菅原道真を天神として祀るのも、戦国時代に多くの寺院が建立されたのも、怨念への恐れがあったからです。
慰霊碑や供養塔が現代で果たしている役割は、仏教本来の供養よりも霊を鎮めることにあるように思います。
高城さんははっきりと言葉にされませんでしたが、加工場内に獣魂碑があるということは、ここで怨念が生まれているということを意味し、と畜解体の作業が「悪いこと」であると言っていることになってしまうのでは、という懸念があったのかもしれません。
魚をいけすから出して捌く料亭や居酒屋さんに魚魂碑はありません。
木を伐採する山に木魂碑はありません。
なのになぜ食肉加工場には獣魂碑を置く必要があるんだ。
高城さんにはそんな納得のいかない思いをお持ちだったのかもしれません。
もちろん職員さん全員が獣魂碑を不要と思っているわけではありません。
ただ、第三者が「ここで動物が…」と思って手を合わせるだけでも、傷つく人がいるという事実が、そこにあるのです。
そしてそのと畜解体は、趣味や遊びではなく、求められて行う仕事であるということを忘れてはいけないのだと思います。

若い職員さんの言葉
意見交換会で、30代の若い職員さんが同席してくださいました。
交換会の途中では多くを語らなかった職員さんが、終了後私に声をかけてくださいました。
「すいません、なんでご飯を食べる前に手を合わせるんですか?申し訳ないからですか?娘が幼稚園で覚えてきて戸惑ってしまって。」
普段であれば「いただく命に手を合わせることで〜」とありきたりでも説明がつきます。
しかし、高城さんのお話を聞き、職員さんの様々な思いを知った後では、何を言っても自分が逃げているようにしか感じられず、私はその時自分がした説明もよく覚えていません。
すると、その職員さんが、その仕事に就いて経験したことをお話ししてくださいました。
聞けば、婚約者の身内が自分の職業を知った途端に猛反対をして、破談になってしまったことがあったそうです。
そして最後に一言私にこうおっしゃいました。
「牛を殺している人間と話すのは初めてですか?」
私の頭には色んな言葉が駆け巡りました。
あの作業を見て私は「殺している」とは思わなかったということ、本当に牛や豚が死ぬかどうかは消費者がどう扱うかにかかっているのではないかということ。
しかし、どんなに言葉を尽くそうが、当時の私にはその職員さんの悲しみや怒りを癒すことはできないと思いました。
それほどに、「牛を殺している人間と話すのは初めてですか?」という一言は様々な感情を帯びて私に投げかけられたのです。

と場見学を終えて
初めてのと場見学は、こうして自分の力不足と、視野の狭さと、想像力のなさ、多くの至らなさを痛感して幕を閉じました。
私は永平寺で「食べる」ということを根本的に見つめ直すことが出来たと思って帰ってきました。
しかし実際は、その食を巡って理不尽な辛さを味わっている方がいて、私はそんな方にかける言葉も見つかりませんでした。
また見学の中で、職員さんは口々に「みなさんが禁じている殺生を我々をしているのかもしれませんが…」とおっしゃていました。
その時、自分が何の疑いもなく触れて来た不殺生戒というものが、真面目に仕事をしている人に負い目や後ろめたさを抱かせることもあると気づかされました。
私はそれまで、食と向き合ってきたつもりでいましたが、人間の「食べる」という行動の本質に目を向けていなかったのです。
食べるとは一体どういことなのか。
不殺生と言いながら生命を取り込むという矛盾。
仏教はこれとどう向き合ってきたのか。
私はこの、食肉加工場の見学を通して「食と不殺生」について考えるようになり、これが現在の禅活の活動にも繋がっています。
次回からは、「肉を食べるということ〜肉食と殺生〜」というタイトルで、インド・中国・日本という仏教が辿ったルートで仏教が肉食をどう捉えたかを考えてみたいと思います。
まずは芝浦と場の高城さん、そして案内をしてくださった職員さん、見学をお許しいただいた職員さんに心よりの感謝を申し上げます。
「肉を食べるということ〜肉食と殺生〜」へつづく