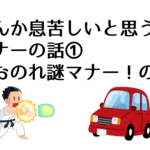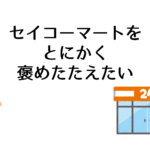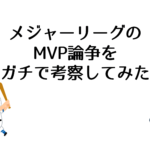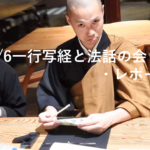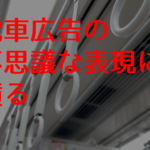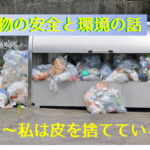スポンサードリンク
群雄割拠の大相撲3月場所。
今場所も、見ごたえのある相撲が多い白熱した展開となりました。
千秋楽までもつれ込んだ優勝争いは、膝の大けがと病気からの見事な復活を成し遂げた照ノ富士関が貴景勝関を破り、
自身の大関昇進に花を添える形で賜杯を手にしました。
本記事を書いている久保田イチオシの翔猿関も、内容の濃い相撲で2ケタの勝ち星を挙げ、兄の英乃海関ともども来場所の躍進に期待がかかるところです。
もはや恒例となりつつある、趣味全開の相撲ネタ。
今回は横綱鶴竜関の引退表明について思うところを述べていきます。
Contents
横綱の引き際
私は今回の鶴竜関の引退がとにかく残念でなりません。
というのは、土俵の上では神に等しい存在とされる横綱の引き際としては、あまりに寂しいものに感じられてしまったからです。
何場所も休場が連続していたとはいえ、稽古では新進気鋭の若手を圧倒するなど、「ケガさえ治れば、まだまだやれるぞ!」という意気を見せていた鶴竜関。
ただ年齢が年齢だけに、そろそろ引き際を考えなければならない時期であったのは事実でしょう。
しかし今回の場所中の電撃的な引退が、7年間にわたり横綱をつとめあげた鶴竜関にとって相応しいものであるとはなかなか思えないのです。
昨年逝去された元横綱・千代の富士の九重親方の引き際は、それは見事なものだったと言われています。
自らの状態を見極め、貴乃花はじめ次代を担う力士たちの台頭に合わせて潔く身を引いた千代の富士関。
時の運とは言いますが、鶴竜関にはそのようなタイミングがあったでしょうか?
いち相撲ファンとして、できることなら納得いくまで相撲を取ってもらって、しかるべきタイミングで華々しく後進に道を譲ってほしい、そのように考えていました。
今回、鶴竜関が引退を決断された背景には、ご自身のケガを発端とする様々な要因があったことと思います。
なかなか良くならないケガ、休場によって高まる不満の声、横綱としての責任。
引退後の報道では、鶴竜関が「責任感が強く、まじめで、兄弟子に対する敬意も欠かさず、後進の育成にも親身に取り組んできた人格者」であることが繰り返し報道されていました。
引退に際するインタビューで語られた「少しずつ気持ちが切れて、中途半端な気持ちでは土俵に上がれない」という言葉には、鶴竜関の忸怩たる思いが込められているように思えました。
まだやれたのでは……というのはファンのひいき目かもしれません。
今後は、年寄「鶴竜」として後進の指導に当たられる鶴竜関。
親方となった鶴竜関の育てた力士が活躍するのを期待せずにはいられません。
横綱への敬意と報道の是非
ところで、今回、鶴竜関の引退に関する報道を見ていて思ったのは、
「外野がとやかく言い過ぎではなかったか?」
ということです。
強い横綱に対して、他の関取たちが一所懸命にぶつかっていく姿は大相撲の醍醐味です。
それが見られないのは残念ですし、休場が続く横綱に対して、不満の声が上がるのも当然のことだろうと思います。
横綱審議委員会が出した「注意」決議には、そうした不満の声を重く見て、という背景もあることでしょう。
しかし、本意ならず休場のやむなきに至っている横綱に対し、さも「給料泥棒である」かのような言説が繰り返されるのはいかがなものかと思います。
先にも書きましたが、神事たる大相撲における横綱は神にも等しい別格の存在。
雑誌のゴシップ記事やスポーツ新聞の記事などには、横綱への敬意に欠ける言説があまりにも多いように感じます。
勿論、はた目から見て何らかの問題があると思えるからそうした記事が生まれるのでしょうが、
引退した横綱の今後について何の責任も持たないメディアが、
尊重され、敬われるべき存在である横綱をさんざんにこき下ろしているのは、見ていて気分の良いものではありません。

大相撲とケガ
大相撲はとにかくケガの多い競技です。
年間90日(これだけでもおかしいと思う)の取り組みに加え、日々の稽古、地方巡業というハードスケジュール。
さらには激しくぶつかり合う力士同士が大型化していることも、ケガを多くする要因と言われています。
大相撲で長く活躍する力士で、ケガと無縁という人はほとんどいないような状況です。
公傷制度がなくなって以来、横綱・大関以下の力士はひと場所でも休めば番付が大きく下がってしまうため、多少のケガであれば無理をして出場します。(今場所も、親指の脱臼と肋骨の骨折を抱えながら土俵に上がっていた幕内力士が居ました)
一方で横綱の責任を重く感じ、無理をして出場した結果、ケガを悪化させ、引退を近づけた横綱も居ます。
このような状況をこそ改善すべきではないでしょうか。
今場所の照ノ富士関のように、ケガと戦いながら相撲を取る姿には、確かに感動を禁じ得ません。
しかし前途有望な力士がケガをして番付を下げ、さらに無理をしてしまうような状況は果たして健全と言えるでしょうか。
そんな中、横綱だけが休場しても番付を下げずに済む、というのは確かに不公平であるかもしれません。
そもそも「ケガに泣く」力士が多いのに、根本的な解決策を取らず、あまつさえ「ケガをした方が悪い」というような今の風潮には、どうしても賛同しかねるのです。

特殊な世界「大相撲」と現代社会
私が強く思うのは、ケガに限らず大相撲の様々な制度が、今の時代にあって本当に適切なものなのかということです。
女人禁制、公傷制度、幕下以下の力士の給料、相撲茶屋へのチケット委託問題、タニマチとの付き合い方、年寄株問題など様々な問題が思い当たります。
現代の価値観から判断すれば、時代錯誤とも取れるような制度が未だにまかり通っているのが大相撲の世界であるように私は感じます。
もちろん相撲が日本の国技であるという性質上、変えてはならない部分も多くあると思います。
私も「現代の価値観に照らして、おかしい部分はすべて変えてしまえ」と言っているわけではありません。
一般的な考えだけではすべてを理解しきることができないのも、大相撲の「勝負の世界」なのでしょう。
しかし「伝統だから」「変えない」というだけでは、もはや通用しない時期にも来ていると思います。
「伝統」に学びながら、少しずつ「変化」していく姿勢が必要なのではないでしょうか。
日本相撲協会の運営はじめ、
個々の担い手である力士たちや、親方衆、
そして横綱の格と品位を担保する横審。
それぞれの意識やそのシステムを、少しずつでも更新すべき時だと、私は感じています。
特に横審については、特殊な世界である大相撲と一般社会の仲立ちとして、他では果たすことのできない役割を担うことができるのではないでしょうか。
横綱に対して「上から物申す」ではなく、世論と横綱の意志のバランスを取りながら横綱の格と品位を保っていく、そのように変わっていってほしいと思います。
さて今回は趣味に任せて、好き勝手書いてしまいました。
あくまでいちファンの遠吠えですので、どうか笑ってお許しください。
事実誤認があれば訂正します。教えてください。
それでは最後に。
鶴竜関、お疲れさまでした!
そして、本場所を戦った力士の皆様、熱い取り組みをありがとうございました!