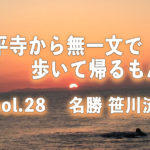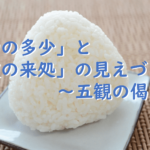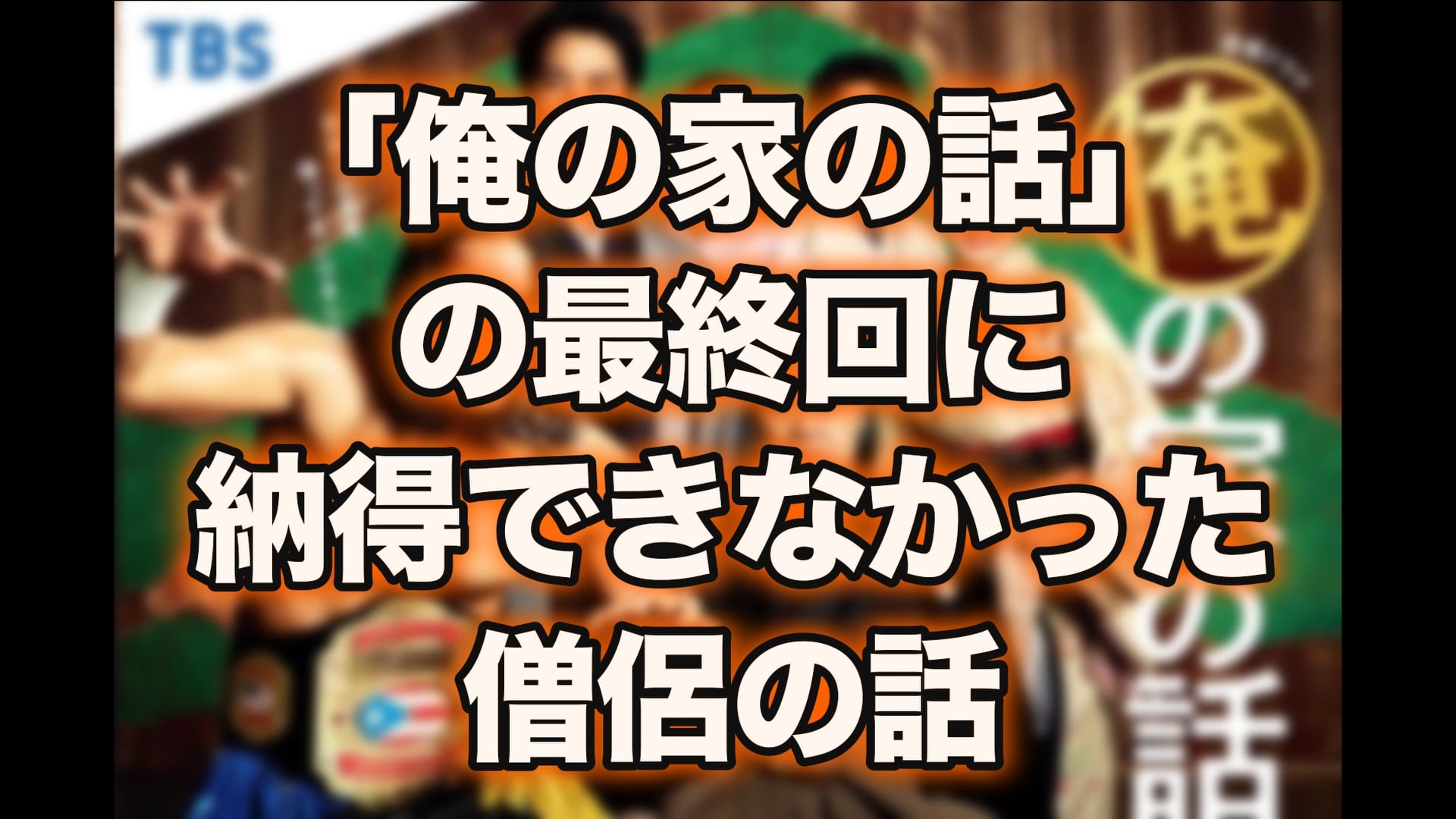
スポンサードリンク
昨年末くらいから、TVerを利用するようになった私。
TVerは簡単に言うと、テレビ番組を放送後一定期間視聴ができる、無料のオンデマンド配信サービスです。
最近はテレビ番組をリアルタイムで観ることがなくなり、観たかったものがいつの間にか終わっていた、ということの多かった私には非常にありがたいサービスで、よく利用しています。
そんなTVerでよく観るのはバラエティ番組が主だったのですが、この3ヶ月は久しぶりに毎週観たいと思うドラマ番組に出会いました。
それが、早くも名作と呼ばれつつある、「俺の家の話」です。
コメディでありながら、非常に人の深いところに触れた、この作品に私も夢中になってしまいました。
今回はそんな夢中になったドラマ番組が、最後の最後に納得できなくなってしまった僧侶の感想をお話します。
Contents
作品のあらすじ
この作品は脚本・宮藤官九郎、主演・長瀬智也という、ゴールデンコンビが手を組んだ作品です。
「IWGP(池袋ウエストゲートパーク)」は当時の若者たち絶大な影響を与え、「タイガー&ドラゴン」も大きな話題となりました。
そんなお二人が組んだこの作品のストーリーはこんな感じ。
あらすじ
能の一大流派、観山流を代々受け継ぐ観山家に生まれた主人公・観山寿一(長瀬智也)。
父・観山寿三郎(西田敏之)は観山流宗家にして人間国宝。
そして幼少期から寿一に能を教え込みますが、その厳格さ故に寿一は反発、高校生の時に家を出てしまいます。
そんな寿一が就いた職業は、プロレスラーでした。
人気レスラーとして活躍した時期を経るも、42歳という年齢で体力ともに人気は低迷し、決して順調とは言えない状態にあった寿一。
そんな時、父・寿三郎が倒れたと知らせが入り、病院に駆けつけて数十年ぶりの再会を果たします。
寿三郎は一命を取り留めるも、後遺症から介護が必要になります。
そこで、寿一はプロレスに区切りをつけ、寿三郎の介護を引き受け、さらに観山流跡を継ぐことを決心します。
自分がしてもらえなかった「親らしいこと」を逆にしてやろうと、慣れない介護と、そして離れていた能の稽古の日々が始まります。
そこに、余生を自由に生きると宣言した寿三郎の婚約者の登場や、子どもたちの知らない様々な過去が明らかになるなど、波乱の展開を迎えます。

老いとは?死とは?
この作品はコミカルな中にも、年老いた父に対する子どもたちの葛藤と、自分自身が死を見据えている父の、非常に生々しい心情が描かれます。
物語の序盤、あれほどに厳しかった父が、お風呂やお手洗いに自力で行けなくなったことに対して、寿一が悔しさとも怒りともとつかない感情を爆発させたのは、決してフィクションの世界だけのことではないでしょう。
一方で、人間国宝という自負を持ったまま、身体機能の低下だけでなく、認知症の症状も出るようになった寿三郎も、静かにその苦しみと向き合っていました。
そんな寿三郎が口にした「自分の人生のしまい方が、広げた風呂敷の畳み方がわからなくなった」という言葉は非常に印象的でした。
死を覚悟するも一命を取り止め、出来ないことは多くとも生きているという、死が思い通りにならないことへの苦しみが表現されていました。
人間の老いや死というものは、決して本人だけのものではないということが改めて分かる、そんなストーリーに私は引き込まれました。

最終回の残念さ(以下、ネタバレを含みます。)
最終回は、寿一がいよいよ能の舞台に立つというところから始まります。
ところが、寿一は寿三郎以外との会話が成立せず、視聴者は違和感を覚えます。
そして本番を迎え、寿三郎が寿一の姿を探していると、実はその数ヶ月前に寿一が亡くなっていたことが告げられます。
もちろん、その死は隠されていたのではなく、寿三郎はその事実を受け止めることができず、そこに認知症が重なったことで、ずっと周りには見えていない寿一と会話をしていたのです。
この展開にはこれまでのエピソードに伏線が張られていたらしく、その回収が素晴らしいと話題になりました。
私もそれはいいと思います。
しかし、その後がどうにも納得できない、いや、自分の立場から観ると辛すぎる展開だったのです。
最終的に寿三郎は寿一と最後の言葉を交わし、その死を受け止めることができます。
しかし、観山家には仏壇があるにもかかわらず、おそらく四十九日が過ぎてもご遺骨と位牌を祭壇に飾ったままにしてあります。
そして、一家揃って食事をする時には寿一の「いただきます!」という声が欠かせなかったことから、寿一が生前撮った「いただきます!」と言う動画を再生し、観山家は食事を始めます。
私が納得できないのは、細かい儀礼的な部分ではありません。
観山家がずっと、「生きている寿一」を頼って生きているということです。
このブログやYouTubeで、仏教は故人の肉体ではなく教えを頼りに生きていく道を説いているというお話をしてきました。
それは、遺された人にとって、大切な人の死をただの喪失にしないための道でもあります。
しかし、このドラマで描かれた寿一の死後の様子というのは、「生きている頃と変わらず、寿一はここにいます」というものです。
人間の感情としては理解できます。
生きていた頃と同じようにご飯を用意し、話しかけ、動画によって声も聞こえる。
その様子が世間に感動を与えた理由も、わからなくはありません。
ただ、葬儀や供養によって亡くなった方と関係を新たに結び直さないことで、いつかその喪失感に押し潰されてしまうのではないだろうかと、私は心配でならないのです。
観山寿一という人が残してくれた言葉や、その生き方に習って、遺された人がそれぞれに生きようとする。
そして「いただきます!」という掛け声を、寿一の息子である秀生が受け継いで終わる、そんなエンディングであってほしかったと、つい思ってしまいます。
この作品が、ずっと老いや死というものを扱ってきただけに、少なからず仏教的なシンパシーを感じたからこそ、私はそう感じたのかもしれません。

まとめ
結局、ここに書いたことは一視聴者の、しかも割と深く引き込まれてしまったが故に感じたことなのだと思います。
この作品のテーマは素晴らしかったと思うし、プロレスラーがそのまま実名で出るところや、能のお話とその回のテーマがリンクするところはクドカン作品の過去のオマージュとも取れて、思わずニヤリとしてしまいました。
「タイガー&ドラゴン」然り、古典芸能をドラマにするに当たって、専門家に取材をし稽古をする大変さは想像もつきません。
ただ、そこが丁寧なんだから葬儀や供養ももう少し丁寧でよかったのでは?と思ってしまうわがままなファンが私なのです。
ともあれ、長瀬さんはこれで舞台からは引退し裏方に回るとのことですので、そうしたところともリンクした、素晴らしい作品でした。
これが、「俺の家の話」をみた私の話です。