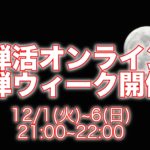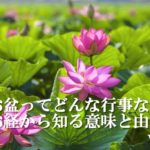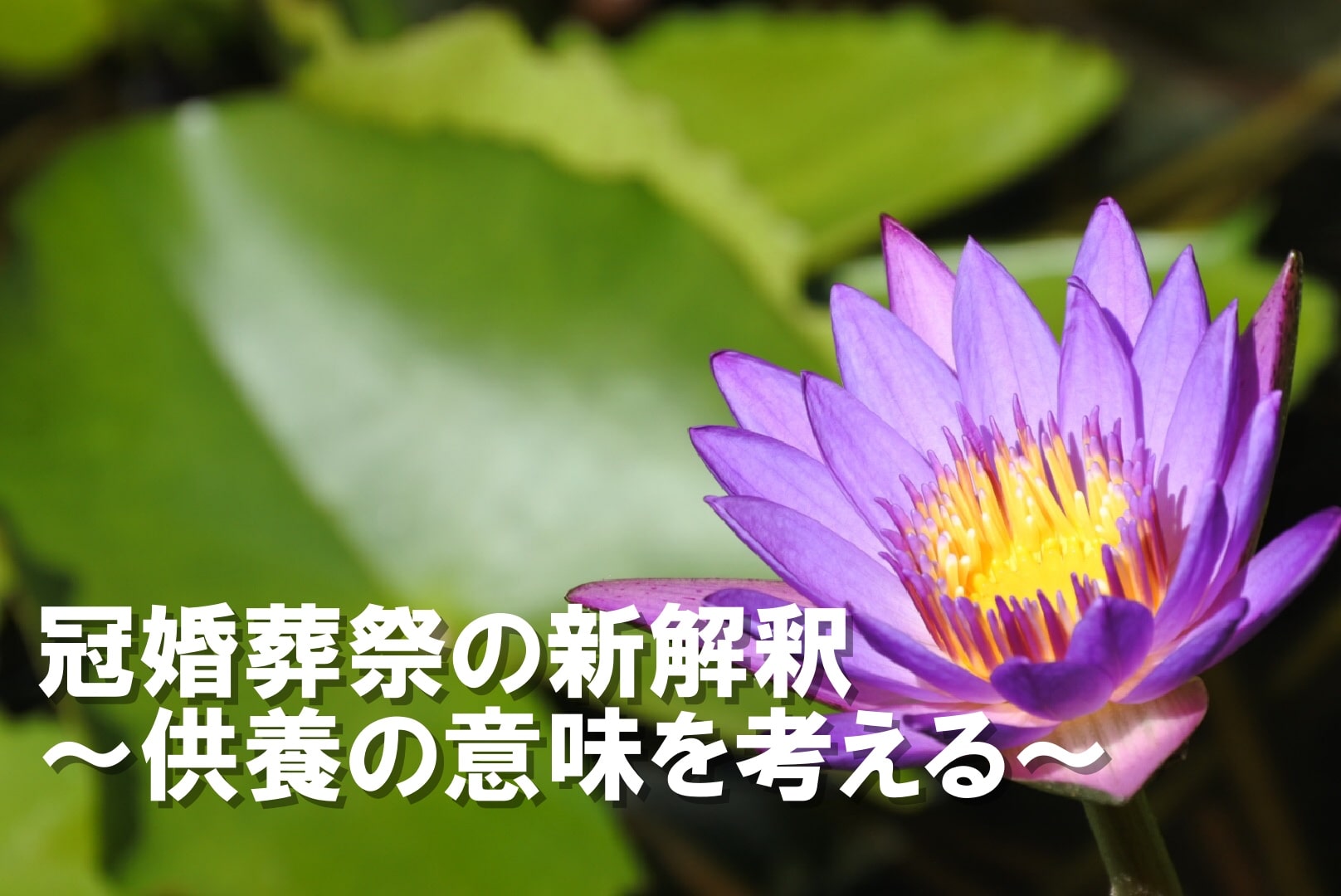
スポンサードリンク
現代では「結婚式」と「お葬式」を合わせた名称として使われる「冠婚葬祭」という言葉。
前回は「冠婚」と「葬祭」ではなく「冠」「婚」「葬」「祭」それぞれに意味があることをお話ししました。
しかし、これを知っただけではただのマメ知識。
今回はそこから一歩踏み込んで、「冠婚葬祭」を人生とリンクさせ、そこにある供養の心を掘り下げてみましょう。
Contents
人の節目に込められた想い
節目いろいろ
日本に残る風習には、人の一生を細かく分けた「節目」がたくさんあります。
七五三、成人式、還暦、米寿、白寿…。
もっと細かくすればお宮参りやお食い初めなどなど、実に多くの節目に沿った儀礼が存在しています。
少し話が逸れますが、人生の区分で言えば「青春」もそうですね。
儒教では東西南北をそれぞれ司る四神と季節とリンクさせて、人の一生を次のように区切りました。
東を守る青龍と春で青春、これは春の若葉が芽吹くように、生まれてから青年期にあたる20代前半までの時期。
続いて南の朱雀と夏で朱夏、これは夏に力強く葉が茂るような、気力や体力が最も盛んな壮年期で、だいたい50代前半までの時期。
そして西の白虎と秋で白秋、ここまで生命力に満ちていた葉は赤く染まり、落ち着きを見せ始める60代前半の時期のこと。
最後に玄武と冬で玄冬、冬にかけて葉が散っていき、その葉が来年の養分となるように後世に想いを託す時期を迎え、人は人生を終えていきます。
昔の中国で生まれた区分なので、平均寿命が伸びた現代ではこの通りではありませんが、古くからこうした人生の在り様が語られていたんですね。

節目が果たした意味
さて、中国から伝わったものも含め、昔の人々はなぜ人間の一生にはたくさんの節目をつけたのでしょうか。
答えはいたってシンプルです。
それは、生きていくことが容易ではなかったから。
食糧に恵まれず、医療も発達していなかった時代、特に子どもが生き延びるということはとても大変なことでした。
仮に食糧が足りていても、戦や疫病が訪れれば、まず失われるのは幼い命です。
小さな命というのは、現代よりもずっと脆くて弱いものでした。
では、当時の人々はそんな子ども命の弱さや理不尽さをどのように受け止めたのでしょうか。
その答えのヒントはお宮参りや七五三という風習にあります。
3歳、5歳、7歳という年齢に神社に挨拶に行き、感謝をするその理由。
それは、子どもの命というのは神様からの一時的な預かり物と考えたからです。
7歳まで育ったら、その子が自分の元にいることを神様が認めてくれたということへの挨拶をするのというのが、7歳のお宮参りです。
そうすることで、逆に幼くして子を亡くなってしまったら「神様が認めてくれなかった」と、なんとか自分を納得させる知恵が、七五三という習慣の背景にはあったのです。
お七夜(7日)、お宮参り(1ヶ月)、お食い初め(100日)、七五三(3歳・5歳・7歳)、元服(15歳)など、ここまで細かく設けられた節目と風習には「なんとかここまで育ってくれた」という現代以上の歓びがあったのです。

冠婚葬祭が人生に与える意味
それでは、冠婚葬祭は人生においてどのような意味があるのでしょうか。
冠婚葬祭は基本的には人生の節目となる儀礼のことですが、私の師匠はよく人生の4つの時期として考え、時計に例えて表します。

表にしてみるとこんな感じ。
このように表すと、右半分の冠と婚が生きている期間、左半分の葬と祭が死んでからの期間となります。
人は生まれてから成人する頃までの冠の時期は親に育てられ、婚の時期には子供や後進を育てる側になります。
そして死と共に迎えるのが葬と祭なのですが、これは冠と婚に比べてイメージがしにくいはずなので、詳しくみていきましょう。
生と死の儀礼
まずはじめに、さきほどの冠・婚・葬・祭、それぞれの時期に行われる儀礼や行事を整理してみました。

特に注目していただきたいのが、冠と葬。
生まれてから一人前になるまでが冠、亡くなってから33回忌までが葬という期間。
そこでそれぞれ行われる儀礼や行事が、非常に似ている、というかほとんど一致しているんです。
人が生まれ、一週間経つとお七夜があります。
一方、亡くなって一週間では初七日が行われます。
生まれて100日でお食い初め。
亡くなって100日は百箇日。
七五三がでお宮参りに行くのは3、5、7歳。
法事も元々は5回忌も存在していたそうなので、3、5、7年。
生きている人が32歳になる頃には働き盛りで責任を背負い、仏様も三十三回忌で忌明け、子孫を導く仏様として祀られる存在になっていきます。
では、誕生と死という正反対の出来事に対して、ほとんど同じ日数や年数で儀礼を行うのはなぜでしょうか?
そこには現代に通ずる供養の心があったのです。
葬の時期と供養の在り方
この理由を考えると、亡くなってから32年間、葬の時期に行われる法事や供養の意味が見えてきます。
お葬式で行われるのは、個人を出家させて仏様にする儀式です。
では仏様とは何かというと、私たちが悩み迷った時に導いてくれる存在のこと。
しかし人が亡くなると、残された人は哀しみや喪失感の中で、「その人がいないこと」に苦しめられ、お葬式という儀礼を行ったからといってすぐに「あの人は仏様になった」とは思えないでしょう。
意外かもしれませんが、これは人の誕生ともすごく似ていることなんです。
最近私の周りではお子さんが生まれて父親になった人が何人かいますが、みんな口を揃えて「生まれてすぐには実感が湧かなかった」と言っていました。
実は感情のベクトルが逆なだけで、人が誕生と死は、「新たな人間関係を結ぶ」という点では共通しているのです。
仏様を育てる
そして人は、生まれるとこの世界に新たなの一員として周囲に育てられながら人生を歩み始めるように、亡くなるとまた新たに仏様として死後の人生を歩み始めます。
ところが、人が生まれても亡くなっても、その直後というのはその新たな関係性への実感がなく、心における存在としては非常に不安定なものです。
そこで先人たちは、冠と葬の時期にはその成長と関係の構築を一つ一つ確認するように、細かな儀礼を行ったのではないでしょうか。
生まれた人が七五三を経て周囲に馴染んでいくように、亡くなった人は三・(五)・七回忌を経て残された人の仏様として馴染んでいきます。
ちなみに、七回忌は休広忌ともいい、休広とは安定を意味することからも、7年という節目には大きな意味があったことがわかります。
一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌…と供養を重ねていき、三十三回忌の忌明けまでは32年間。
人生の様々な出来事のなかで「あの人だったらどうしたかなあ、何て言うかなあ」と故人思いを馳せるうちに時間をかけて人生を導いてくれる存在となっていくはずです。
こうして冠の時期と対比させてみると、法事をはじめとする供養とは、仏様を育てる儀礼なのではないか、そう思えてくるのです。
僧侶が葬儀や法事でお経を唱えていたら故人が仏様になる、というわけではありません。
どれだけ僧侶が一生懸命葬儀や法事を勤めるよりも、残された一人一人の心の中で育てられることでようやく本当に仏様となっていくのです。
言ってしまえば僧侶はその「仏様を育てる」お手伝いをしている立場と言ってもいいかもしれません。
そして、そうした供養の期間を経て、立派に育った仏様が、私たちのご先祖様です。
ご先祖様は顔を見たことすらなくても、子孫を導き、守ってくれる存在としてお墓やお仏壇に祀られます。
こうして葬という期間を経て立派な仏様になって入っていくのが「祭」という時期なのです。

冠婚葬祭を生きる
ここまで読んでいただければ、冠婚葬祭がただの儀礼以上の意味を持っていることはおわかりいただけたはずです。
人は肉体を得て冠・婚という時期を生き、肉体を失ったら人の心を住処として葬・祭という時期を生きていきます。
現代で美化される「私の人生は私が決める」という言葉はとても力強くて良い言葉に聞こえますが、私たちの人生は常に他者との関わりの中で進み、死後はその他者によって生かされていくのです。
供養という在り方に様々な考え方や価値観がある現代社会だからこそ、冠婚葬祭という言葉の原点に立ち返り、その根底にある心を汲み取ってみてはいかがでしょうか。
難しく色々考えていたことが、スッと氷解してしまうかもしれません。