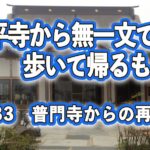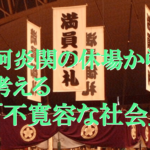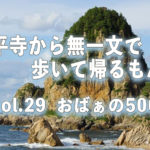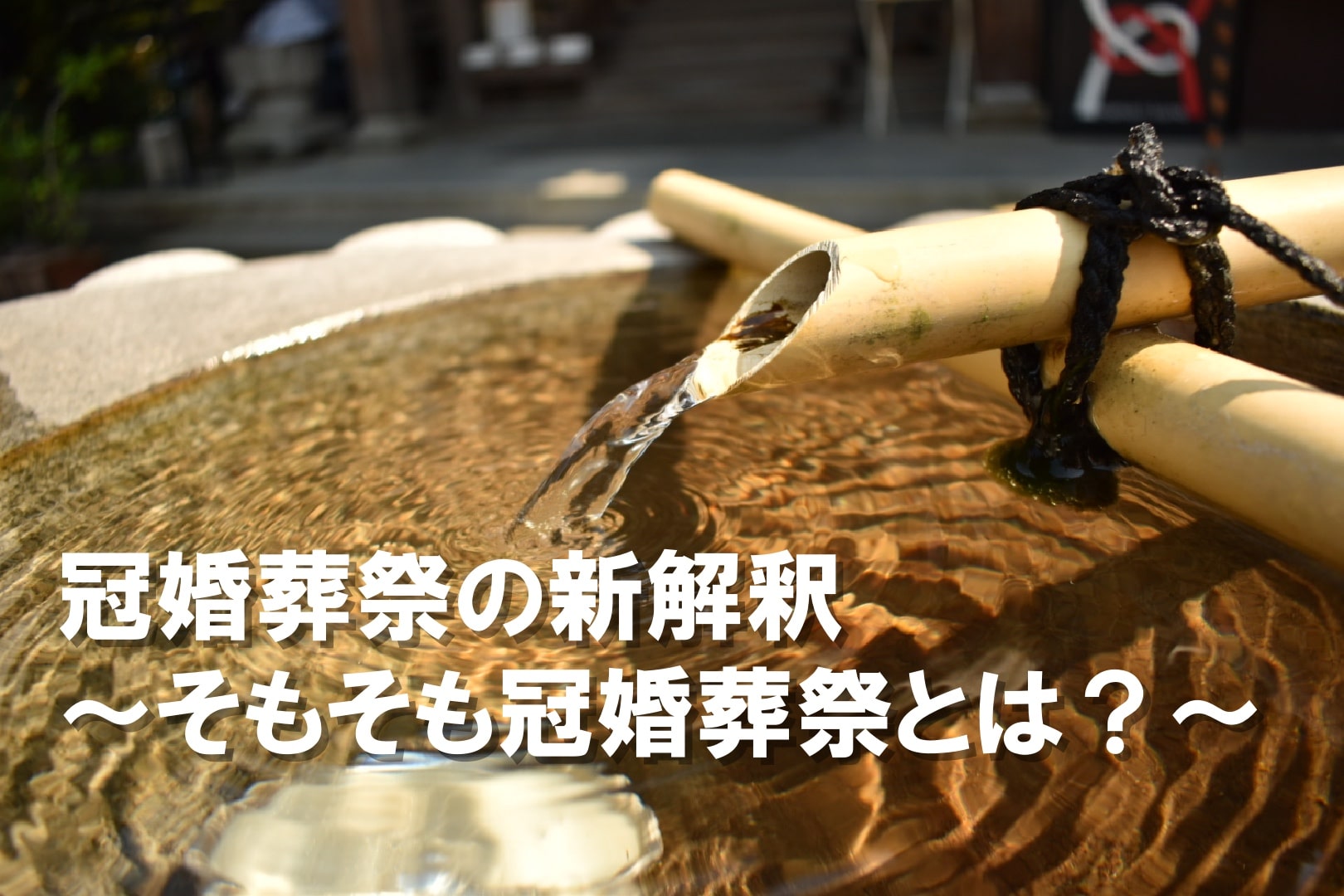
スポンサードリンク
今年28歳になる私西田。
この1〜2年で一気に増えたのが友人の結婚式。
すると私の立場上、人前でお話しをする機会に恵まれているためか、乾杯の音頭や友人代表の挨拶を務めさせていただくこともあったりします。
そこで気をつけるのが、結婚式のマナー。
使うべき言葉・使うべきでない言葉、良い振る舞い・悪い振る舞いなどが、当然ながら日頃の法事やお葬式とは異なるからです。
慣れない頃はスーツの色やご祝儀袋の用意の仕方など、一つ一つネットで調べながら準備をしていました。

こうした冠婚葬祭のマナーが難しく感じるのは、日常生活の様式とそうした場での様式がかけ離れてしまったせいでもあるのかもしれません。
どんなに形を変えたとしても、冠婚葬祭自体は日本という国の文化の中で何かしらの形で残っていくはずで、いずれは社会生活を送る誰もが関わらなくてはならないものです。
冠婚葬祭に携わることもある意味で大人になっていくことなのかもしれません。
…ところで、この冠婚葬祭という言葉の意味を、皆さんはご存知でしょうか?
結婚式とお葬式?
そう思いますよね。
実は冠・婚・葬・祭は全部別物です。
しかもそこには供養に関する大切な精神性が込められています。
今回は冠婚葬祭に関して、私の師匠が常々供養の場で申し上げていることを土台として、私なりの解釈でお話ししたいと思います。
Contents
冠婚葬祭の由来
中国に由来がある冠婚葬祭という言葉は、今申し上げた通り「冠婚」と「葬祭」ではなく「冠」「婚」「葬」「祭」と全て別々の意味を持っています。
まずはそれぞれの意味と内容に触れてみましょう。
冠
冠というのは、日本では奈良〜江戸時代頃まで行われていた、元服という通過儀礼のことを指します。
当時は15歳になると成人とみなされ、貴族は冠、武家は烏帽子といった被り物を授けられます。
この成人となると共に被り物を授ける風習は、中国で行われた冠礼という儀礼が日本に伝わったもの。
そしてこうした冠などの被り物を授けられることから、元服のことを「冠」というようになりました。

婚
婚は、字からもわかる通り結婚式のことです。
昔は今とは社会の在り方や価値観が異なり、結婚というのは必ずしも自由なものではない上、成人した男子が妻をめとり、子孫を残すことが「勤め」とされていました。
これは日本に限らず、インドや中国を含め、「長男が子孫を残す」ということの重要性は様々な思想から説かれています。

葬
葬も字の通りで、お葬式のことをさします。
ちなみにお葬式というのは通夜・葬儀、そこに告別式などを合わせた葬送儀礼の総称です。
中国では現在、冠婚喪祭というように「喪」という字を当てるそうで、人の喪失や、喪に服する儀式という意味では「葬」と大きな違いはありません。

祭
祭というのはお祭りのことです。
といっても、祭祀という言葉があるように、お祭りとは本来神様や仏様を祀る儀礼のことです。
祭るというのはどういうことかというと、日頃の生活の中で心の拠り所としている神仏に関係の深い日に、お供えをしたり、音楽やお経を捧げたりするなどの行為によって、感謝し讃えることと言ってよいでしょう。
夏祭りなどでは、ついつい露店やお神輿に心を奪われてしまいがちですが、神社でもお寺でも、お祭りというのはそこにおられる神様や仏様をお祭りしている儀礼に他ならなりません。
お祭りに参加する時などは、その神社やお寺でお祀りしている神仏について調べてみると良いかもしれませんね。

「知識」と「生き方」の違い
これで、冠婚葬祭という言葉には以上の4つの儀礼が含まれていることがわかりました。
正直な話、これだけならウィキペディアや葬儀会社さんのコラム、書籍などでいくらでも書いてあります。
なぜならこれは言葉の意味という、一つの知識に過ぎないからです。
私が尊敬する故・奈良康明老師は、仏教を学ぶ上で一番重要なことは「一人称であること」だとおっしゃいました。
たとえば、諸行無常という教えを知ったなら「なるほど、この世はみんな無常なのか」だけではなく「ああ、私は無常な存在なのか」と受け止めることが、「一人称であること」です。
少し調べればいくらでも情報を手に入れられる現代ですが、その情報を活かすことができるかどうかは別の話です。
「知ってる?冠婚葬祭って結婚と葬式じゃなくて冠と婚と葬と祭、全部違う意味があるんだって〜!」
という情報や知識で止まっては、結局人生を変えるような「生き方」にまでは至りません。
なぜこのような言葉ができたのか、その過程にはどんな思いがあったのか、そこに思いを巡らせ、自分自身に活かして初めて、その知識が意味を持つのです。
これは私たちの活動に直結する部分でもあります。
仏教には知識欲を満たすような意外性や人に話したくなる話題性のある教えもたくさんあります。
しかし、それを「知識」で終わらせず「生き方」に変換して伝えていくことが私たち布教活動を行う僧侶の役割だと思っています。
そこでこのコラムでは、もう一歩踏み込んで冠婚葬祭という言葉を自分の生き方に当てはめてみたらどうなるのかを考えてみましょう。
次回は「知識」を「生き方」に変換していきたいと思います。
つづく