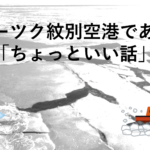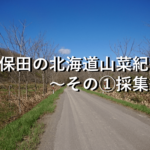スポンサードリンク
医療や技術がどれだけ発達し、経済的に豊かになっても無くならない人権問題。
以前、Black Lives Matter(ブラック・ライヴズ・マター)についての記事を掲載しましたが、それもこの世界が抱える問題の一つで、日本国内にすらまだまだ問題が存在しています。
そこで今回は、そもそも人権について学ぶのはなぜなのか、そしてその学習はどうあるべきなのかについて考えます。
Contents
曹洞宗と人権問題
曹洞宗は、日本の仏教教団の中でも、特に人権問題解消に力を入れている宗派です。
実はそれにはきっかけとなった出来事があります。
1979年、アメリカで開催された「世界宗教者平和会議」にて、当時の曹洞宗のトップが
「日本にはもう部落差別はない」
という旨の発言をしたことで、日本国内で糾弾を受けたのです。
この発言のどこに問題があるのかというと、日本では食肉加工などを含む一部の職業の人や出身の人に対して「穢多・非人」に代表されるような被差別身分を設け、社会的な差別を行ってきた歴史があります。
その歴史を遡れば、奈良時代に仏教が伝来したことが大きな転機であったともいえるでしょう。
私の連載「肉を食べるということ」(記事リンク)でも触れているように、その社会構造というのは、
「肉は食べるが、殺生はしたくない。それなら特定の人間にそれを背負ってもらって、消費の場ではセーフにしよう」という、一部の人間による非常に理不尽なものでした。
そうした社会構造は実はいまだに尾を引いていて、食肉加工場の見学に訪れた際には、最近になって送られてきた、それはひどい差別投書が展示されていました。
詳しくは記事をご覧ください。
つまり、現代にも部落差別や職業差別は残っていて、苦しんでいる人や差別と闘う人々がいる中での「日本に部落差別はない」という発言だったのです。
曹洞宗の人権問題への取組はこちらから詳しくご覧いただけます。

学習の在り方
そういった経緯があり、私たち曹洞宗の僧侶は定期的に人権学習を行っています。
その学習方法はケーススタディが多く、事例とその不適切な部分を学ぶというものが基本になります。
もちろんそういった学習の在り方は重要ですが、時々、疑問に思うことがあります。
それは、「こうすると人権問題になってしまうのでやらないようにしましょう」という、批判を浴びないための学習、いわゆる炎上対策に感じてしまうのです。
国籍や肌の色、身体的な特徴や職業など、日本国内だけでも様々な問題が点在しており、さらに世界に目を向ければその問題の量は膨大なものになります。
ではそれら全ての問題の最新の状況を追い、一つ一つの解決に取り組めるかというと、それは不可能だと思います。
実際に、Black Lives Matterについて調べたり考えたりすると、SNS等では「なぜウイグルの問題に触れないんだ!」という意見に遭遇することがあります。
もちろん、食肉加工業従事者や黒人差別の問題以外には興味がない、というわけではありません。
ただ、自分の歩んできた人生の中で、ど真ん中にくる問題は人それぞれに異なり、全てに同時進行で取り組むというのには無理があるのです。

人権学習に必要な前提
では、人権問題とどう向き合うべきなのか、どうしたら一人でも傷つく人を減らせるか、と考えた時、ヒントになりそうな出来事を思い出しました。
これは中学生の頃の記憶です。
当時の私は、なぜか「お寺に生まれた」ということを人から触れられることに、過剰に反応していました。
今は全くそんなことないのですが、当時はそれが「生まれを馬鹿にされている」と思えたのです。
坊主頭でおちゃらけることの多いキャラクターなのに、お寺いじりだけはNGという私を、友人たちはさぞかし不思議に思ったことでしょう。
しかし、当時の私にとってそれはとても傷つき、笑って許せない大問題であったことは確かです。
逆に、気づかなかっただけで、私が何気なく発した言葉や態度に傷付いた人もいたことでしょう。
こうした、境遇や立場の違う人は気づかない「痛み」があると知ることが、まず人権学習の前提として必要な気がするのです。

大坂なおみ選手に対する批判
先日、テニスプレイヤーの大坂なおみ選手が、アメリカで黒人男性が警察官から銃撃された事件を受ける事件を受け、試合を棄権するというアクションを起こしました。
ご自身が「黒人女性」である大坂選手にとって、この事件は決して他人事ではなく非常にショックの大きいものだったはずです。
— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) August 27, 2020
しかしこのアクションに対して、日本で起こったのは賛同だけではありませんでした。
SNSを中心に、一部の人々から「日本人として出場するんだから黒人差別の問題は関係ないだろう」という批判が起こったのです。
これは、他人の痛みを勝手に「それは痛くない」と決めつける行為といえるでしょう。
実は、この他人の痛みへの決めつけや想像力の欠如をなんとかすることが、人権問題解消の鍵になるのではないかと、私は思います。
痛みへの想像力
人権問題は、その問題がどのようにして生まれたかを理解すると同時に、それがどのように人を傷つけたのか、その「痛み」を知ることが重要になります。
その「痛み」に対する理解が欠け、怒られないための知識になると、「今は下手なことを言うと怒られますからねえ」という発言につながるのです。
この世界には、私が好きなパクチーが嫌いな人もいれば、逆に私が飲めない日本酒を美味しそうに飲む人もいます。
そのように、一つの物事をどう感じるかは千差万別なのが、人間です。
だから当然、自分にはわからない「痛み」もあります。
そこで他者の「痛み」を想像する力が、仏教の「慈悲」なのだと、私は思います。
全く同じ立場・境遇に立って、同じ気持ちになるということはできないかもしれません。
しかし、「パクチーが苦手な人は、私が日本酒を飲めないのと同じ気持ちなんだな」というように、自分が経験した痛みを、相手に置き換えて想像することで、可能な限り共有できるのではないでしょうか。
お釈迦様は、
「自分が暴力を受けたくないのと同じように、誰もが暴力を受けたくない。だから暴力はいけない」
と説かれました。
自分の経験した「痛み」を出発点として、他者の「痛み」に想像を働かせるという姿勢を養うことが、仏教徒としての人権学習の在り方の一つなのかもしれません。

最終的には、当事者意識
最後に、人権問題に関して最も重要なことは、当事者意識をもつことでしょう。
「私は全ての人を平等に見れるし、差別なんて絶対しない」と思うのは、非常に危険といえます。
なぜなら、過去に起こった人権問題が、「よ〜し、人権問題を起こすぞ〜」と思って起きたものではないからです。
人間は日々の生活の中で、自分の価値観や視点を形成していきます。
その価値観の中に含まれない、あるいは反するものに対する違和感から、差別意識は生まれます。
まずは、無意識のうちに自分の中に差別意識やその種があると、一人一人が自覚することから、仏教徒としての人権学習はスタートするのではないでしょうか。
それは仏道を歩む上で必要な自己反省と、なんら変わりません。
僧侶が人権についても学ぶのではなく、人権について学ぶことは仏道に違わないという姿勢が求められるのかもしれません。
そして、その姿勢を社会に広め、共有していくのが、布教教化と呼ばれる修行なのだと、私は思います。

まとめ
・人権問題には、理解できない「痛み」があるのは当然
・理解できないことは自分の問題と置き換えて考えることが必要
・「自分は差別などしない人間だ」と思わないことが重要