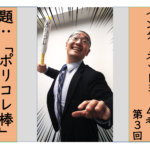スポンサードリンク
坐禅に関するいろんなことを未熟なりに考えて呟いているこちらの企画。
前回は坐禅の「調心」で勘違いしがちなことについて書きました。
今回は少し趣を変えて、だるまさんのお話をします。
Contents
そもそもダルマさんて?
まず、だるまさんはお坊さんだということはどれくらい知られているのでしょうか?
だるまさんはインドから中国にやってきて禅を伝えた方で、日本の禅宗にとっても超重要人物です。
私たち曹洞宗では菩提達摩大師、という風にお呼びしていますが、この方には様々な伝説があり、その人物像には多くの謎が残っています。

そんなだるまさんが、当時の中国の皇帝である梁の武帝と交わしたと言われる会話があります。
熱心な仏教信者であった武帝は、インドからやってきたというだるまさんにこう問います。
「私はこれまで多くの仏塔を建て、お経を翻訳させ、僧侶を保護してきた。この功徳はどれほどのものであろうか。」
褒められる気マンマンの武帝に対して、だるまさんが一言。
「無功徳。」
功徳なんてないと、バッサリ切り捨ててしまったのです。
実はこの武帝というのは、仏教に熱心になるあまり、国が傾くほど財をつぎ込み、最後はクーデターによって倒れた人。
最後は籠城し、その城では、生き残った兵士が死んだ兵士や馬の肉を食べるという、地獄のような有様。
この武帝とだるまさんのやりとりは、この最期を踏まえて作られた一つの伝説と言われていますが、仏教への信仰の在り方を戒めたお話として語り継がれています。
ダルマさんと坐禅
さてそんなだるまさんですが、日本ではお坊さんどいうより、あの丸い置物のほうがポピュラーで、手足がないものと思われていることがあります。
実はこれ、坐禅をしている姿なんです。
手足がなく見えるのは「被」という坐禅をする際の防寒具をかぶっているからです。
禅宗に伝わる物語でははだるまさんが雪の中で坐禅をしていたとされますし、インドからきただるまさんが被をかぶって坐禅をしていたという姿がとても印象的だったのかもしれません。
ダルマさんが起き上がる理由
さて、そこでもう一つ気になるのがだるまさんが「転ばない」ことの象徴になっていること。
実はこの丸いだるまさんは日本にしかありません。
福島県の会津若松地方にある起き上がり小法師のような原理で、倒しても起き上がるだるまさん。
実はこれも坐禅に由来があるのです。
坐禅というのは身と呼吸を調えることで心が調うものである、ということは以前お話した通りです。
体を左右に傾けないのは、悩みや不安に右往左往しないということ。
そして前にかかんだり後ろに仰け反らないのは、卑屈になったり傲慢になったりしないということです。
前後左右、このどれもが行き過ぎれば大きな失敗をしたり人を傷つけてしまうものです。
そうならないように支えてくれるのがお尻と足です。
坐蒲であれ椅子であれ、坐るということは大地に支えられるということでもあります。
大地というのは鉱物や植物や動物が積み重なってできたいわば「命の結晶」です。
いや、「死の結晶」と言った方が正しいかもしれません。
私たちは常に、足元にあるたくさんの死に支えられて生きています。
この「死」が植物や動物を育て、人間を生かしてくれています。
死というのは恐い、悲しいものではなく、そんな命の循環の一つです。
坐禅というのはそんな命の循環である死に根を張って生きていることを実感するものでもあります。
自分の命は、この皮膚の内側だけのものではなく、もっとずっと大きな循環の中で支えられて存在していると気づくことが、お釈迦様が気づき、だるまさんが中国に伝えた仏教の根幹です。
いろんなことに悩んだり苦しんだり、時には間違いも犯してしまうけれど、その土台に「支えられている自分」があることで、また起き上がることができるのです。

転んだっていい
仏教の教えで重要なことは、「転ばない方法」ではなく「起き上がる方法」です。
もちろん、転ばないに越したことはないからこそ、戒律があったり生活の作法があります。
しかし、転んだとしてもまた起き上がることこそが重要なのです。
現代では、少し調べればどんなことも無難にやり過ごせる方法を見つけることができます。
しかしそれによって、失敗することに不慣れになって、謝ったり、反省したり、今後に繋げるということが下手になってきてしまうことがあります。
転ぶこと自体が悪なら、だるまさんの形を三角錐にすればよかったのです。
ただし、三角錐は一度倒れたら自力で起き上がることはできません。
だるまさんが丸く作られているのは、命の循環の上に根を張って坐るという、そんな坐禅の精神が背景にあったのです。
そんな生き方ができたら、少し楽になるかもしれませんね。