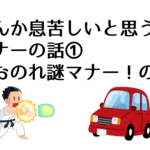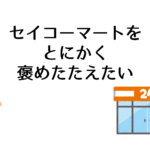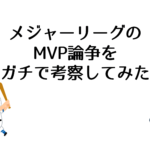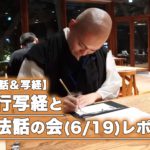スポンサードリンク
インターネットのミーム(インターネットから広まる独特の言い回しやネタ)を取り上げ、久保田が雑感を述べる「インターネット・ミーム考」。
今回のテーマは「絵師ガチャ」です。
使われ始めたのは2018年くらいからのようで、これまでに取り上げたミームの中でも比較的新しいものです。
今回はこの言葉が生まれるに至った背景や現在の出版業界の問題点などから、「絵師ガチャ」について考えていきます。
Contents
個人による創作活動がしやすい時代
携帯電話が普及し、パソコンやインターネットの利用が当たり前になった現代。
それによる様々な新しい問題も発生しておりますが、私たちはその恩恵を大いに受けながら生活しています。
その恩恵の中で、この「絵師ガチャ」という言葉の登場と関連深いのが、「個人による情報発信の容易化」や「一般有志による創作活動の活発化」です。
リアルな感情描写が多くの共感を集めた「恋空」はモバイルの小説投稿サイトを介して広まりました。
携帯電話がスマートフォンへと移り変わるに従い、当時人気を集めた小説投稿サイトは閉鎖したり、移転したりしましたが、個人による投稿は今でも活発に行われています。
いや、むしろ、現在の方が活発に行われていると言っても過言ではないかもしれません。
大型小説投稿サイト「小説家になろう」や、KADOKAWAが運営する「カクヨム」などでは、日夜多くの小説が生み出されアップロードされ続けています。
そして、一定以上の人気を集めたものや、コンテストで賞を獲得したものは、すぐさま出版され、売れ行きが良ければコミカライズ、アニメ化とメディアミックスされていきます。
例えば……
「Re:ゼロから始める異世界生活」
「転生したらスライムだった件」
「ログ・ホライズン」
「この素晴らしい世界に祝福を」
これらはいずれも「小説家になろう」に投稿され、アニメ化までされた人気作品です。
書店や大型ビジョンの広告などで目にする機会もありますから、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
趣味の創作が出版社の目に留まり大ヒット……。
そんなわかりやすいサクセスストーリーを求めて小説が投稿され続けているわけですが……。
正直なところ、今は「とにかく出版しとけ、数打ちゃ当たる」状態になっているように思います。
出版不況が叫ばれる中にあって、多種多様な人の手によって「使いやすい」原作が次々に出てくるという状況。
近年の投稿サイト原作書籍の乱発には、とにかく手数を多くしてヒット作を生み出して利益を上げたい……そんな出版社の思惑があるのではないでしょうか。
あふれる原作と「絵師」
さて、こうしたいわゆる「ラノベ」やコミックを出版する際に必要になるのが「イラスト」です。
表紙や挿絵、広告用など「イラスト」の需要は常にあります。
限られた予算の中で、多くの書籍を出版しようとした場合、イラストをどうするのか。
名の知れた絵師を起用すれば、本は売れるでしょうが予算がかかります。
また同じ絵師のイラストばかりが巷にあふれるようになっては、いずれ飽きられてしまうでしょう。
低予算かつ、オリジナリティのあるイラストを調達するにはどうすればよいか。
答えは簡単。
原作をインターネット上の投稿サイトから調達したならば、イラストもインターネットから調達すればよいのです。
twitterやpixiv、これらは在野の絵師の宝庫です。
たまたま目に留まった絵師に、イラストを依頼する。
そうすれば予算は抑えられ、特徴的なイラストを選べばオリジナリティも担保されます。
しかし、当然のことながら絵には上手い下手が存在します。
中には素人目に見ても「ひどい」と思ってしまう絵が小説のイメージイラストになってしまう場合もあるのです。
キャラクターの書き分けができていなかったり……

顔のパーツが真ん中に寄りすぎていたり……

原作の良し悪しよりも先に目についてしまうのが、絵の良し悪しです。。
皆さんはCDの「ジャケ買い」をした経験はありますか?
内容を知らずに購入を検討する場合、「タイトル」と「絵」が重要なファクターとなります。
つまり「絵師ガチャ」とは。
「出版された小説が売れるかどうかはイラスト担当者の腕しだい」という状況と「どんな絵師が担当になるかは運しだい」という状況を、何が出てくるかわからない「ガチャガチャ」になぞらえた言葉なのです。
「絵師ガチャ」の本質
たとえどれほど優れた原作だったとしても、画力の高い絵師が味方に付かなければ正当な評価を得られない。
書籍が売れなければ、続編も望むことはできません。
「絵師ガチャ」という言葉は、ある作家さんが現状を嘆いて使い始め、その後ネット上で広まりました。
この言葉からは、まるで絵師さんだけが使い捨ての商材であるかのような印象を受けます。
しかし作家さんが「絵師ガチャ」を嘆く裏で、本当に行われているのは、出版社による「絵師ガチャ」と「作家ガチャ」だと私は思います。
ガチャガチャを回してフィギュアを獲得し、それが気に入れば大切にし、気に入らなければポイ捨てする。
出版社によるクリエイター(もしくはクリエイターの卵)の大量消費という現実の、片方の側面が「絵師ガチャ」なのではないでしょうか。

確かに「絵師ガチャ」と「作家ガチャ」は出版業界における、優秀で新しいビジネスモデルなのかもしれません。
しかし、「作家」も「絵師」も、ガチャガチャの景品ではなく、一人の人間です。
「ガチャ」の景品のように、アタリ・ハズレで価値が決められるものではありません。
一人の人間が景品に例えられてしまう今の状況が健全であるとは、私にはどうしても思えないのです。
浪費されていく才能
皆さんは「蟲毒」をご存じでしょうか。
簡単に説明すると、密閉した容器に毒虫を詰め込んで、生き残ったものを最強の毒虫として呪術や暗殺に用いるというものです。

実は「小説家になろう」をはじめとするネット小説業界の現状は、この蟲毒に例えられることがあります。
毒虫(作家)を一つ所に集めて、喰らい合わせ、殺し合わせ……
残ったものだけに価値がある。
多くの作家も絵師も、過当競争の中で埋没し、残ったものだけが創作活動に携わることができる。
しかし、週刊連載のマンガで、たった一年で絵が劇的に上手になることがあるように……才能は育てるものだと思います。
ネット小説業界の「蟲毒」はこの才能の芽を摘んでしまってはいないでしょうか。
掛け替えのないもの
私は書籍というものを、本当に特別で貴重なものだと考えています。
作家さん、絵師さん、編集者さん、多くの人が携わり、知恵を出し合い、ようやく日の目を見る。
いわば、書籍は掛け替えのないご縁によって生み出された唯一無二の存在です。
しかるに、「絵師ガチャ」「作家ガチャ」が横行するネット小説業界の現状はどうでしょうか。
自分にとって都合の良いものだけを大切にし、他は切り捨ててしまう。
そんなことが許されてよいのでしょうか。
自分とつながったご縁を大切にし、育てていくというあり方。
かつて、出版社と作家、編集者と作家はそのような関係を築いていたのではないでしょうか。
ネットが発達し、出版のハードルが下がった現在でも、一冊の書籍に多くの人が携わっているということは変わりません。
あらためて、一冊一冊を大切に出版してほしいと思うのです。