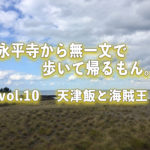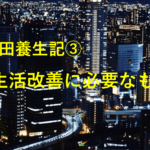スポンサードリンク
最近、曹洞宗総合研究センターからの帰り道や、実家との往復、何かにつけて歩くようにしています。
なぜなら強くなるし、ポイントが加算されるからです。
いきなり何のことかと思われるかもしれませんが、これは最近流行中の「ドラゴンクエストウォーク」(以下、ドラクエウォーク)というゲームアプリのお話。
地図とリンクしたマップの上を実際に歩きながらモンスターを倒していくゲームで、歩いた歩数でキャラクターが成長したりアイテムを買うためのポイントとして加算されていくので、ウォーキングを促すという側面も持っています。
9月にリリースされてから、有名人の方もSNS等でその様子を発信するなど、現在は「ポケモンGO」と人気を二分していると言っても良いかもしれません。
というわけで、神奈川YES! pic.twitter.com/njqtS34mCL
— 有吉弘行 (@ariyoshihiroiki) October 11, 2019
さて、私は「ドラゴンクエスト」シリーズは「テリーのワンダーランド」しかやったことがなかったのですが、ドラゴンクエストシリーズには2つのパターンがあります。
一つは、人間がモンスターを倒していくパターン。
もう一つは、モンスターを手懐けてモンスター同士で戦わせるパターン。(テリーのワンダーランドはこっち)
今回の「ドラクエウォーク」は前者で、私はこれまでやったことのないパターンでした。
操作するキャラクターはそれぞれ「戦士」「武闘家」「魔法使い」などの中から職業を選んで戦うわけですが、ここにとある職業が。
それは「僧侶」。
「戦士」や「魔法使い」の中に突然現れる「僧侶」に、私は戸惑いを覚えます。
一体どこの宗派なのか…。
というかそもそも仏教徒なのか…。
今回はそんな、ドラクエの僧侶は仏教徒なのか?というお話です。

Contents
そもそも僧侶とは?
僧侶という言葉はインドに起源を持ちます。
もともと、インドで出家をして修行をする人の集団を意味するサンガという言葉を、漢字で僧伽と表しました。
この僧伽という言葉は僧と略され、仏と法と合わせて仏教の信仰の核である三宝の一つになります。
この僧という言葉に中国語で「共にゆく仲間」という意味を持つ「侶」という言葉が加えられ、「僧侶」という言葉が誕生しました。
つまり、僧侶という言葉は古いインドの言葉と中国語のハーフということになります。
僧侶という言葉を本当に広い意味で捉えると「宗教者全般」と考えることもできなくはないですが、この成立過程から考えると、少なくとも日本では仏教徒と考えた方が良いでしょう。
ドラクエの僧侶の特徴
それではここで、「ドラゴンクエストウォーク」における僧侶の特徴を見てみましょう。
ゲーム内の説明にはこうあります。
「キズついた仲間を回復するパーティにサポート役!」
実際に、仲間のキャラクターを回復させる呪文や、防御力をあげる呪文を中心に習得する上、武器や呪文での攻撃は得意ではないようです。
「魔法使い」という職業は攻撃の呪文を得意としていることも考えると、僧侶という立場の特殊さが際立ちますね。

仏教徒ではないと思う3つの理由
では、いよいよドラクエの僧侶が仏教徒であるかどうかですが、タイトルにある通り私は「仏教徒ではない」と思っています。
服装が〜とか髪型が〜とかではありません、なんなら普段はアロハ着てる僧侶もいますし。

お釈迦様は、人は「行いによって」僧侶になるとおっしゃいました。
そう、ドラクエの僧侶は行動が僧侶ではないのです!
そう思う3つの理由を挙げてみます。
①僧侶は蘇生させない
ドラクエにおける僧侶の基本的な役割が「回復」であることは先にも述べた通りです。
傷ついた人の痛みを癒す。
つまり「苦を抜き楽を与える」ということで、これは僧侶として素晴らしい行いです。
しかし、装備した武器によってはある一線を踏み越えてしまうのです。
それは蘇生です。
特別な武器を装備した時、「ザオラル」という呪文を使って死者を蘇らせることができてしまうのです。
お釈迦様は、諸行無常という摂理の中で、老いや病、そして死との「向き合い方」を追求されました。
そして、自分自身への執着を離れることで、その恐れを離れると説かれたわけです。
それなのに、ドラクエの僧侶は蘇生をさせてしまうんです!
摂理に逆らう生き方、ましてやそれを意図的にできるなんて、なんと恐ろしい。
仏教徒なのであれば回復呪文で収めて欲しいものです。
②攻撃呪文は唱えちゃだめ
ドラクエウォークでの僧侶は、基本的に習得する能力の中で「バギ」と「バギマ」という呪文を覚えます。
これは風を起こして敵にダメージを与える呪文です。
別にね、呪文自体がおかしいわけではないんですよ。
仏教にも「真言」や「陀羅尼」という呪文があります。
これはインドの言葉をあえて翻訳せず、漢字に「音写」したものですることでその神秘性を強調したもので、真言宗に限らず曹洞宗でもよくお唱えします。
例えば「消災妙吉祥陀羅尼」という、毎朝の読経でお唱えする陀羅尼は、「災害や災難がありませんように」という願いが込められた、いわば「呪文」なわけです。
なので「ホイミ」や「スカラ」といった回復や身を守るための呪文なら、かなり仏教と近いニュアンスがあるんです。
ところがです。
自然現象を操って敵にダメージを与える!?
そんな呪文を僧侶が唱えていいわけありません。
他の苦しみに共感し取り除く、仏教徒にはあるまじき行為です。

③そもそも「敵」とかいない
そして、そもそもよくないのが「敵」という物の見方です。
ドラクエの世界では、人間が暮らしていて、そこにモンスターが現れて被害を被ると敵とみなし、倒すための旅に出るわけですが、これじゃいけないんです。
そもそも正義と悪という考え方がいけない。
戦隊ヒーローの悪役のように、自らを「悪の秘密結社」と思っている悪がどれだけいるでしょうか。
対立というのは、お互いの正義が異なることで生まれます。
仏教では「二見にわたる」と言って、どちらか一方の立場に偏ることを戒めています。
片方の立場に立ってしまうと、結局反対側は「敵」になってしまうのからです。
主張や立場が異なる時に、まず最初に必要なことは、論破や理論武装ではなく、相手を理解することです。
相手は何をどう大切に思ってその主張をするのか、それを尊重した上で話すというのが仏教的な関わり方です。
ひょっとしたら、ドラクエの世界では対話による本当の平和を目指して、僧侶が入っているのかもしれませんが、現時点ではそうは思えません。

まとめ
日本では戦国時代の「僧兵」などがあったためか、僧侶が戦うということに対する違和感が比較的弱いのかもしれませんが、本来の僧侶の在り方は「争いにならない」他者との関わり方です。
「争わない」ではなく「争いにならない」というのは、相手の感情も汲み取って尊重していく姿勢の在り方です。
ただし、ドラクエに本当に仏教的な僧侶がいたら、まあ戦闘に役立たないでしょう。
というか、そんなゲーム流行らないと思います。
ただ、敵を倒すゲームばかりではなく、敵と仲良くなるゲームが出てきたらおもしろいかもしれませんね!
ということで、ドラクエの僧侶はぼんやり何か宗教的な心を持ったキャラクターとして考えて、これからも「ドラクエウォーク」を楽しみたいと思います。
ここまでごちゃごちゃと書いてきましたが、ドラクエを通して僧侶がどんな存在かをお話できれば、というのが今回の記事の主旨でした。