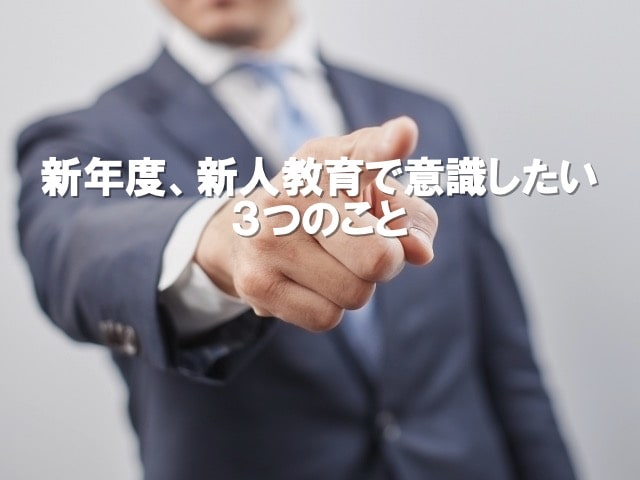
スポンサードリンク
4月に入りました。
コロナウイルスの関係で、私が所属する曹洞宗総合研究センターも在宅勤務となり、新年度の行事等もどうやらGW明けになりそうです。
ニュースを見る限り、読者の皆様の中にもその影響で例年通りの新年度開始!とはいかない方も多くいらっしゃることでしょう。
今回はそんな状況を利用して、本来であれば間に合わない新年度開始に関するお話です。
修行生活の中で学んだ、後輩との関係で気をつけたいことを3つご紹介します。
Contents
その1:礼儀は一方通行ではない
新人さんを緊張させるのが、そのコミュニティでの礼儀でしょう。
会社ではもちろん、部活やサークルでもそれぞれの礼儀があります。
そこで重要なのが、礼儀とは何かということを、先輩が忘れないということです。
新人さんが先輩への礼儀を守るというのは、慣れてしまえばそこまで難しくありません。
しかし先輩が後輩と接する時、ついついその礼儀は疎かになってしまいがちです。
礼儀といっても、ここで言うのはそんなに仰々しいものではなく、挨拶や返事、名前の呼び方など、日常のコミュニケーションレベルのことです。
礼儀というのは本来、後輩が先輩に一方的にへり下りったり媚びるために行うものではありません。
立場に関係なく、人と人の間で守られるべき「敬意の表し方」であるはずです。
新人というのは、先輩の態度に対して非常に敏感なものです。
自分を見下している人、敬意をもっていない人にはすぐに気付きます。
それで怖がりはしても、尊敬はしませんよね。
逆に、先輩が新人の自分に敬意をもって接してくれれば、威圧せずとも自然にその先輩を敬うようになるでしょう。
そして新人時代のその経験は、次の年の新人さんと良好な関係を築くことへと繋がっていきます。
全員が一方通行ではない礼儀の実践ができれば、その環境には良いサイクルが生まれるはずです。
解説
曹洞宗では、僧侶同士がお互いを仏として敬い合うことを大切にしています。
永平寺などでの修行道場では、僧侶がすれ違う際には必ずお互いに足を止めて合掌し、頭を下げます。
私が永平寺で出会った、こんな方がいます。
その方は、修行僧の指導にあたる「役寮」という立場でありながら、必ず誰とすれ違っても足を止めて合掌してくださる方でした。
どんなに急いでいる様子でも必ず立ち止まり、手を合わせ、一礼。
厳しい方ではありましたが、そんな誰に対しても礼儀を欠かない立ち振る舞いから、注意や指導がとても身に染みた記憶があります。
普段、自分に対して丁寧に接してくれる方の言葉ほど、身に染み入るのかもしれません。
礼儀というのは上下に関係なく、心を通わせるのに必要な最低条件なのです。

その2:マナーやルールを教える時は意味とセットで
どんな環境でも、新人さんに覚えてもらい、守ってもらうマナーやルールがあるはずです。
それを指導する時に大切なのが、その意味を伝えるということです。
マナーやルールというのは、必ずそれを守ることによって得られる秩序や関係性というものがあります。
名刺の渡し方、挨拶の仕方など、環境ごとに様々なマナーやルールがあるはずですが、そこに含まれる意味を指導者が踏まえておくことで、新人さんにとって覚えやすく、間違えのないものになっていきます。
私を含め、「ゆとり世代」は、納得さえできれば案外素直に言うことを聞くものなんです。
そして何より、改めてその意味を考えることで、自分にとっても、そのマナーやルールがより意味あるものになっていきます。
新年度に入るにあたって、ご自分がやっていることの意味を頭の中で整理してみてはいかがでしょう?
逆に、その意味が全くない、ただ引き継がれてきた、というものは見直しが必要になるかもしれません。
解説
曹洞宗には、修行生活の作法を「ただひたすら覚える」「無心でやる」という指導が行われた時代がありました。
しかし本来、仏教の戒律や曹洞宗の生活の作法には、一つ一つに守るべき理由が記されています。
それは以前書いた食事作法でも同様です。
このように食べることで、仏教のこういう教えが実践される、という納得があるから作法に意味があるのです。
頭で納得し、身体で示すという一連の流れの中で、人はその道を自分の人生と重ねていきます。
余計なことを考えずにこれだけ守れ!というやり方ではなく、きちんと納得をさせたからこそ、仏教の戒律は2500年も受け継がれてきたのでしょう。
がむしゃらな時期の後に、しっかりと整理して噛み締める、この作業は非常に重要だと、私は思います。

その3:後輩は、めっちゃ見てる
自分が新人の時、先輩がこちらに目を光らせていると思い、常にその視線を気にしませんでしたか?
先輩に失礼がないよう、一挙手一投足に気を張っていませんでしたか?
実はそうやって、後輩は先輩とは違う意味で目を光らせているんです。
言ってることとやってることが違うのもすぐにわかります。
でも、怒ってくることはありません。
ただ、信用だけが失われていくのです。
後輩が増えるというのは、自分の立ち振る舞いを見る目が増えたということなのです…。
解説
私は修行の一年目の冬、「修行は一年目が一番辛いのだから、二年目を迎えない方がいいのでは?」と思い、永平寺から別のお寺への移動を考えたことがありました。
その理由は、年数を重ねて楽そうにしている先輩や、一年目の終わりに向けて空気が緩やかになったのを感じたからでした。
それを師匠に手紙で相談すると、「一年目には一年目、二年目には二年目にしか見えない景色がある。環境のせいにしているうちはまだ本当の修行に出会っていない。」という返事がきました。
それを受けて二年目を迎えた私は、入ってきたばかり一年目の修行僧に注意をしなければならない場面に出くわし、気づいたのです。
「今から注意することは自分ができていなければいけないことなんだ。」と。
それまで、できなければ先輩に注意されて終わりだったところが、今度はできなければ自分の言葉が嘘になる、という状況になったのです。
私にとっての一年目は、知らぬ間に先輩や永平寺という環境に対して、受け身で耐える期間になっていました。
しかし二年目に入ると、自分の在り方が問われるようになり、言葉や行動の責任が大きくなりました。
私にとっての修行はそこからが本番だったのです。
後輩がやってくることで、責任が生まれ、その責任が私の姿勢を大きく変えてくれました。
後輩というのはある意味で先輩よりも厳しい指導者なのかもしれませんね。

後輩って、難しい
後輩の扱いが難しいと感じる方は、きっと少なくないと思います。
その理由は先輩と違って、自分の誤りを指摘したり、叱ってくれたりすることもなく、本心が見えづらいというところにあるでしょう。
私がまさにそのタイプで、先輩についていく方が後輩といるよりもずっと楽に感じてしまいます。
しかし実は、本当に自分を成長させてくれるのは、後輩だったりするのかもしれません。
叱ってくれない分、常に自分の立ち振る舞いや言動に責任を背負う覚悟が生まれます。
また、先輩の顔を立てることよりも、後輩の前で天狗になってしまわぬよう、自分を律することの方が難易度が高いでしょう。
新年度を迎え、新人さんや後輩と接するというのは、実はこれまでの人生の応用編で、決してイージーモードに突入したわけではないんです。
最後に、人間はあくまで十人十色で、どんなマニュアルも全知全能ではありません。
新人さんや後輩を自分の「下」と思わず、敬意をもって接し、その中でお互いに成長できたら素敵ですね!
























