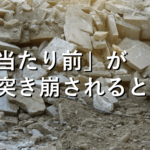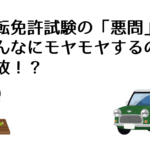スポンサードリンク
2月も下旬へと差し掛かり、今年もこの季節がやってきました。
そう、曹洞宗の修行道場の上山(入門)シーズンです。
このブログでは2年ほど前に私の永平寺上山エピソードについてお話ししました。
今回は上山からしばらく経った頃、当時の私が抱えた悩みについてのお話です。
Contents
修行の理想と現実
幸いにも、大学で曹洞宗の修行観について触れることができた私は、「曹洞宗の教えを体験できる場」を想像して永平寺へと上山しました。
しかしその上山直前、大学の恩師からは「あまり理想を求めて行かない方がいいよ」と言われ、それが引っかかっていました。
上山後、その言葉の意味が分かるまで、そう時間はかかりませんでした。
曹洞宗の修行とは、自らの行いの上にお釈迦様の姿を表すものであって、段階を踏んで上達していくようなものではない。
そう学びました。
しかし実際は、新人には厳しく姿勢を指導しておきながら、自分はさておきという先輩や、朝の坐禅や読経が終わった頃に押入れから出てくる同期など、あまりにも学んだことと異なる現実がありました。
さらにある日、何年も修行した先輩が指導役の老師から仏教の基礎問題を出されて答えられず「私は永平寺のことはわかりますが仏教はわかりません」と言ったのを聞き、何かが崩れた気がしました。

意識高い系修行僧あるある
「ここにいても自分は立派な僧侶にはなれない」
そんな思いが私の頭を満たしました。
そして私は徐々に、永平寺は大き過ぎるからいけないんだ、地方僧堂と呼ばれる小さな修行道場の密度の濃い修行ができると思うようになります。
一年目の年末、私は師匠に手紙を書きました。
「永平寺では私の思い描いた修行ができません。師匠が修行をした瑞應寺に移らせてください。」
その意思を褒められるだろうとすら思いながら、その手紙に封をしました。
それからしばらく経って、師匠から返事が来ました。
「あなたが今抱える悩みは、これまで真面目な修行僧がみんな抱えてきたものです。」
やはりそうか。永平寺じゃダメなんだなと思う私。
ところがそこから予想外の言葉が続きます。
「まだあなたは一年目の修行僧としての景色しか見ていません。二年目には二年目の景色、三年目には三年目の景色というように、後輩を迎えて初めて見えるものがあります。まずは先輩になってから考えてみなさい。」
動揺しながら読み進める私に、最後の一言が刺さります。
「環境のせいにしているうちは、まだ本当の修行に出会えていません。」
正直なところ、初めはその言葉を素直に受け入れる気になれませんでしたが、私は渋々永平寺で二年目の春を迎えることになりました。

後輩って怖い
季節が巡り、再び迎えた二月。
後輩となる新米の修行僧が上山してきました。
これまで永平寺で一番立場が下だった私が、下から二番目になる瞬間です。
自分が指導を受けるだけだったのが、指導をする側になるわけです。
そこで気づいたことがありました。
指導をするということは、指導される人に見られるということでもある、と。
これまでは間違えがあれば注意や指導を受けるだけでした。
しかし、これからは自分ができて当然の立場になっていたのです。
それに気づいてから、指導をすることが怖いのなんの。
指導したことが間違っていれば、私は別の先輩から注意を受けることになり、自分自身も間違えるわけにはいかない。
初めてまともに注意や指導をした時には、心臓がバクバクしていました。
後輩ってこんなに怖い存在だったのか!と気づいた瞬間でした。

立場が変われば景色が変わる
そしてようやく、私は師匠がもう少し残れと言った意味がわかりました。
永平寺というところは、慣れない環境や生活に耐え、先輩の目に怯える一年目こそが修行だと思っていましたが、違いました。
私はこの時初めて、「ここでどう過ごすか」を考えられるようになったのです。
それは、生活にも慣れ、後輩の見本とならなければならないという責任感、そしてあまり怒ってもらえなくなるという立場によるものです。
そしてそうなった時、師匠の言った
「環境のせいにしているうちは、まだ本当の修行に出会えていません。」
という言葉が深く胸に刺さりました。
自分のことをよくよく振り返ってみれば、納得のいかないことに対しては大学でかじった知識で理屈をこね、自分よりもずっと真摯にストイックに修行している人のことは見ないようにしていました。
自分がこんなに辛く感じるのは永平寺のシステムのせいだ、先輩のせいだ、同期のせいだ。
大学で学んだ曹洞宗の教えとはここが違う、あれがおかしい。
師匠のいう通り、環境のせいにして自分の逃げ道を作っていただけだったのです。

「理想の修行」の正体
私はようやく、自分が永平寺に対して、「都合の良い理想の修行道場像」を重ねていたことに気付きました。
恩師の言った「あまり理想を求めて行かない方がいいよ」とはこのことだったのです。
よく、修行とは辛さ厳しさに耐える、僧侶としての通過儀礼のように語られます。
もしくは、葬儀や法要の知識や技術を身に付けるための専門学校のように捉えらたりもします。
私に「大学で学んだ教えを体験できる場所」という理想があったように、そうした様々なイメージや理想を持って修行に行けば、そのギャップに苦しむことになります。
なぜならそのギャップは自分の我から生まれるものだからです。
道元禅師は、中国での修行から帰国した際、こう仰ったといわれています。
当下に眼横鼻直なることを認得して、人に瞞ぜられず、便乃ち空手にして郷に還る。
『永平広録』
簡単に言えば、目は横、鼻は縦についていること知って、何も持たずに帰ってきたということ。
これは、当時の日本では仏像や経典を持ち帰ることが修行の成果として重視されていたことが背景にあるわけですが、要するに当たり前のことに気づいて体一つで帰ってきたということです。
それは、修行とは何かを身に付けるものではなく、むしろ余分なものを手放して、本来の自分に立ち返ることを意味し、そのまま坐禅へとつながっているのかもしれません。
師匠の言った「本当の修行」とは「理想の修行」という名の我を手放すことに他ならなかったのです。

これから修行に行く方へ
現時点の私は「修行とは何か?」と聞かれたら「身に付けるのではなく手放すこと」と答えます。
それは、人によって異なるでしょうし、今後また違う答えが出てくるかもしれません。
しかし、間違いなく言えることは、修行とは「どこに行くか」「何年いるか」ではなく「どのようにいるか」だということです。
行った先を自分の修行の場として真摯に向き合えば、必ず学びがあります。
そして学んだことは僧侶としての生き方の基盤となって、一生自分を支えてくれるはずです。
新型コロナウイルスや地震など、様々な不安を抱えて上山される方は本当に気の毒ではありますが、そんな状況だからこそ修行ができてよかったと思えるよう、心から身心安寧を願っております。