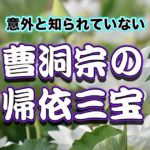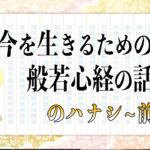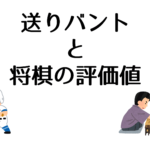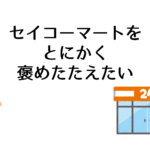スポンサードリンク
今回お送りする内容は、以前にYouTubeでお話した内容の記事となります!
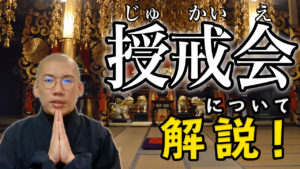
ちょっと情報量が多く、わかりづらかったという方はこちらをご一読ください!
Contents
授戒会が行われるのはいつ?
私が修行をした曹洞宗大本山永平寺では、毎年4月23日から29日までお授戒、授戒会という行事が執り行われます。
恐らく、永平寺において1年間で最も忙しいと言っても過言ではないビッグイベントとなっています。
ちなみに曹洞宗では永平寺の他に、横浜市鶴見区にある「總持寺」というお寺が両大本山となっておりますが、總持寺では4月12日頃からの1週間行われます。

戒とは?
さて、この授戒という行事、簡単に言うと、戒法というお釈迦様から続く正しい道を歩ための教え、仏教を歩む上でとても大切な教えを授かる・授ける儀式・行事になります。
受ける側は「受戒」、授ける側は「授戒」という表記になります。
ここでいう戒とは、戒めと書きますが、その意味するところはやってはいけないルールとか強制的にこれはダメという決まりではなくて、あくまでも自発的に仏教徒として歩んでいく誓いを立てることになります。
十六条戒
そして、曹洞宗で授ける戒は十六条戒といって、16個の戒があります。
それは三帰・三聚浄戒・十重禁戒という戒です。
三帰(さんき)
三帰とは、仏と法と僧の三宝(さんぼう)に帰依(きえ)することを意味します。
・仏とは、お釈迦様のこと。
・法とは、お釈迦様が説かれた教えのこと。
・僧とは、仏と法を守り嗣ぐ僧侶のこと。
これを3つの宝として、三宝と言います。
帰依とは、帰投(きとう)・依伏(えぶく)と書きますが、自分という存在を投げ入れ、伏することを意味します。
つまり仏様と、その教えと、教えを守る僧侶に対して深く敬い信じることを三帰と言います。
※一歩踏み込んだ解釈はこちらの記事をご覧ください。
三聚浄戒(さんじゅじょうかい)
三聚浄戒は、摂律儀戒・摂善法戒・摂衆生戒の3つの戒のことを言います。
・摂律儀戒(しょうりつぎかい)は、諸々の悪事をなさないこと。
・摂善法戒(しょうぜんぼうかい)は、常に善行を行うこと。
・摂衆生戒(しょうしゅじょうかい)は、全ての人を良い方向に導くこと。
つまり簡単に言いますと、悪いことはせず善いことをし、人のためになることをするという3つの戒を、三聚浄戒と言います。
十重禁戒(じゅうじゅうきんかい)
そして十重禁戒は、
・不殺生戒(ふせっしょうかい)・・・殺さないこと。
・不偸盗戒(ふちゅうとうかい)・・・盗まないこと。
・不邪淫戒(ふじゃいんかい)・・・淫らな行いをしないこと。
・不妄語戒(ふもうごかい)・・・嘘を言わないこと。
・不酤酒戒(ふこしゅかい)・・・酒を売ったり溺れたりしないこと。
・不説過戒(ふせっかかい)・・・他人の過失を咎めすぎないこと。
・不自讚毀他戒(ふじさんきたかい)・・・自分の自慢をしないこと。
・不慳法財(ふけんほうざいかい)・・・物やお金など与えることを惜しまないこと。
・不瞋恚戒(ふしんにかい)・・・怒らないこと。
・不謗三宝戒(ふほうさんぼうかい)・・・仏法僧の三宝を謗らないこと。
の10個の戒を指します。
重禁と書きますが、あくまでも破ってはならないということではなく、自ら誓うというところに戒の意義があります。
つまり、この授戒会とは16個の戒、菩薩戒を授かり、仏様がおしめしになったこの決まりを自分たち自らで守って、正しい生活、生き方を示すというのが授戒会という儀式になります。
授戒会の歴史
日本で初めて授戒を行なったのは、鑑真和上が聖武天皇に戒を授けたのが始まりとされています。
授戒会は、鎌倉時代から行われていたようですが、江戸時代頃からさらに大きな運動となっていきました。
明治時代になってからは廃仏毀釈運動などからさらに、仏教離れ、檀信徒離れが問題となっていくなかで、授戒会を確立させて大本山のみならず、全国の寺院で授戒会が盛んに行われるようになっていったと言います。
通常、授戒会は1週間かけて行われますが、現在では金銭的な問題や日程的な問題から、1週間の授戒会を行なっているのは、永平寺と鶴見にある總持寺の両本山のみとなっています。
3日間や5日間といった授戒会もほとんど行われなくなっている現状です。

授戒会では何をするの?
授戒に参加する人のことを、戒を授かる弟子と書いて、戒弟さんと言います。
戒弟さんは、1週間お寺で寝泊まりをして修行、加行することになります。
そして、朝の坐禅から始まり、朝昼晩のお勤め、お坊さんと一緒にお経をお読みします。
朝昼晩の食事も修行になるので、作法通りに食事を摂ります。
また、説戒(せっかい)と言って、先ほどお話しした十六条戒についての勉強、お話を聞いたりします。
昼間はこのように、朝昼晩のお勤めや説戒などを聞くことになります。
そして、1日目から4日目までの夜は、壇上礼(だんじょうらい)・仏祖礼(ぶっそらい)が行われます。
これは、お釈迦様から続く歴代の祖師、これまで仏教の教えを伝えてこられた、お坊さんたちに対して礼拝の行を行います。
毎日、1時間近く仏祖・祖師をお唱えするごとに、1回五体投地の礼拝を行うので、修行僧ですら大変なお勤めです。
5日目の夜には、懺悔道場(さんげどうじょう)が行われます。
キリスト教では「ざんげ」と言いますが、仏教では濁点はつかず「さんげ」と読みます。
意味合い的には似ていますが、自分が意識していようともしていなくとも、大小かかわらず積み重ねている罪に対して悔い改め、仏様の前で小罪無量(しょうざいむりょう)とお唱えし滅罪をする儀式が行われます。
6日目の夜は、教授道場(きょうじゅどうじょう)・正授道場(しょうじゅどうじょう)が行われます。
ついに禅師様、戒師様から十六条戒と血脈(けちみゃく※仏様の弟子となった証明書のこと)、そして生前戒名である安名(あんみょう)を授かる儀式が執り行われます。

最後に戒弟さんたちは、戒師さんから「衆生仏戒を受ればすなわち諸仏の位に入る。位大覚に同じしおわる、真に諸仏の子なり」という言葉をかけられます。
これは、仏の戒(十六条戒)を受ければ、仏様と同じ位、悟った人と同じことであると同時に、仏の弟子であるという証という意味です。
つまり授戒会というのは、十六条戒の菩薩戒を授かるというのは、自発的に戒を守ることをお誓いすることで仏様の弟子になること。
しかし、それに留まらず、戒を拠り所として生きていくことがそれが即ち仏としての位、悟りの世界、安らかな世界に入るということですよということであり、実はそのことがすでに仏の境地として自分が歩んでいるという自覚する儀式なのです。
これが曹洞宗で行われている授戒会の意味だと私は思っています。
まとめ
亡くなった後自分が知らないままに戒名を授けられて、仏様の弟子に入るのではなく、できれば生きている間に戒を授かり、お誓いをし、生前戒名の安名をいただくというのが、仏教徒しては理想なのかもしれません。
と、いうことで今回は授戒会の行事についてお話をさせていただきました。
私自身も、授戒した者として、「戒」を拠り所として精進し、そしてさらに参究していきたいと思います。
授戒会についてお読みいただきありがとうございました。