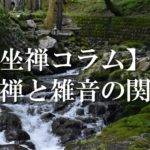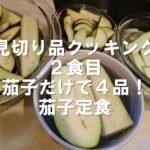スポンサードリンク
今や流行りという言葉すら当てはまらないほど、社会に定着したSNS。
私もニュースや音楽の最新情報、知人の近況など、SNSで知ることが多くなりました。
芸能人や学者、政治家に至るまで、物理的・立場的な距離を超えて直接言葉を届けられるようになったことも大きな特徴の一つといえるでしょう。
これによって思いがけない交流が生まれ、活発な意見交換や新たな流行、作品が生まれることもあります。
しかしここにきて、一段と問題になってきている感じるのが、その匿名性です。
自分の身元を隠したまま他人に暴力的・差別的な言葉を投げかけたり、必要以上に攻撃的な態度を示すことで、無益な言い争いが絶えず、事件に繋がることも少なくありません。
私はそんな様子を見ていて心配になることがあります。
それは傷つけられた人以上に、傷つける人に対する心配です。
今回はそんなSNSの匿名性がもつ危険と、自分自身が「鍵垢」をやめて変わったことをお話します。

Contents
デジタルTatoo
まずはこちらの動画をご覧ください。
こちらはACジャパンの2017年のCM「デジタルTatoo」という作品で、第55回ギャラクシー賞テレビCM部門奨励賞をはじめ、多くの賞を獲得しました。
私は今回初めてデジタルTatooという言葉を初めて知ったのですが、ネット上での発言や、一度載せてしまった写真や画像というのは、いくら匿名でも、後から消しても自分自身に刻まれていく、という意味があるそうです。
これは仏教の考え方とも非常に似ています。
私たち人間の行いというのは、どんなに匿名で、身元を隠していても、誰も見ていないところでも必ず見ている人が一人います。
それは自分自身です。
良い行いも悪い行いも常に自分だけは見ていて、どんどん心に蓄積していきます。
だからこそ匿名のSNSだから何を言ってもいいという思考が恐いのです。
鍵垢を持っていた頃の話
SNSでプライバシーを保護したり、匿名性を守るにはいくつかの方法があります。
全く個人情報を公開せず、何かあったら消せばいいという姿勢の捨てアカウント、通称捨て垢。(インターネット上ではアカウント→アカ→垢と略されるようになったらしい)
知り合いとも繋がるメインのアカウントとは別に、共通の趣味や目的の人など、限られた範囲とだけ繋がるためのサブアカウント、通称サブ垢。
そしてもっともポピュラーなのが、フォロワーや友達以外は自分の投稿を見られないようにする鍵アカウント、通称鍵垢です。
プライバシーを保護したり、交流の範囲を限定すると言う意味では、サブ垢や鍵垢は決して悪いことではありません。
かくいう私も鍵垢を持っていたことがあります。
ただしその経緯や使い方が僧侶としては不健全だったと、今では思うのです。

サークルの人間関係とSNSの苦痛
私は大学ではストリートダンスサークルに所属し、2年生の秋からはサークルの幹部として会計と広報を担当するようになりました。
ダンスサークルというとどことなくチャラいイメージがあるかもしれませんが、上下関係や挨拶には厳しく、どことなく部活のような雰囲気もあるサークルでした。
そんなサークルの幹部となって変わってきたのがSNS、特にTwitterでの人間関係。
私の代の運営方針に納得のいかない先輩やそれに同調する後輩たちの意見が、私が見ているタイムライン上で飛び交うようになり、私への批判や嘲笑も目にするようになったのです。
それまでは他愛もないやりとりを楽しみながら観ていたタイムラインが、突然自分にとって攻撃的なものになってしまったことに、私はとても動揺しました。
それからは「あの人にこう思われるんじゃないか」と、ツイートをするのも怖くなり、かといってアカウントを消したりブロックをすれば逃げたと思われるので、それもできませんでした。(正確にはできないと思っていた。)
今考えれば、自分が攻撃されている場所があると知った以上、当時の私はそこから目を離せなくなっていたのかもしれません。

サブ垢という逃げ道
そこで私が見つけた逃げ道が、名前をわかりにくくして仲の良い友達とだけ繋がるサブアカウントでした。
西田稔光のtoshimitsuのアルファベットを数字に置き換えたり逆さまにすることでt0shlwltsnというアカウントを作り、さらにプライバシー保護設定をすることで私の「サブ鍵垢」が誕生したのです。
そのアカウントでは本当に仲の良い友達や先輩、後輩とだけ繋がり、再び私の目の前には平和なタイムラインが流れるようになりました。
そうして、メインのアカウントでは広い範囲の人の色んな意見を見ながら発言はせず、サブ鍵アカウントではごく限られた範囲の知人と活発に言葉を交わす、という形が生まれたのです。

鍵垢と僧侶の矛盾
その後私は大学を卒業し、永平寺へ修行に行くのを機にメインのアカウントを削除し、鍵垢だけを残しました。
永平寺から帰ってきて曹洞宗総合研究センターに入所し、2年目で禅活-zenkatsu-としての活動を始めると、SNSは私にとって僧侶としての活動の場所の一つになっていきました。
禅活としてブログの記事やTwitter、Instagram、Facebookで仏教に関する発信を始めると、徐々にそれを見てくれる方が増えていきました。
一方では、自分の鍵垢も存在し続けていたため、公的な発言と私的な発言を分けている私がそこにいました。
そんなある日、禅活のWEBを担当してくれている堀田から学生の頃に言われた言葉を思い出しました。
「なんでわざわざこっち(鍵垢)でつぶやいてるの?気にしなきゃいいのに。」
私がそれまで鍵垢で発していたのは、少なくとも見られたくない、知られたくない人がいる言葉です。
僧侶として言葉と向き合っていく中で、これでいいのだろうか…。
そんな疑問が湧いてから間も無く、私はアカウント作成以来一度も外したことのない鍵を解除し、名前と身元を明かして再スタートを切ることにしたのです。

鍵垢をやめてよかったこと
結果的に、私は鍵垢をやめてよかったと思えることがあります。
それは
①内弁慶な自分がネット上にいなくなった
②言葉を発信をするまでによく考えるようになった
③自分の言葉に責任感が生まれた
という3つです。
①内弁慶な自分がネット上にいなくなった
これは当時は自覚がありませんでしたが、鍵垢とメインを使い分けるうちに、限られたコミュニティでだけは元気で、他の場所では静かという自分がいつの間にか出来上がっていきました。
自分に否定的な人が見ていないという安心感は、なんでも許してくれるおばあちゃんみたいなもので、その環境によって自分の承認欲求を満たしていたのかもしれません。
鍵を外し、その壁を取り払って発言をするようになったことで、いつしか「鍵垢だけの自分」という内弁慶な人格がいなくなりました。

②言葉を発信するまでによく考えるようになった
鍵を外したことで一番気になるのが、不特定多数の目に止まるということ。
ちょっとしたニュースや音楽の感想にしても、当事者に届いてしまうのがSNSです。
実際に、良いなと思ったラップの歌詞をツイートしたらそのラッパーの方が「いいね」をしてくれることなどはざらにあります。
そうやって思いがけずご本人やその関係者の目に留まる場合を考えたら、称賛でも批判でも、敬意を持って、誤解のないような言葉選びをする癖がついていきました。

③自分の言葉に責任感が生まれた
西田稔光という一人の曹洞宗僧侶として、誰でも見ることができる場所で発信するということは、見る人によっては私が曹洞宗や僧侶の代表にもなりうるということでもあります。
自分が発信する言葉には、自分一人ではなく宗派や僧侶としての責任があるということに気づけるようになりました。
宗派や僧侶としての責任を負うということは、成功した時は驕らず、失敗した時は誠実であることだと思います。
責任をもって発言をするということは、僧侶として、人間として非常に有意義であるように感じました。

せっかくなら良い自分に出会える使い方を
私は、ネットの匿名性やプライバシー設定は、悪いものだとは思っていません。
ただ、同じものでも人によっては上手に使えない場合があるということです。
私は、コミュニティを限定することで必ずしも自分に良いと言えない使い方をしてしまいました。
大切なことは、その使い方が自分にとって本当に良いと思えるかどうかです。
たとえ「いいね」や「リツイート」がなくても、思いやりや敬意を忘れずに発言することは、良い言葉を自分に聞かせることでもあります。
良い言葉を自分に聞かせるというのは、良い自分との出会いでもあります。
それは逆もまた然り。
どんなに匿名でもプライベートでも、その言葉は常に自分に返ってきているということは忘れずに、上手にSNSと付き合って行きたいですね。