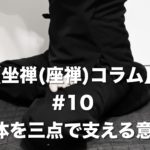暦の上では春が立ちましたが、まだまだ寒い日が続きますね。
大いに賑わいを見せた先日のほっと晩ごはんの様子をお伝えします。涅槃会にちなんだ今回は、どんな精進料理がでてくるのでしょうか?
Contents
涅槃会と枕団子について
2月15日は仏涅槃会。この日は仏教を開かれたお釈迦様のご命日であり、世界中の仏教徒がそのご遺徳を偲ぶ大切な日です。
およそ2500年前にお生まれになったお釈迦様は出家してお悟りを開かれ、40年以上にわたる説法の旅をされました。
しかしお釈迦様も寄る年波には敵わず体調を崩されます。
ある日病床に伏し、食事もあまり食べられないお釈迦様を気遣った弟子たちは、食べやすい大きさに丸めたお団子を枕元にお供えしました。
これが「枕団子」と呼ばれ、お墓や仏様にお団子をお供えする習慣の元になったと言われています。
そんな由縁から、今回のほっと晩ごはんでは涅槃会にちなんで参加者の皆さんと白玉団子を作りました。
当日の様子
会場の「こまきしょくどう」に到着された方から、メンバーと一緒に調理配膳に加わっていただきます。
店主の藤井小牧さんが契約農家さんから仕入れた食材が、下ごしらえされてテーブルに並びます。


いちごは禅活メンバー西田の地元、栃木が誇るとちおとめ。

恒例の焼き茶作り。火を止めるタイミングが肝心です。

こちらは白玉作りの様子。今回は水ではなく絹ごし豆腐と混ぜ合わせます。
こうすることでモチモチの白玉団子が出来上がるんだとか。

白玉粉とお豆腐がしっかり練りあがったら、みんなでお団子を丸めていきます。
真ん中を凹ませることで火が通りやすくなります。
キレイな形の白玉が出来る頃には、参加者の皆さんも打ち解けて、とても和やかな雰囲気に。



仕上げに盛り付け。鮮やかな野菜の色合いが素敵です。

いす坐禅&食作法
いす坐禅と食作法の案内は深澤亮道が担当します。
初めての方でもご心配なく。
ひとつひとつの作法を丁寧にご案内します。



いす坐禅で姿勢と呼吸を調えたら、いざ精進料理をいただきます。
今回の献立は…
雑穀粥
人参のきんぴら
法蓮草とキャベツの胡麻和え
蕪の生姜葛引き
漬物
胡麻塩

作法に沿って短いお唱えをして、いただきます。


食材を生かした素朴な味に時折驚きの声が上がります。
お粥をおかわりする人もちらほら。もちろん筆者もおかわりしました。
食べ終わったらお茶の給仕。残しておいたたくあんで食器をぬぐい、きれいにします。



きれいに洗えたら最後にもう一度お唱えをして、ごちそうさまでした。

茶話会
デザートは皆さんで作った白玉団子をいちご豆乳でいただきます。
いちごのさわやかな酸味と、モチモチした白玉団子の相性はとても新鮮でした。

茶話会では西田稔光がお話をしました。
なにやら最近、彼はyoutubeデビューしたんだとか!?ぜひ事の真相をチェックしてみてくださいね。
今回のお話は、枕団子に見る食と人の出会い、別れについて。

古くは日本の神話から、食は人間関係の節目に関わってきました。
スタジオジブリの『千と千尋の神隠し』(2001年)では、千尋が「千」として神の国で暮らすのに、まずはその土地のおにぎりを食べたことや、キリスト教で言えば最後の晩餐など、いかに食が出会いと別れに大きく関わっているかがわかります。
そして、辺見庸氏の著作『もの食う人びと』に描かれる人間の命の物語を紹介しながら自身の経験についてお話しました。食によって、人は単に命もしくはカロリーを「摂っている」わけではなく、食によって「繋がっていく」ということをお伝えしました。
最後に各々が思ったこと、感じたことをシェアしてこの日の「ほっと晩ごはん」は終了しました。
諸々予告
次回のほっと晩ごはんは3月6日(水)を予定しています。様々な節目を迎えるこの時期に、精進料理で心と体を調えてみてはいかがでしょうか。
申し込みはこちらからどうぞ
そして、今年新しく始まった
一行写経と法話の会 も毎月開催中です!
2月18日の第2回も、まだご参加いただけます!
未経験の方も大歓迎ですので気軽にお越しください。
参加希望の方はこちらから!
今回紹介した本