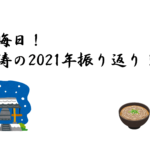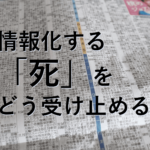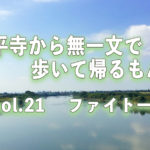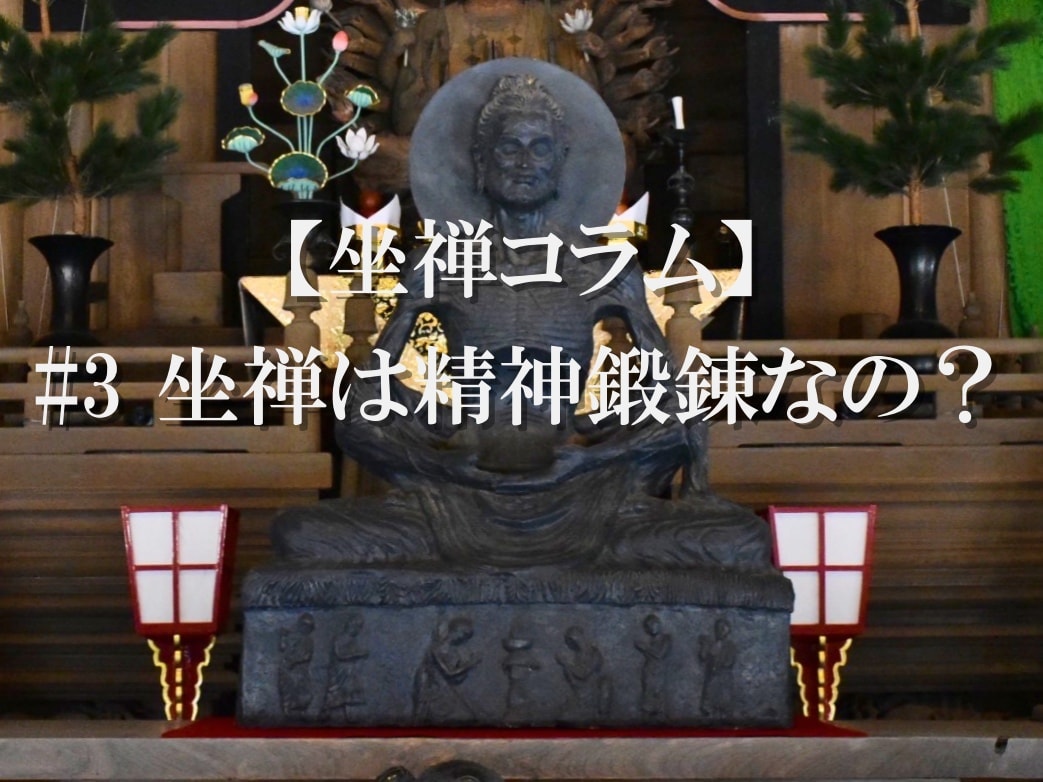
スポンサードリンク
坐禅を体験した人、これから坐禅をしたい人が気になる坐禅のアレコレについてつぶやくこちらの【坐禅コラム】。
坐禅というと、雑念を払い、精神統一をし、痛みに耐える厳しさが魅力として伝えられやすく、そのイメージが世間にも定着している部分があります。
しかし、結論から言うと実際の坐禅は決して厳しさや痛さに耐え、忍耐力を高めるための修行ではありません。
今日は真面目で熱心な人ほどしてしまいやすい「坐禅と忍耐」のお話です。
Contents
坐禅のイメージ
近年、ヨガやマインドフルネスの流行の影響か、リラックスをしたい、癒されたいというきっかけで坐禅に興味を持たれる方が増えてきました。
しかし、ひと昔前はアスリートや新入社員、さらに遡れば軍人が精神鍛錬のために坐禅を取り入れることが多くありました。
実は、厳しい坐禅に耐えることで忍耐力をつけようとされる方は今でもよくいらっしゃいます。
以前、とある坐禅会で会場の坐蒲(坐禅用のクッション)が使えないということがありました。
そこで急遽、その日はいす坐禅をしようということになり、坐禅堂ではなくいすのある場所に会場を移すことに。
すると、参加者のお一人が「私は坐蒲無しでも坐禅をします。坐禅は我慢大会ですから。」とはっきり仰ったのです。
その方は結局お一人で坐禅堂に残り、坐蒲無しで坐禅をされました。
申し上げておきますと、私はその方を批判するつもりは一切ありません。
ただ、それくらいに坐禅には我慢・厳しさ・忍耐というイメージが根強くあるということです。

お釈迦様と坐禅
仏教を説いたお釈迦様は、自分の老・病・死への苦しみを解決するために出家をしました。
そしてその修行の過程で苦行に身を投じます。
当時、インドの出家者の中で行われていた苦行には、非常に多くの種類があります。
息を止める、痛みに耐える、断食などなど、苦しければ苦しいほどその功徳が高いとされ、その苦行の末に亡くなると、それは偉大な修行者として称えられました。
なぜこうした苦行をするかというと、自分の欲を断ち切るためです。
特に、お釈迦様が選んだ断食は、食欲を断つためのものでした。
その断食の凄まじさは、今も断食像として伝えられますが、このように骨と皮だけになるほどのものだったそうです。

その凄まじい断食は、体力が弱ることで一時は食欲を無くすことができましたが、ひとたび水を飲んだり少しお粥を食べればすぐにまた食欲は湧き上がっていきます。
そこでお釈迦様は苦行の中に答えはないと感じ、その生活に終止符を打ちました。
そしてスジャータという村娘からの乳粥の供養を受けて栄養をとり、沐浴によって体をきれいにすると、菩提樹の下で坐禅を組んだのです。
苦行を離れて選んだ修行が坐禅だったと考えると、少なくとも坐禅が苦行でないことがわかります。
弦楽器のたとえ
そしてお釈迦様は坐禅の中で、自らの苦しみを解決する答えを見つけます。
それが仏教の「覚り」であり、この坐禅に立ち返ったのが曹洞宗でした。
つまり、曹洞宗の坐禅もまた苦行ではなく、苦しみから解放されるものです。
そんな苦行ではない修行の在り方に関する、重要なお釈迦様の言葉があります。
ある日、お釈迦様にソーナという大変熱心な弟子が尋ねます。
「一生懸命に修行をしていますが覚りにたどり着けません。どのように修行すれば良いでしょうか?」
お釈迦様は答えます。
「ソーナよ、そなたは出家の前は弦楽器の名手だったそうですね。弦楽器の弦は弱く張るとどうなりますか?」
ソーナは戸惑いながらも答えます。
「はい、それでは音が出ません。」
するとお釈迦様はさらに重ねます。
「それでは弦を強く張りすぎればどうなりますか?」
ソーナは再び答えます。
「それでは今度は弦が切れてしまいます。」
そこでお釈迦様は仰います。
「そうです。弦を弱く張っても音は出ないし、強すぎれば切れてしまう。修行も同じことでなのです。」
ソーナはハッとしました。
真面目で熱心な性格が故に、気を強く張り詰めすぎていたことに気がついたのです。
頑張るということ
私たちは努力をするという意味でよく「頑張る」という言葉を使います。
しかし、「頑なに張る」と書いて頑張る読むように、人間にとって頑張るというのは決して楽なことでありません。
ピンと張り詰めすぎた心の弦は、ちょっとしたきっかけで簡単に切れてしまいます。
同じように、脚の痛みに耐えたり力いっぱいに背すじを伸ばすような坐禅もまた、ちょっとしたほころびで切れてしまうような非常に危うい部分があります。
例えば、怪我や病気で今までと同じように坐禅をすることができないとなったらどうでしょう?
その形にこだわっていると「もう坐禅ができない」と思い込んでしまうはずです。
そうではなく、脚が痛い日は脚が痛くない坐り方をしたり、体調が悪ければその日はしっかり休む。
無理をして坐禅をすることは、結果的に坐禅をやめるきっかけになってしまう可能性があるのです。
ただでさえ社会生活や私生活の中で頑張ることや成功することを求められる私たち。
坐禅は呼吸と姿勢を調えることで、日常で張り詰めすぎたり緩んだ心をチューニングするものです。
それは精神を鍛えるというより、結果的に精神が柔軟になるものと言った方が近いかもしれません。
今、現代人に本当に必要なのは、どんなことにも動じない強さや頑丈さではなく、地面にしっかりと根を張りながら枝を揺らし、雨風に負けない大木のような柔軟さなのではないかと私は思います。
今、頑張ることに疲れた方にはぜひそんな柔軟になる坐禅に触れてみてはいかがでしょうか。