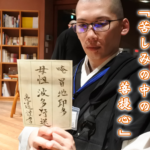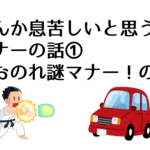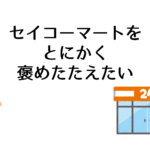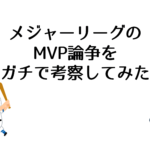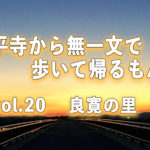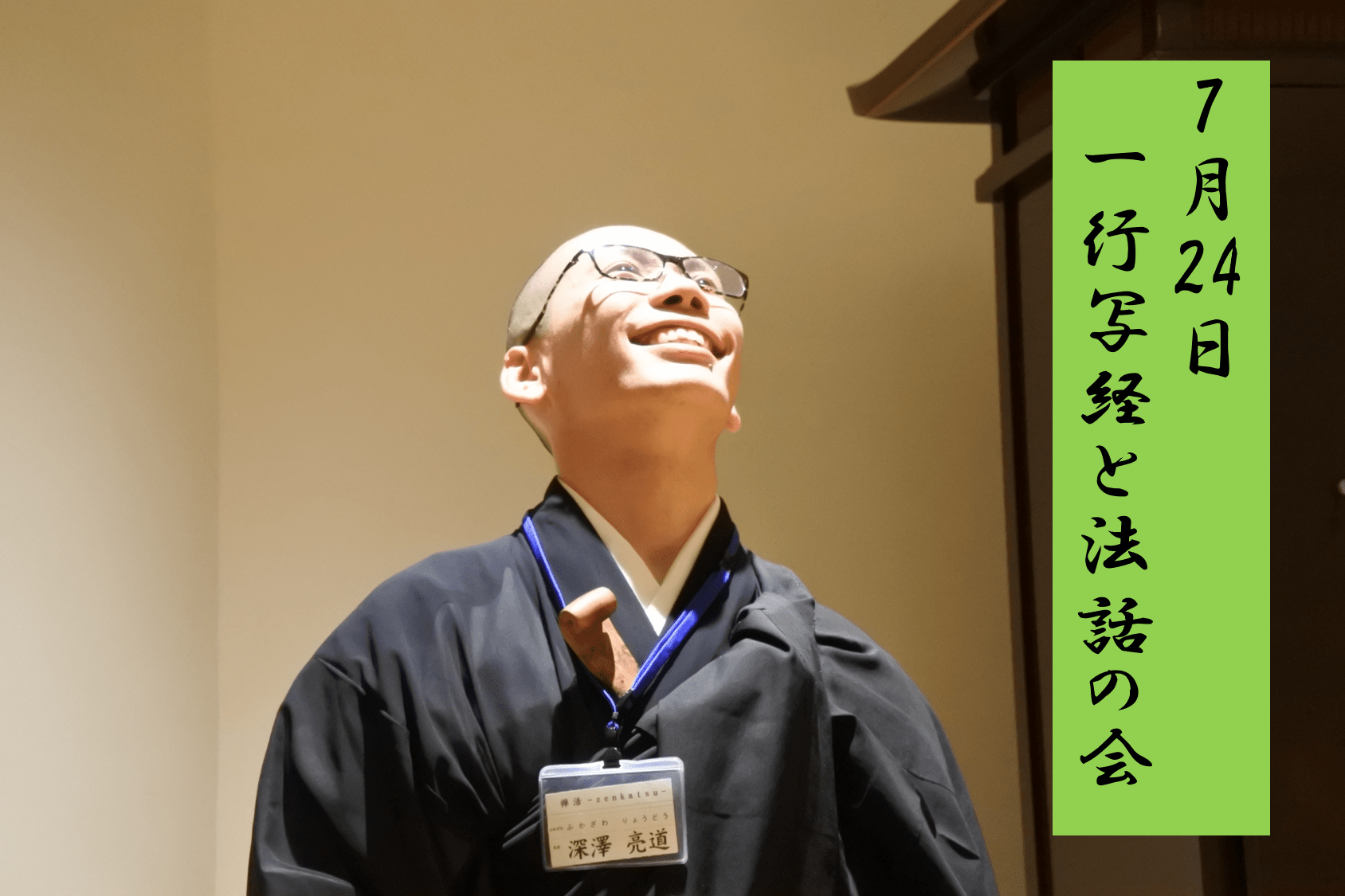
スポンサードリンク
今週も四ツ谷東長寺さま、文由閣で一行写経と法話の会を開催いたしました。
7回目となる一行写経と法話の会。
今回はな、な、なんと!過去最多、7名の参加者さまにお集まりいただきました!(うれしい!)
禅活メンバーは久保田、西田、深澤の3名。
いつもより一層賑やかに始まった一行写経と法話の会。
その様子を、禅活の宴会部長。久保田がお送りします。
Contents
法要&法話
本日の法要導師は深澤亮道さん。
_190726_0050-min-300x200.jpg)
この表情を見てもわかる通り、リラックスして臨んでいます。
西田さんが鳴らす木魚と鐘の音に声を合わせて……
_190726_0041-min-1-300x200.jpg)
文由閣に、般若心経の読経が心地よく響き渡ります。
_190726_0043-min-300x200.jpg)
厳かな法要の後は法話に移ります。
ボランティア活動に身を投じる一人の男性の生き方に、深澤さんが深く感銘を受けた経験をお話しいたしました。
_190726_0034-min-300x200.jpg)
法話はこちら↓
本日の写経
法話の後は写経です。
まずは身体と呼吸を調えて、いす坐禅。
_190726_0024-min-300x200.jpg)
墨を擦り……
_190726_0023-min-300x200.jpg)
筆ならし(今回は永平寺の「永」の字を書いてもらいました)をしたら、いよいよ本番!
_190726_0020-min-300x200.jpg)
今回は『甘露門』の一節である「発菩提心陀羅尼」を写経してもらいました。
_190726_0005-min-300x200.jpg)
_190726_0009-min-300x200.jpg)
「唵 冒地即多 母怛波多野迷」
昔のインドの音を漢字で表したものなので、パッと見たでけは意味がわかりません。
これは『甘露門』で供養される餓鬼たちに、菩提の心を起こさせるというお経です。
さて、写経というと、お手本を写経用紙に透かして写すという方法が一般的です。
これまでは自由度の高い写経をしてもらおうと、お手本を横においても、写し書きでも、両方OKというやり方を取ってきました。
しかし、お手本を横において写経された方の声を聴いていると、どうしても書く字の形やバランスに気が取られてしまうようでした。
確かに上手な字には憧れますし、そのように書きたいと思うのも自然なことです。
ただ、写経の意味からすれば、字の上手い下手は関係ありません。
たった一回の写経に誠心誠意、心を込める。
そのためには、やはり、お手本を透かして書く方がいいようです。
_190726_0016-min-300x200.jpg)
写真を撮っている私も、本当は混ざりたい……(笑)
茶話会
本日の茶話会は、2テーブルに分かれて行いました。
すっかりテンションの上がった久保田が居酒屋トークを繰り広げている横で、
落ち着いたお話をする深澤さんに、
_190726_0051-min-300x200.jpg)
まじめに仏教の話をする西田さん。
_190726_0012-min-300x200.jpg)
<※写真はイメージです(笑)>
メンバーの個性が良く出た茶話会になった気がしますが、お楽しみいただけたでしょうか。
最後は集合写真を撮って、一行写経と法話の会は終了!
_190726_0002-min-300x200.jpg)
参加された皆さま、ありがとうございました!
次回予告!
次回の一行写経と法話の会は、9月25日19:00~20:30に開催いたします!
(8月はお盆のため、おやすみします)
場所は変わらず、東長寺文由閣。
多くのご参加をお待ちしております!
Peatixからのお申し込みはこちら
Googleフォームからのお申し込みはこちら