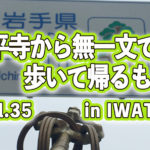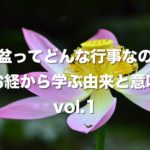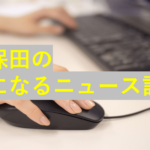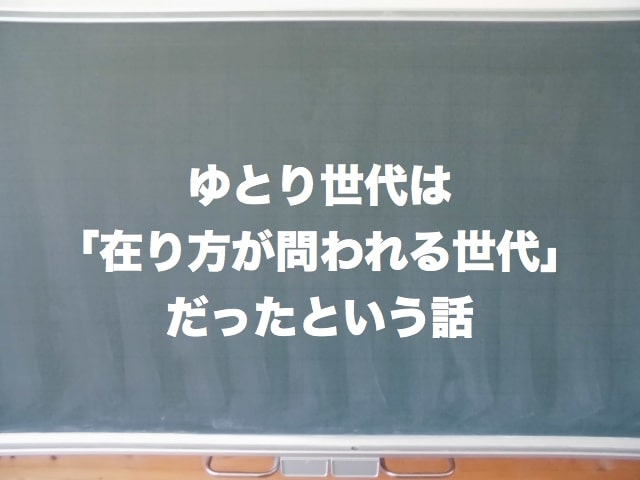
スポンサードリンク
とある飲み会の席。
ほとんどお酒が飲めない私は、たとえ先輩やご年配の方からの勧めといえど、お断りしてしまうことが多々あります。
そして勧めてくださる方の胸のうちにも、アルハラになることを危惧する気持ちがあるのか、穏便に済むことがほとんど。
しかし、時々そうした場面で聞こえてくる言葉があります。
「これだからゆとり世代は…。」
平成3(1991)年生まれの私は、小学校に入学した時にはすでに第2・4土曜日は学校が休み、4年生の時に週5日制になったTHE・ゆとり世代。
ということで、大人になるにつれて度々競争を生き抜いて来られた大先輩から、こうしたゆとり世代を羨む発言を頂戴してきました。
今回はそんなゆとり世代と呼ばれる自分にとって修行とはなんだったのか、そしてどう生きるべきなのかを考えてみたいと思います。
Contents
修行道場の変化
厳しい修行って何?
私が信仰している日本曹洞宗は「修行が厳しい」と特徴づけられることがよくあります。
確かに、大本山永平寺を開き、日本の曹洞宗の教えの基礎を説かれた道元禅師という方の書物を見ると、綺麗好きで、細かくて、仏道に対して尋常じゃなくストイックだったことがわかります。
そんな方が遺された修行生活の作法や規則は確かに緻密で、「そこまでやる?」と思うようなこともあります。
しかし、それは「こうすればお釈迦様と同じになって、心も自然と落ち着くよ」という、言ってしまえば親切心からくるもので、苦しめようなんて想いは毛頭なかったはずです。
それを「厳しい」と感じるのは、道元禅師の説いた修行生活とそれまでの自分の生活にギャップがあるからです。
つまり、修行を厳しく感じるというのは、それだけ自分が曹洞宗の教えから遠い生き方をしていたということでもあるはずなんです。

罰を受けた人、与えた人
ただしそうではない、誤った厳しさもあります。
曹洞宗には、戦時中に軍人が感心するほど、気合いや根性、絶対的な上下関係による「厳しい修行」を是としてきた時期があります。
それは戦後、さらに平成に入っても続き、見直されてきたのは平成の後半、私が入門する少し前でした。
昔の修行を経験した先輩僧侶は「罰のあれが辛くてさ〜」と、青春を振り返るかのように罰を受けたことを語ることがあります。
それは同時に罰を与える側の僧侶がいたことを意味します。
実は、私が永平寺に入門した時、2年目には本田、4年目に深澤がいました。
この中で深澤は、先輩から罰を受けた世代です。
そして本田が入門する前の年に大きな見直しが行われ、修行僧間での罰のやりとりは全面禁止になりました。
そもそも、仏教に人が人に罰を与えるということは認められていなくて、お釈迦様の時代にはあったとしても生活規則を守らなかった人を程度に応じて「反省<無視<追放」という措置があっただけでした。

ゆとり=甘やかされる?
さて、そうなると当然、罰を受けてきた世代と比べて、罰を受けたことのない世代は緊張感が異なってきます。
話を聞けば、社会でそれをやっていたら大問題になるようなことをする人もいたようなので、昔の人が怯えたのは当然です。
一方で「怒られるとしてもこれくらいで済むだろう」という感覚が生まれてしまえば、緊張感が無くなってしまう部分があるのも当然です。
そしてこの「緊張感がない」と言われるのが、ちょうど私たちゆとり世代になってくるわけです。
昔と比べれば叱責以上のことはほとんど無くなり、年数を重ねれば叱責すらされなくなっていきます。
そんな私たちを見て、昔を知る人は「今はずいぶん甘くなったなあ〜。」と納得のいかない面持ちでそうに言うのです。
確かに、罰や叱責の恐怖が大きければ大きいほど、緊張感やその「厳しさ」を乗り越えた達成感も大きいでしょう。
しかし、そうした恐怖が弱まっていたからこそ、「別の厳しさ」が存在していたと、私は思います。

「どれだけいるか」ではなく「どういるか」
以前、私は修行二年目で現在の禅活メンバーであり当時の超先輩修行僧の深澤に怒られ、自分の横着さやだらしなさに改めて気付いたことを書きました。
私は24歳になるその年に、すでに永平寺で一年を過ごしたにも関わらず、幼い頃からの自分の欠点が根本的に変わっていないということに気づくことができました。
おそらくそういう部分も、先輩からの罰や叱責が激しければ、否が応にも改まっていたでしょう。
しかし、ゆとりのある修行生活の中では、自分自身が意識しない限り、強制的に変えてもらえることはないのです。
それは自分の在り方を自分で意識し、問いかけない限り、長所が伸びることも短所が改まることもなく時間が過ぎていくという非常に残酷な「厳しさ」でもあったように思います。
ゆとり修行の世代である私たちは、修行道場で「どれだけの時を過ごすか」ではなく「どのように時を過ごすか」という、自分自身の在り方が問われていたのです。

結局、ゆとり世代とはなんなのか
ゆとり世代の私は、当時それが「ゆとり教育」であることなどつゆ知らず、休みが増えた!やったー!くらいにしか思っていませんでした。
つまり教育について特別勉強したわけではない私にとっては、学校教育=ゆとり教育のことで、そこにどんな目的があったかなんて知る由もなかったのです。
そこで、改めてゆとり教育が実施された背景を調べてみると、受験戦争や競争の中でとにかく生徒に詰め込むようなスタイルだった学校教育を、生徒自身が考えるように促すことが目的であったことがわかります。
確かに、修行でもゆとりがあったことで、色々な矛盾や疑問を抱くことができ、結果的に修行生活の良いところも見えてきて、現在の活動にも繋がっています。
しかし、このゆとりをただの緩和と考えて、怒られないから、強制されないから適当でいいと考えてしまうと、上の世代からはゆとり世代がモンスターに見えてしまうのでしょう。
人生の諸先輩方の、ゆとり世代の私たちには想像のつかない厳しい、辛い経験をしてきたからこその言葉や生き方には、学ぶことや感服することがたくさんあります。
しかし私はゆとり世代も、実はある意味で非常に厳しい環境に置かれているのだと思います。
それは、教育に中で作られたその「ゆとり」の中で、自分がどのように生き、どのように在るかを無言のまま問いかけてきている社会のことです。
「やっぱりゆとりはダメだった」と言われるかどうかは、私たちがゆとりをどう使うかにかかっているのかもしれません